�g��F��
�l���ƍٔ����̌����@�@���]�͍_�搶�@�@16PJ10003 �g��F��
���_
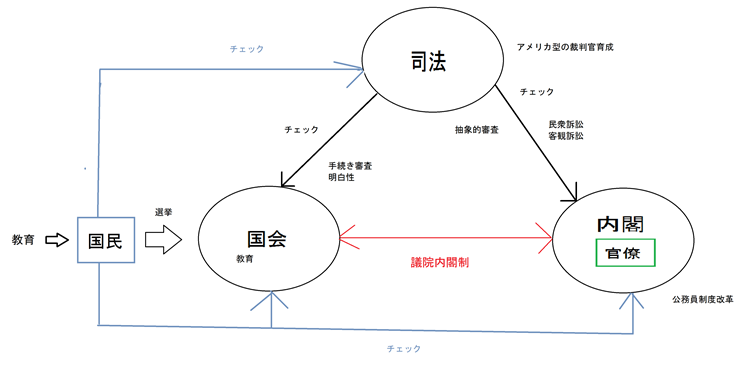
�͂��߂�
���͂��Ƃ��ƒ��ۓI�Ŕ����̎���̈������@�̕��������Ȃ̂ł����A����Ȏ��ł�����̃e�[�}�́u������Ə�����̂ł́I�H�v�Ǝv���Ă��܂����B�Ƃ��낪������ɂ�ăh�c�{�ɂ͂܂蔲���o���Ȃ��Ȃ�܂���(�E_�E;)�@���]�搶�̃e�[�}�͂��������Ȃ̂ł����A�˂��l�߂Ă����Ƒ����[���Ȃ��Ă��܂���ł���ˁE�E�E�B���������l�����e�[�}�ł�������͂��Ȃ�L�����[���B�ł��̂ŁA�����̗\��ʂ�T���b�ƑS�̂��O�ς��Ă�������l��������_���������悤�Ǝv���܂��B
�\���͏��_�E�{�_�E���_�̌`��
�@
�i�@��
�A
���_
�B
��
�̏��Ō������܂��B
�@
�i�@��
�܂��͎i�@���͈̔͂m�ɂ��܂��傤�B
�u�@����̑��ׁv
�ٔ����@�R���Ɣ܂玖������u�@����̑��ׁv���A�[����܂��B
�v���@�i�T�j�����ҊԂ̋�̓I�Ȗ@���W�܂��͌����`���̑��ۂɊւ��鑈���@�@�{�@�@�i�U�j�@���̓K�p�ɂ��I�ǓI�ɉ����ł��鑈��
���̗v���ɍ������̂Ȃ�i�@�͔��f�ł��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�u�i�@���̌��E�v
�@����̑��ׂ������Ă����̂��͎̂i�@�����f�ł��Ȃ������ł��B
�u�����s���v�u�����Љ��v�u�ٗʍs���v
�ጛ���@�R����
�x�@�\�����i�ׂ���u�t���I�ጛ�R�����v���A�[����܂��B
����ɁA�ጛ�R���ɂ����Č��@���f�����Ȃ��ʼn����ł��鎖���͌��@���f�������Ƃ����u���@���f����̏����v�������܂��B
���ǁA�ጛ�R���ɂ́u�@����̑��ׁv�{�u�t���I�R�����v�{�u���@���f����̏����v�{�u�i�@���̌��E�v�Ƃ����ǂ����邱�ƂɂȂ�܂��B
�ጛ���f
�u����������߁v�Ɓu�K�p�ጛ�v�Ƃ����ǁB����Ɍ��ʂɊւ��āu�ʓI���͐��v������܂��B
�i�@���Ɏ�`
�O�������Ƃ����V�X�e����A�i�@�͍���E���t�̔��f�d���ċɗ͌����o���Ȃ��Ƃ����l����������܂��B
�s�������i�ז@
���Ƃ��Ǝi�@�͖����ƌY�������������Ă��肨��͈��������Ȃ��Ƃ������Ƃ���s����i���邱�Ƃ��o���܂���ł����B���ꂪ�s�������i�ז@�Ȃǂ̓����ɂ�菭�����i���邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ��Ă��܂����B
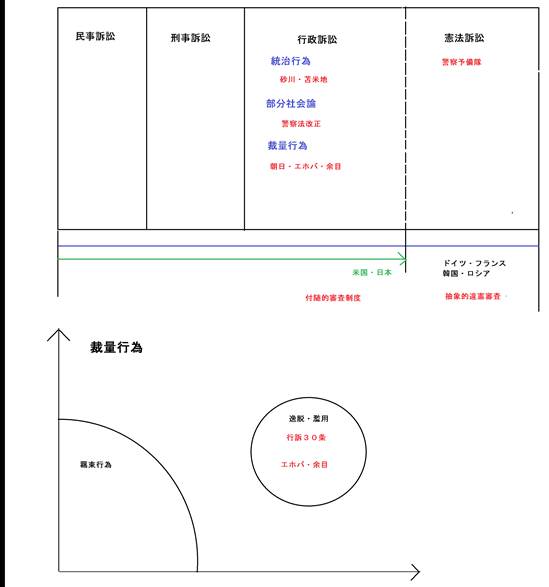
�o�T�F���]�͍_
�}�ɂ���Ƃ����Ȃ�܂��B
���̎i�@���Ŏ������ق������ʂǂ��Ȃ�̂��H�Ƃ������Ƃ����͌������܂��B
�A
���_
���@�̔����F�X�Ɠǂނ킯�ł����ǂ̔������������肵�����Ƃ������Ă����ł���ˁB���Ԃ����͂��Ă���Ƃ��ꂾ���łƂ�ł��Ȃ��ʂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���̖��_�ł͎��̍��܂ł̕�����ɓƒf�ƕΌ��Ŕ����S�̓I�Ɋώ@�����_�����悤�Ǝv���܂��B
�@����̑��ׂ��M���̎��R
�܂玖��
�@�؎�����
������������
�����͖@����̑��א����Ȃ���������o���Ȃ����Č������킯�ł����A���̂��G�z�o�̏ؐl�A�������E�������Ƌ��ێ����ɂ͌����o���̂ł��傤���ˁH
�A���������M���̎��R����n�܂����Ȍ��茠��ʂ��āA���@���f����肭�������`�Ŗ��@�E�s�@�s�ׂ̐l�i���ɒH�蒅���A���ǃC���t�@�[���h�R���Z���g�̖��ʼn���������B�܂��Ɍ��@���f����̏������g���I�݂ɋc�_������ւ����͖̂��������Ǝv���Ă��܂��B�����������������ł���ˁH�I�܂�͍��\���������画�����o�����Ƃ��o�����̂ɏo���Ȃ������B����A�������͍��\���y���ɓ�����e�ł���B�����āA�A�����ꂽ�G�z�o�̐l�������c���Ă���̂Ɍ��Lj�t���������B��������t�Ŗڂ̑O�Ŏ��ɂ����ɂȂ��Ă������t���p�^�[�i���Y���Ȃǂ��l�Ƃ��ď�����ł��傤�B
�Ȃ̂ɁA�M�����������疽���������̂ɐ������Ȃ��������畉�����ł����ˁH���ʂ̐l�Ȃ當���芴�ӂ��o�����ȃV�`���G�[�V�����ł����ǂˁ`�B�M������Ƒ��Q��������Ƃ������Ƃł��傤���ˁH
�����̓��e�͕�����܂���I�����Ă��鎖�͂������Ƃ��ŁA���O�ɐ�������ĂȂ����^���ȐM���f��@��Ȃ��������l�i���̐N�Q�Ƃ����_���͗����ł��܂��B
�ł��ł���A���ǂ̂Ƃ���܂�ŏ@���ɂ͌����o���Ȃ��ƌ������̂ɏ@���̖��������Ƃ����悤�Ɏ��ɂ͌����܂��B
�������Ƌ��ێ����������ł��B���e���ٗʍs���ɎЉ�ϔO�R���Ɣ��f�ߒ��R���̍��킹�Z�ňጛ�����f���炵�������ł��B�ł����A���Ǐ@���Ɍ��o���Ă܂����
���̃��|�[�g�Ƃ͊W�̂Ȃ��܂��ɖT�_�ł����A�M���̎��R�͍����@���������ɉ����t������R���g���[���������h�~���邽�߂̂��̂ł���ˁB���_�I���R�̈�œ�d�̊�_����l���ďd���̂͗ǂ�������̂ł����A�@����̋��`�Ɋւ��锻�f�͏o���Ȃ��킯�ł�������p�Ƃ����Ώ����������̂ł͎v���܂��B����ɍ����S�̂ŏ@��������Ă���l�͏��Ȃ��ł����ǂ��炩�ƌ����Αn���A�G�z�o�A�I�[���Ȃǃl�K�e�B�u�ȃC���[�W������l�������Ǝv���܂��B���Q����K�v�͂���܂��@�l�ł₨�z�{�Ɋւ��Ă��D������K�v�͂Ȃ��ł��傤�B���z�{�̘b�ɂȂ����Ƃ��Ɂu������̉��Ɠ����v�Ƃ������Ƃ��܂����A�n���w��̂悤�ɂ������܂ő傫���Ȃ��Đ����ɐH�����ނقǂȂ̂Ɂu������̉��Ɠ����v�Ƃ͂ƂĂ��v���܂���ˁB�C�O���M���̎��R��������ی삳���̂͂������ł���ˁB�Ȃɂ����@�����̓��{�ő����𑵂݂���K�v�͂Ȃ��Ǝv���܂��B
����Ȃ��Ƃ��l���Ă���ƌ������Ƌ��ێ����ő�֎�i������Ă����邱�Ǝ��̂��D�����Ă���ƌ������w�Z���̎咣�ɂ͋����ł��܂��B�����A�w�Z�����G�z�o�̏ؐl�ւ̔��Q����̎����ł�������ٗʌ��̗��p�ƌ����Ă��d���Ȃ��Ǝv���܂��B
���������������Ƃ����ƁA�����͘_�����������肵�Ă��Ė��Ȃ��ł����܂玖���Ƃ̊W�Ő��������Ƃ�ĂȂ��Ɗ�����Ƃ������Ƃł��B
�����s��
���쎖���i�����s���{�������j���a�R�S�N
�ϕĒn�i�ׁi�����������s���j���a�R�T�N
���쎖���Ɋւ��āA�������������̕����ȒP�Ȃ��Ɓi���D�ʐ��j�A�����������t�̎d���ł��邱�Ƃ��l����Ɩ����������Ďi�@�R���̉\�����c�����̂͗ǂ������Ǝv���܂��B
�������A���쎖���̌�ł���ϕĒn�i�ׂɖ�������t���Ȃ������̂͏O�c�@�̉��U���ɂ��Ă͎O�������d�����Ƃ������Ƃ��Ƃ��Ă��A�����������̂悤�Ɋ����Ă��܂��܂��B�O����������Ȃ̂������Љ��Ȃ̂�������܂��A���U����ߒ��ł������Ȏ������̂��c�����b�ł���ˁB���U�Ƃ������ʂɂ��Ă̐R�����o���Ȃ��Ă����U�Ɏ���ߒ��̐R���͉\���Ǝv���܂��B�u���̔��f�͎匠�҂��鍑��
�ɐ����I�ӔC���Ƃ���̐��{�A����̐�������̔��f�Ɉς���A�ŏI�I�ɂ͍����̐������f�Ɉς˂��Ă���B�v�Ƃ����̂͗ǂ�������̂ł����A�匠�҂��鍑���͉����o����̂ł����H�H
���U������A��������A�W�c�I���q���̉��߂�ς�����E�E�E�B�I���ł����H����}�ɔC������_���_���ŁA�����}�����Ȃ����玩���}�ɂ���āA�m���ɃA�x�m�~�N�X�ɂ͂�����Ɗ��҂��܂����������Ɉ�[���ꂽ�킯�ł͂Ȃ���ł���ˁB�s���ƍ���������f�������킯�ł��Ȃ��A�����ւ̗��_����I���ɂ��������A���[���R�O�����炢�Ō��܂����z�珟��ɂ���Ă���̂ɐ����I�ӔC�H�H
���ǂ̂Ƃ���匠�҂��鍑���͉����o���܂���B���ɍ������[�����Ă����t�͂��̌��ʂɔ����Ȃ��̂ł���H�z��̍D�����肶��Ȃ��ł����B���@�͂�������������̂Ȃ̂ɁA���̌��@��B��s�g�ł���ٔ����������s����R�����Ȃ���ΒN���o���Ȃ��ł��傤�B�w���̒��ɂ������s�ט_�͕K�v�Ȃ��Ƃ����l�������̂Ƃ����܂��B���������v���܂����A���ɎO���������������s���ւ̑��d���������Ƃ��Ă��K���i�@�ɂ��R���̉\�����c���ׂ����Ǝv���܂��B
�����Љ�_
�x�@�@�������������@����ւ̉���͗��@��p�ɂȂ��Ă��܂��ʂ�����̂ŋɗ͔�����Ƃ����̂͗ǂ�������̂ł����A�܂�����������Ȃ��Ƌc���̂�肽������ł����Ƃ����Ǝ����}�̂�肽������ʼn����ꂽ�@�������̒��ɏo�Ă��Ă��܂��܂��B�����s���Ɠ����c�_�ł��������͉����o���Ȃ��̂ŁA�葱���ւ̐R���͉\�ɂ���ׂ����Ǝv���܂��B
����|�|�������@�@�@���a�R�W�N�i�^�̖ړI�ȊO�͋��L���Ȃ��j
���a���q��w�����@�@���a�S�X�N�i���l�Ԍ��́j
�x�R��w�����@�@�@�@���a�T�Q�N
���a���q��w�ƕx�R��w�������Ɩ�������悤�ɂ��݂���̂ł������a���q��w�͎��l�Ԍ��͂ł̏����ł������疵�����܂���B�l�̐��������̎��R�Ƒ�w���̐��k��I�Ԏ��R�̂悤�Ȃ��̂�V���ɏ悹�đ�w�����d�������̂��Ǝv���܂��B����Ɛ��������͑�w�̐^�̖ړI�ł͂Ȃ��Ƃ����̂����f�̗��ɂ͂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̌�̕x�R��w�����ł͊w���̍݊w�W��`���I�ɓ��ʌ��͊W�ŏ������Ă������̂��A�����E������킸�����Љ�_�Ƃ��ē����O���_�ŏ��������̂͐l���ی�ׂ̈Ɉ���i���f�������Ƃ����܂��B�����A�����O���_�ł̏����������Ǝ����Ŕ�ׂ�ƁA���@�ł̖ړI�͍��邱�Ƃł����獑���̕����ی�̗v�����������ƂɂȂ�܂��B�������獑����w�̒P�ʔF��ɂ��i�@�R�����y�Ԃ悤�ɂ���ׂ��ł��傤�B
�R�k���c����i�����O���_�ł̏����j
���Y�}�ѓc�����i�����O���_�{�葱���R���j
�ѓc���������͓����O���_�����ł̏����������R�k���c����ɔ�ׂāA�葱���R�������������O�i���Ă��܂����A���̋K�����Ǒ��ɔ����邩�̔��f���o����\�����c�������Ƃ����ɗǂ������Ǝv���܂��B�K��ɖ��Ȃ����̋K��ɑ����Ĕ��f���ꂽ�Ȃ���Ȃ��ł�����ˁB
�c���k���Y�̖T�_����n�܂��������Љ�_�ł����A�v���ɓ�l�����̔����_����A��Ђł̃��X�g�����A�ŗ��m���i�@���m����S�Ă������Љ����Ǝv���̂ł���B�����Ƀg���u���������Đl���N�Q�̉\��������Ȃ������Љ�������R�����Ȃ��Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�葱���ƌ_���[���ɂ��Ďi�@�����f����ׂ����Ǝv���܂��B�w���̑����������悤�ɑ�w�͂Q�R���A���}�͂Q�P�����瑸�d���鍪���ɉ������Ή������̂��ǂ��Ǝv���܂��B��������E���t�̐R�����Ȃ�ł��ł���Ƃ���ƁA�@�Ă��ʂ�Ȃ�������}�������玟�ւƖ@�Ă��������ނƂ����������O�����̂ŁA�葱���R���{�������ł̏������ǂ��Ǝv���܂��B
�ٗʍs��
�}���[������
�L���T���[������
�����Ă��邱�Ƃ͐������̂ł����A�u�`�ł�������悤�ɍݗ����l���Ȃ��ōٗʂɊۓ�������͓̂������Ƃ����v���܂���ˁB�m���Ɍ����o���s���Ɋ����邱�ƂɂȂ�܂����A�����ɐl���N�Q������Ȃ�R������ׂ������Ǝv���܂��B
�����i���@���a�S�Q�N
�x�ؑi�ׁ@���a�T�V�N
�ǂ�������Y���Ɛ��������Η����鎖���ōٗʌ��{�������ł̏����ł����B�A�x�ؑi�ׂɊւ��Ă͕����֎~�ɂ��ĂȂ̂ŏ����Ȑ������̃��C���ł͂Ȃ��ł����A���̏�ł̕����֎~�̔��f�͎Љ�ۏ��Ƃ̌��ˍ����ł��x���o���܂��B�����i���Ɋւ��ĕ�[���̌�����Љ�ۏ��̐��i����s���ɍٗʌ���F�߂�̂͒v�����Ȃ��Ǝv���܂����A�������̌����Ŏi�@�̉���o����\�����c�����̂����Ƃ��Ă͎x�����܂��B����������̐����Ɓu�x�͎d���Ȃ����ǒ����͉��Ƃ��������v�Ƃ��������悭���ɂ��܂��B���Ԃ�A�Z�̎d����͐����ی삾���ł͐����ł��Ȃ��Ƃ������R���瑗�����������ی�̊���Ⴗ���遨�������Ƃ������t�œ������A�Ƃ����v�l���炾�Ǝv���܂��B���̋C������������̂ł����A���̊�ɂ��čl����Ɣ��ɓ���̂ł���`�B
�܂����@�͍�����̂����玄�l�ɒ��ډ������邱�Ƃ͖w�ǂȂ��B�ł����{��`�̒��Ŏ�ҕی�̗v�������܂��ĎЉ�����܂ꂽ�B�����Ɍo�ϏȂǂ��l�������v���O�����K����̍l����������B
���{�̍������l���Ďx���z�����߂�͍̂s���̎d���B�O����������i�@���Ɏ�`�B��Ɋւ��Ă͎���ɂ���ĕς��̂Ō��߂Â炢�B�������l����Ɩ������ʼn����������f���d���Ȃ��Ɗ����܂��B
�����A�ٔ������ɂ������Ɖ�������̃��C���͂���̂ł��傤���A�������Ŏi�@�R���̉\�����c�����̂ɁA�����������Ƃ��Ĉጛ�������o�Ȃ��Ƃ��낪���Ȃ̂ł��傤�ˁB�l���N�Q�̉\�����l������̊�������i�@�ɋ��߂��Ă���Ǝv���܂��B
���݂ɐ������ɂ��Ă̍��̒ʐ��͒��ۓI�������ł��B�v���Ɍ��@�̐��i���l������v���O�����K����Ȃ̂ł��傤������ł͎Љ�Ƃ��Ă̈Ӗ����Ȃ��Ȃ�܂����N���~���܂���B
�S�_�ьx�E�@����
�S���������X�֎������s���g�������S�_�ьx�E�@�����@�{�@���ƌ������@�P�O�W���̂Q
|
|
�� |
���� |
���q���E�Y�����E�C��ۈ����E���h |
|
�c���� |
�Z |
�Z |
�~ |
|
�c�̌��� |
�Z |
�~ |
�~ |
|
�c�̍s���� |
�~ |
�~ |
�~ |
���q������h�Ȃǂ��X�g�������獬�����N�����đ�ς�����_���B���̑���l���@�B�m���ɐ�������ł����ǁA�Ȃ牽�̂ɔƂ́Z�������̂ł��傤���H�H
�����̏L�������܂��B
�_�ːŊ֎���
�v���̂ł����A�����Љ�_�ł͓����O���_���g����̂ɁA�ٗʍs���ł͒�E�E����E�����ƖƐE�ł͈Ⴂ��t���Ȃ��͈̂�a���������܂��B�����������̐��������̎��R�͔��ɓ���ł��ˁB�����������琭������������ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ������܂����A�������������Ȃ��Ɠ�������̌��������v�͂���܂���ˁ`�B���̌��ˍ���������ƐE�̏ꍇ�͎i�@���ׂ������f�o���Ă��ǂ��̂ł͂Ǝv���܂��B
�ɕ������i�ׁi����i���f�j
�������Y�������i���f�ߒ��R���j
�]�ڌ��t���ꎖ���i�@�̖ړI�ᔽ�j
�s���@�̎i�@�R��
㊀�s���̍s�����s�ׂ��ٗʏ����ł��邩�ǂ�����F��
�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
㋥�ٗʏ����ƔF��@or
㋥�ٗʏ�������Ȃ��ƔF��
�@�@�@�@�@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
㊂�ٗʓ����^�R���@�@�@�@�@�@㊂���Ԕ��f��u�^�R��
�@�@�@�@�@��
�@�@�@�s�i�R�O��
�Љ�ϔO�R�����u�Љ�ϔO��A�������Ó����������v����ጴ���@���������@�s�����ȓ��@�E�@�̖ړI�ᔽ
���f�ߒ��R�����l���s���@�����l���@�ߑ�]���@�ߏ��]��
�葱�R��
�����̐R�����@���g���čs�����ٗʍs���ɑ҂��������������������B�������ł����ٗʍs���ɐH������Ō����Ă܂��B
�G�z�o�̏ؐl�������Ƌ��ێ���
�O�q���܂������A�Љ�ϔO�R���Ɣ��f�ߒ��R���̍��킹�Z���ٗʍs���ɑ҂����������������B
���Y��
���Y��ŋ��Ɋւ��Ă͈���ጛ�����I�s���̎v�����܂܂ł��B
���ߒr��᎖���ł͍��Y���̖��Ӗ����������܂������A���̂܂܂ł͗ݐi�ېł��i��ł����܂��B���Ԃ�ŕ��S���T�O�������獑���������o���܂���B���������͍����̃R���Z���T�X���K�v�ł��傤�B
�g�̂̎��R
�Y���i�ז@�̃e�[�}�͐^������VS�l���ی�ł��B�Ȃ̂Ɍ����Ƃ��ČY���i�ז@�ł͏ё����i����̂��͕s���j����@���W�؋����Ȃ�ł�����ł��B�N�i�X��`�͎d���Ȃ��Ƃ��Ă����@���̏��i�����X�X���ȏ�Ȃ�ĕ��ʂɍl������肦�܂���B��^�Ғi�K�ł̐ڌ���ʌ����F�߂�ꂽ�̂͑O�i���܂������A����ł��{��������x�@���ɓK�@�����肳��Ă���͉̂��Ƃ��Ȃ�Ȃ����̂��Ǝv���܂��B
���_�̂܂Ƃ�
�����܂Ō��Ă���Ƃǂ̔������f���炵�����Ƃ������Ă��邵�F�X�ȍ�ɔ����Ă���ٔ����̋�Y���ǂ�������܂���ˁB�ł������Ă��ĕ�����悤�ɑS�̓I�ɓ������ł��B���ۏ��Ɋւ��Ă����j�I�ɂ݂�Έጛ���f���o���Ȃ��������Ƃ������������Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ł͍ٔ����̐������f�͐����������̂ł��傤�B�����A������Ȃ��@���̘b�Ɍ��͂����̂Ɍ��@�Ƃ��Ă̖����A�܂荑���̒�R�����l������A����E���t�E���ւ̔��f�������͖̂�肾�Ǝv���܂��B���オ�ς���đΉ��o���Ȃ��Ȃ����画��ύX����Ηǂ��̂ł����画�f������ׂ��ł��傤�B�����������ŕt���I�R���̖�肪�o�Ă���킯�ł��B�N�����i�ׂ����Ȃ��ƕς��Ȃ��B�܂��Ă≽�N�|���邩���킩��Ȃ����@�ٔ���킨���Ȃ�ēz�͂��܂���B
�����čł��d�v���Ǝv����̂��ٗʍs���ł��B���̐}�����Ē�����킩��悤�ɁA�������I���ō���c����I�сA�c�@���t���ł�����^�}�ł��鎩���}�̑��ق������ߑg�t����܂��B���t�ɂ͖@�Ē�o��������A��o���ꂽ�@�Ă͑����̈Ăł������{�I�ɂ͕K���ʂ�܂����A���t�s�M�C�Ă��ی������ł��傤�B�����Ĉ����␛�┵���@�Ă�����킯����܂���A��������Ă���̂͊����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����Ċ����͊�{�N�r�ɂȂ�܂����b���ς���Ă������l�������ɂ��Ė@�������킯�ł��B���R�����B�ɕs���Ȗ@���͍��܂���B���������w�i�܂��ď�̔���߂��Ƃ��Ɋ�������t�ւ̋K���̕K�v��������Ƃ������ƂɋC���t���̂ł��傤�B�����Ă��̊����哱���p�^�[�i���Y���^�̎��Ԃ����ݍ���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B�P�O�O�O���~����Љ�ۏ��̂��͂܂��ɂ��̌���ł��傤�B���ł͂����̖��_����������ׂ�����l���Ă����܂��B
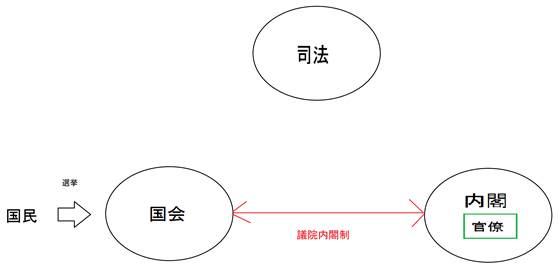
�B
��
��͓���ł������͊w�҂ł͂Ȃ��̂ʼn������������čD���Ȃ��ƌ������Ⴂ�܂��悗��
���_�͓��t�Ɗ������傫�ȗ͂������߂��邱�Ƃɂ���܂��B���̖����܂��͐l�Ɛl�ȊO�i�V�X�e���j�̖��ɕ����Č������܂��傤�B
�V�X�e���̑�
���_�͋c�@���t���Ȃ̂ł����A��r�Ƃ��Ă͑哝�̐���������܂��B�哝�̐����ƃ��[�_�[�ڑI�ׂ邯�ǐ��i�܂Ȃ��Ȃ�B�c�@���t���̓��[�_�[�ڑI�ׂȂ����ǐ��i�݂₷���B�ł����{�ł͓�@�����̗p���Ă��邽�߂ɋc�@���t���ł����߂��Ȃ������ɂȂ��Ă��܂��B�ȑO�̎Q�c�@�͗ǎ��̕{�Ƃ���ďO�c�@�̖\����h���ł����炵���ł��B
�ǂ����ɂ��댻�݂̎Q�c�@�͏O�c�@�̗D�z����d�v�����ꂸ�A����ɕ[���̂��߂̃^�����g�c���ƌĂ��c�������ꂽ���Ƃł��̈Ӗ��������Ă���ƌ�����ł��傤�B�c�@���t���̖��_�͕[���W�܂�Γ��t�����ȗ͂������Ă��܂��Ƃ���ɂ���܂�����A�����h�~�o����ΎQ�c�@�ł��ǂ��̂ł����O�c�@�̗D�z������ȏ㖳���ł��傤�B
�����łȂ�̗}�~�ɂ��Ȃ�Ȃ������ɖ��ʂȐŋ����|����Q�c�@�͎~�߂Ă��܂��āA��������̓��t�s�M�C�Ăŗ}�~���͂���܂��傤�B�i�ǂ������d�g�݂œ��t�s�M�C�Ă�����邩�͕�����܂������j�n�������̎ɂ̓��R�[��������킯�ł�����s�v�c�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
����ɍ����̒�R�������������߂Ɏi�@�����t�ւ̐R�����o����悤�ɂ��܂��傤�B�t���I�R�������ɂ߂ċq�ϑi�ׂ▯�O�i�ׂ̕����L���ē��t�̍s���s�ׂɂ܂ői�ׂ��\�ɂ��܂��傤�I���t�̍s���̖��ɐ푈���N���đ��Q����͍̂����ł����炱����s�v�c�Șb���Ƃ͎v���܂���B
����ւ̐R�����\�ɂ��܂��傤�B�i�W�P���Q�Ɓj����ɍ������獑��c���ւ̃��R�[���\�����~�����ł��ˁB
����ɂ���ɍ������]�ꍇ�̂ݒ��ۓI�R�����\�ɂ��܂��傤�B���̏ꍇ�͖@�߈ጛ����悤�ɂ��܂��傤�B
�����ď��v�����g���đ����̓��t�E����ɊW���锻���������ɓǂ܂��Ė��S�ł͂����Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�����Ă��̔�����ǂ���������i�@�ւ̃��R�[���̐\�����\�ɂ��܂��傤�B�Ƃ����̂��A�����̔����ǂ�ł��ċ^�₾�������������X����܂����B�u�N���u�}�}�̖��c�Ƃ͕s�ςɂȂ�Ȃ������v�͕ςȍl�����ł������A�킢�����̊�Ȃ�����̈Ⴂ�������܂��B�\�ł����ō��ق̂P�T�l�͖��_�E�ł��Ȃ蕅���Ă�Ȃ�Ęb�������܂���ˁI�H���͂����܂łƂ͎v���Ă��܂��A���Ɏi�@�ɗ͂����������Ƃ��Ă����̂P�T�l�̂��������B���K����������ɂ��������f���o����Ƃ͎v���Ȃ��̂ł��I���܂ł������Ă��Ă������������Ől�̖�肪�o�Ă���킯�ł��B
�l�̖��
�Љ�ۏ�@�̃��|�[�g�ɂ͏����܂��������{���������K���a�Ȃ̂ł��B�������A������A���t���A�������A�i�@���݂�Ȑ����K���a�ł��B�ł��̂ł������V�X�e���ƕ��s���ĉ��P���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
���t�E�����͎Љ�ۏ�@�ŏ������ʂ�Ɍ��������x���v�B�����͋���Œ�ӂ̒�グ�B����̓��R�[���\���⌸��̐\�����\�ɂ��Ă��������ْ����������Ă��炢�܂��傤�B�i�@�͌��������x���v�Ɠ��l�ɐ��ٔ����̈琬���~�߂܂��傤�B�A�����J�^�ɂ��Ă܂��͊F�ٌ�m����n�߂Čo����ςޒ��ōٔ����ɂȂ��Ă����悤�ɂ�������Ɛ����������܂�����������Ƃ��ꂽ����������ł��傤�B���̂�����������̃��R�[���\��������Ǝv���Ζ��_�E�Ȃ�Č����Ă����Ȃ��Ȃ�܂��悗�@��قǂ���u���R�[���\���v�Ƃ��Ă���̂͂����܂Ő\���ł����Ď��߂�������킯�ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ��Ē��������ł��B������������Ȃ��z���吨���܂�����ˁB�ꌾ����������邭�炢�̊����ł��B
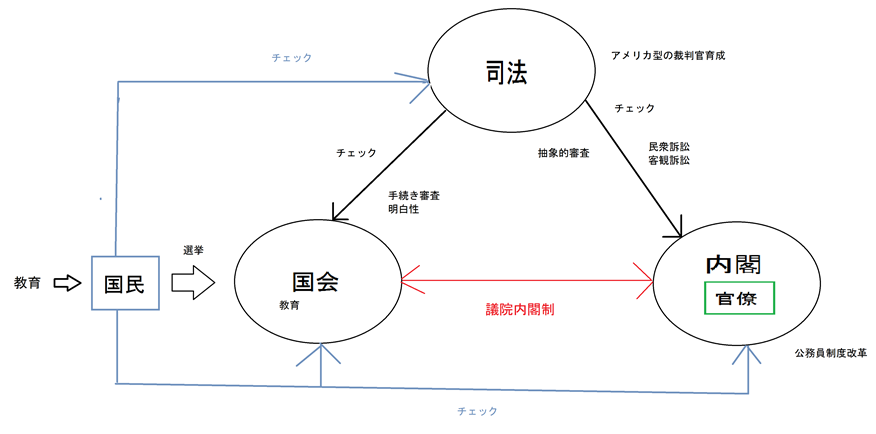
������ƈ��ӂ������߂����悤�ȋC�����܂����A�����ǂl�ɂ́u�@�w���Ȃ̂ɔn�����ȁv�Ǝv����ł��傤�B�����������Ƃ��Ă͔����{�C�ł���
����������ƃ}�N���Ȏ��_�Ō����Ƃ��Ɏ��ɂ͂��̎O�����������݉�̊����̂悤�Ɍ�����̂ł��B���{�Љ���O�l�̊�������ɔC���Ă���킯�ł���ˁB�H�ו��E�C�x���g�E���݂����Ȋ����ł��B
�Ȃ̂ɍ����͋������Ȃ��ĎO�l�͂��݂��Ɋ����Ȃ���ł���ˁB���̔��z���p�^�[�i���Y���^�̎Љ�����Ȍ��茠�^�̐��̒��ɂ��č��������݉�ɋ��������悤�ɂ���A��������̂�邱�Ƃɂ��������킫�܂����A������������������o���Ă�������d��������ł��傤�B�����ăO���[�o���Y���Ƃ����傫�Ȗ�肪�����͂����������ɂ͋��͂��Ė����������Ă�������ǂ��̂ɂȁ`�Ǝv���̂ł��B
�Љ�ۏ�ł������܂������A�l�Ԃ������ł͂Ȃ��ȏ�A�����K���a�ɋC��t���Ȃ����肭�c�[�����g���Ă���Ă��������Ȃ��Ǝv���܂��B
�Q�l����
�͂��߂Ă̌��@�w�@�����r�j
�V�E����n���h�u�b�N���@�@�����a�V
���@�@�����M��
�s���@�ǖ{�@�Œr�`��
�s���@����S�I�T�U
�o�T
�����̓�
���]�͍_
�}�F�����Z�ш���
��������
�@�l���ƍٔ����̌����@
�w�Дԍ�14J112019�@�����@��������
�y���_�z
�l���ƍٔ����̌����͑傢�ɊW������B
�T�y���Ȍ��茠���p�^�[�i���Y���̑Η��z
���Ȍ��茠�Ƃ́A���̖��̒ʂ�A�����̎��������Ō��߂錠���ł���B����́A���Ƃ̓Ɨ��Ɠ����s���̌�����A��Õ��j�̌���Ȃǂ̑���ł��A�l�̎����������d����邱�Ƃ��Ӗ�����B���A���Ȍ��茠�Ɋւ��ẮA���@13���ł͖����ۏ�͂���ĂȂ��B�������Ȍ��茠�Ɋւ�锻��Ƃ��āA�u�G�z�o�̏ؐl�M�җA�����ێ����v����������B���̎������G�z�o�̏ؐl�M�҂ł��銳�҂����Ȍ��茠�����A�S���オ��p�̍ۂɈ���I�ɗA���������Ȃ����p�^�[�i���Y���ɂ��s�ׂ��߂����čō��ق܂ő���ꂽ�����ł���B���́u�G�z�o�̏ؐl�v�Ƃ����̂́A�L���X�g���n�̏@���c�̂ŁA���̋����́A�����ɋL����Ă��邱�Ƃ��ʂ�Ɏ��H���邱�Ƃł���B���̋��`�̑�\��Ƃ��āA�\�͂�i���Z�̔ے�A�A���̋֎~����������B�����̒��ɗA����������s�ׂƂ��Ĕᔻ����L�q�����邽�߁A�A�������Ȃ����Ƃ́A�G�z�o�̏ؐl�̐M�҂����˂Ȃ�Ȃ����܂�̂ЂƂł���B�����p�^�[�i���Y���Ƃ́A��ʓI�ɁA�u����̗��v�̂��߂ɂ́A�{�l�̈ӌ��ɂ������Ȃ��A������s���Ɋ���������������ׂ��ł���Ƃ���l�����v[2]�ƒ�`�����B���̃p�^�[�i���Y���̖��ƂȂ�̂́A����̔���̂悤�Ɉ�҂Ɗ��҂̗���ŋN�������Ȍ��茠�̐N�Q��������B�����āA���̔���̍ō��قł́A�a�@�����p�^�[�i���Y���������҂����Ȍ��茠�d���A�a�@���̕����Ƃ����B���|��v��ƁA�w���҂��A�����邱�Ƃ͎��Ȃ̏@����̐M�O�ɔ�����Ƃ��āA�A������Ís�ׂ����ۂ���Ƃ̖��m�Ȉӎv��L���Ă���ꍇ�A���̂悤�Ȉӎv��������錠���͐l�i���i���@13���j�̈���e�Ƃ��đ��d����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂƁA��t��́A��p�̍ۂɗA�����K�v�ȋً}��p�ɂȂ�\�������邱�Ƃ����炩���ߗ\�����Ă����ɂ�������炸�A���̑Ή��ɂ��āA���҂ɂ܂��������������A����I�Ɉ�t�̔��f�ŗA���������Ȃ����̂́A�ӎv��������錠����D�������̂ƌ��킴����A���̓_�ɂ����ē��l�̐l�i���̐N�Q�x�y9�z�Ƃ��čō��ق͔퍐���̑��Q����������F�߂��B���A���̔���ł́A���@��20���M���̎��R���M�̎��R�̐N�Q�ɂ��Ă�����ꂽ���A�{�����ł́A�@����̐M�O�Ɋ�Â��A�����ۂ�l�i���̈ꕔ�Ƃ��ĔF�߂��ɂ����Ȃ����̂ƂȂ�B�܂��A��قǁA���Ȍ��茠�͌��@13���̐V�����l���Ƃ��ĕۏႳ��Ă��Ȃ��Ə��������A�������A���̔���̂悤�ɍٔ����́A���Ȍ��茠��ۏ�Ƃ����`�ł͂Ȃ����A�l�i���̈���e�Ƃ��đ��d�͂��Ă���Ƃ����`�ƂȂ�B
�U�y�����s���ƍٔ����̗���z
�@�ٔ����@��3��1�����A�u�ٔ����́A���{�����@�ɓ��ʂ̒�߂̂���ꍇ�������Ĉ�̖@����̑��ׂ��ٔ����A���̑��@���ɂ����ē��ɒ�߂錠����L����B�v�ƒ�߂��Ă���悤�Ɍ����A�u�@����̑��ׁv�ɂ�����ꍇ�ٔ����̌������y�Ԃ��A�������A���������s���Ɋւ��Ă͎i�@�������݂�����E�̈�Ƃ��āA���Ƃ��u�@���̑i�ׁv�ɂ�����ꍇ�ł��A�i�@�������݂�����E�ɂ���čٔ��������f�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����݂ł���B�܂�A��O�ɖ@����̑��ׂɂ�����ꍇ�ł��A�R�����Ȃ��A�R���ł��Ȃ����Ƃł���A������A������̌��E�ł��錛�@��55���u���i���ׂ̍ٔ��v�ƌ��@��64���u�e�N�ٔ����v�Ƃ͈Ⴂ���ߏ�̌��E�ɓ�����B�����āA���������s���Ƃ́A��ʂɂ́A�u���ڍ��Ɠ����̊�{�Ɋւ��鍂�x�ɐ������̂��鍑�ƍs�ׁv�y12�z�ł���A�@����̑��ׂƂ��čٔ����ɂ��@���I�Ȕ��f���_���I�ɂ͉\�ł��邪�A�����̐�����A�i�@�R���̑Ώۂ��珜�O�����s�ׂł���B�����s���_��p���čٔ����̐R�����y�Ȃ��Ƃ�������Ƃ��āu���쎖���v����\���B���̔���̊T�v�͓��Ĉ��ۏ��̍������ɂ��đ���ꂽ�����ł���B���|����ꕔ��������ƁA�w�E�ጛ�Ȃ��ۂ�̖@�I���f�́A���i�@�I�@�\���g���Ƃ���i�@�ٔ����̐R���ɂ́A�����Ƃ��ĂȂ��܂Ȃ������̂��́x�y8�z�Ɓu���x�̐������̂��鍑�ƍs�ׁv�y8�z�Ƃ��čٔ����̐R�����y�Ȃ��Ƃ��Ă���B�������A���̔��|�ɂ́A�����Ƃ��āw���������āA�ꌩ�ɂ߂Ė����Ɉጛ�����ł���ƔF�߂��Ȃ������́A�ٔ����̎i�@�R�����͈̔͊O�x�y8�z�Ƃ��Ă���B����́A���t�ƍ���ɂ����̒����̘b�ɕς�邪�A���̒������͓��t�ɂ��邪�A���ɓ��t��X���Ɠ��{�����ɂƂ��āA�l���N�Q�ƂȂ�s����������������Ƃ���B�������A���@��73��3����荑��̌����Ƃ��āA���̒����O�܂��͒�����̏����������Ȃ���A���̕s�������͖����ł���B�������A���̍���ł������s�������̏��F������A�����A���̕s�������͌��͂����邱�ƂɂȂ�B�����A�������쎖���̔��|�ɏ����Ă���悤�ɂ��̕s������ꌩ�ɂ߂Ė����Ɉጛ�����ł���ƔF�߂���Ȃ�A�ٔ����̌����̈ጛ�����Ō��@��98���ɂ��s�������̒�����h�����Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��B�܂�A���̔���̂悤�ɍٔ����������s���ɂ�������̂Ȃ�A�����A�i�@�R���ɋy�Ȃ����A�l���ی�̊ϓ_����A��O�Ȃ��A�����Ȃ������s���ł��R�����Ȃ��Ƃ́A����Ȃ��Ǝ������B�@�����āA�������쎖���ł́A�ꌩ�ɂ߂Ė����Ɉጛ�����ł���Ƃ́A����F�߂��Ȃ��Ƃ���Č������j���i���߁j�Ƃ��ꂽ�B
�V�y�����Љ�_�ƍٔ����̗���z
�@�����Љ�_�Ƃ͒n���c��A��w���Ȃǂ̌��@��̏d�v�ȋ@�ւ܂��͌��@�セ�̒c�̂̎��������F�߂��Ă��邱�Ƃł���A�c�̂̓����I�R���ɂ��ẮA�g�D�̎������E���含�d���A�����̎����I�����Ɉς˂čٔ����̔��f���T���Ă���B����͑O�q�L�ڂ��������s���ɂ��ĂƓ������A�����Љ�_�͍ٔ����@��3��1���̗�O�Ƃ��āA�i�@�R�����y�Ȃ����݂̈�ł���B�������A���������Љ�_�ł��A��I�Ɏi�@�R�����y�Ȃ���ł͂Ȃ��A��ʎs���@�����Ɗ֘A����ꍇ�͎i�@�R������O�Ƃ��ċy�ԂƂ��Ă���B�����Ă��̗�O�ɋy����Ƃ��āu�G�z�o�̏ؐl������u���ێ����v����������B���̎����́u�G�z�o�̏ؐl�M�҂ł���w�����A���Ȃ̏@���I�M���ɔ�����Ƃ������R�ŁA�K�C�Ȗڂł��錕���̗��C�����ۂ������ߗ��N�����ƂȂ��������ɁA���̔N�x�����N�����ƂȂ������߁A�w���ɂ����������̑ފw�����ɂ��������ɑ��āA��@�ł���Ǝ���������߂��s���i�ׁi�R���i�ׁj�v�y14�z�ł���B�w�Z����ɂ������M���̎��R�̕ۏႪ����ꂽ�����ł�����B�w�Z���́u�����i�G�z�o�̏ؐl�M�҂ł���w���j���咣�����֑[�u���w�Z���F�߂���A����̏@���̐M�������x���������ƂɂȂ�A���@��20��3���̐��������ɔ����邱�ƂɂȂ�v�y9�z�Ǝ咣�������A�����ł́A���̎咣��ے肵�A���|�ɂ��A�w�M�̎��R��@���I�s�ׂɑ��鐧�����ɖړI�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��������A�w���̐M�̎��R�ɑ��Ĕz�����Ȃ����ʂƂȂ�A�������u�����̌�����ފw�����̑I�����Љ�ϔO�㒘�����Ó��������A�ٗʌ��͈̔͂�����@�Ȃ��̂Ƃ��킴��Ȃ��x�y9�z�Ƃ��āA����Ɂw��֑[�u���u���邱�Ƃ͓���̏@���ɑ��鉇��������킯�ł͂Ȃ��x�y9�z�Ƃ��āA20��3���̐��������ᔽ�ɂ�����Ȃ��Ƃ����B����āA�����ł́A�w�Z���̏��������������肵���B���̂悤�������Љ�_�ɂ����čٔ����̗���́A�ފw�͈�ʎs���@�����Ɗ֘A����Ƃ��Ďi�@�R���̑Ώۂł��邪�A�������A���̔���悤�ɑފw�⌴�����u����������邽�߂̕��@�����������ǂ������d�����Ă���悤�ɏ������̂������������܂ł̉ߒ��A�葱���A�̕����ɖ�肪�Ȃ������œ_�ɁA�R�����Ă���ƍl������B
�@
�@�W�y���Ƌ@�ւ̎��R�ٗʍs���ƍٔ����̗���z
�@���@��25���ɐ��������߂Ă���B���̐������̖@�I�����ɂ͂R��������Ă��āA���̈���v���O�����K���������B���̐��́A���@��25���͌X�̍����ɑ��Ė@�I������ے肷��̂ŁA��25���Ɋ�Â������ڂ̋��t������ے肵�A���@�s��ׂ̈ጛ�m�F�i�ׂ��ے肵�A����ɍ��Ɣ��������ł��Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B�������A�v���O�����K������̗p���Ă��ق��̂Q���Ɠ����悤�ɋ�̓I���@�Ɋ�Â��������͔F�߂��Ă���B�����āA�����v���O�����K������̗p��������ŁA�����i������������B���̔���́A�������́A�����ی�@�ɂ���Õ}���E�����}�����Ă������Z���d��������Ă����悤�ɂȂ����ׁA��������������́A�����}���ƈ�Ô�̖Ə���ł���ꂽ�B�����Œ�������25���́u�Œ���x�̐��������v���ێ�����ɂ͑���Ȃ��Ƃ��āA�ٌ��̍�����������ꂽ�B���|�ɂ��ƁA�w���@25��1���́A���ɍ����̐������m�ۂ��ׂ������I�E���`�I�`�������ɉۂ����ɂƂǂ܂�A��̓I��������ۏႵ�����̂ł͂Ȃ��x�y10�z�A���v���O�����K������̗p�������Ƃ��������B����ɁA�w�����Œ���x�̐������́A������b�̍��ړI�I�ȍٗʂɈς˂���Ɓx�y10�z���_�Â����B�܂��A�{���ɂ����Đ����}����ł��������Ƃ͎��R�ٗʍs���͈͓̔��Ƃ������A���̂悤�ɍ��Ƌ@�ւ̎��R�ٗʍs���ɔC����Ă���Ƃ���Ă�����̂́A�����s���A�����Љ�_�ƕ��сA�ٔ����@��3��1���̗�O�Ƃ��āA�i�@�R�����y�Ȃ����݂Ƃ��Ă���B�������A���̎��R�ٗʍs������O�Ȃ��A�R���y�Ȃ���ł͂Ȃ��A�����i���Ɠ������A���@25���̐������Ɋ�Â����@�A�y�сu�Œ���x�̐��������v�ɂ��đ���ꂽ����u�x�ؑi�ׁv�̔��|�ł́A�u���@�{�̎��R�ٗʍs�������������������������炩�ɍٗʌ��̈�E�E���p���F�߂����ꍇ�Ɏi�@�R�����y�ԁv�ƍ��Ƌ@�ւ̎��R�ٗʍs���ł���肪����A�ٔ����̎i�@�R���̗]�n�����邱�Ƃ��������B
�X�y�l���ɂƂ��čٔ����Ƃ͏��n�̌��z
�����܂Ř_���Ă����悤�ɁA�i�@���̌��E�Ƃ��Ă����������s���A�����Љ��Ȃǂł��A�����Ɉ�E�E���p���̖�肪����A���@��81�����A�ٔ����̌����ŏ����邱�Ƃ͂ł���B�܂��A���Ƌ@�ւ݂̂Ȃ炸�A���l�Ԃ̐l���N�Q�ɂ����Ă��A���@�̊ԐړK�p��ꍇ�ɂ���ẮA���@�̒��ړK�p���A�l�X�Ȑl���N�Q����̕ی�̗v����}���Ă���B�܂��ɍٔ����Ƃ͌��@�̑��݈Ӌ`�ł���u�l���ی�v�̍Ō�̍ԂƂ������ƂɂȂ�B�������A����́A����Ԃ��A�l���N�Q���Ō�ɐN���̂́A�ٔ����ł��邱�Ƃ��ɈӖ�����B�ǂ������Ƃ���̓I�ɏq�ׂ�ƁA�y�����s���ƍٔ����̗���z�̍��ڂŏq�ׂ��u���̒����v���A���ɓ��t�ƍ��X���Ɠ��{�����ɂƂ��āA�ꌩ�ɂ߂Ė����Ȑl���N�Q�ƂȂ�s��������������Ă��A���쎖���̔��|�ɖ��L���Ă����悤�������s���ɑ�����ꍇ�ł��A���̏ꍇ�Ȃ�A�ٔ����̌����Ƃ��āA�ጛ�R�����s�g�ł��邱�ƂɂȂ�B�������A���̍ٔ����ł������A�ጛ�R�����s�g���Ȃ�����A���͂�A�l���N�Q���~�߂邱�Ƃ�������s�\�ƂȂ�B���̂悤�ɐl���ی�̐���ɂ��čٔ������ŏI���茠�����ȏ�A�l���Ƃ��čٔ����Ƃ́A����ł́A���@�̈З͂��ő���ɔ����ł��闧��ł���Ȃ�����A��������ł́A���@�̍�����ő���ɔj��낤�����݁A�܂��ɏ��n�̌��ƌ�����B
�o�T�j�y1�zhttp://www.geocities.co.jp/WallStreet/7956/han/han55.html
�@�@�@[2]�L����
�@�@�y3�zhttp://www.ne.jp/asahi/box/kuro/report/yhwh.htm
�@�@�@�y5�zhttp://www.mc-law.jp/kigyohomu/10875/
�y6�zhttp://consti.web.fc2.com/12shou1.html
�y7�z�|�P�b�g�Z�@
�Q�l�����j
�y8�z�����M��u���@�i��5�Łj�v�i��g���X�j
�y9�z���J�����j�u���@����S�I�T�i��U�Łj�v�i�L��t�j
�y10�z���J�����j�u���@����S�I�U�i��U�Łj�v�i�L��t�j
�y12�z�u�d�v�������@�����U�`�Q�O�N�x�v�i�L��t�j
�y13�z���@�̃m�[�g
�y15�zhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0
�y17�zhttp://ethics.bun.kyoto-u.ac.jp/jk/jk17/okuno.html
���c�p��
�l���ƍٔ����̌���
�鋞��w�@�w��3�N�@14J107011�@���c�@�p��
�L�[���[�h�F�����s�ׁ@���쎖���@�����Љ�_�@�ٗʍs�ׁ@�G�z�o�̏ؐl�@�M���̎��R
�@�@�@�@�@�@�����i�ׁ@�v���O�����K����@���Ȍ��茠�@�p�^�[�i���Y��
�@�@�@�@�@�@�i�S4299�����j
�͂��߂�
�@���͌l�E�����̈ӎu����苭�����Ă������̂ł͂Ȃ����ƍl�����B�l�ɂ͂��ꂼ�ꐶ�܂�Ȃ���Ɍ������^�����Ă���B�Ȃ�炩�̖�肪�N����ۂɂ͂��̐l�����m���Ԃ��荇���Ă����ԂɂȂ�B�����āA���̐l���͎��ɍ��ƂԂ��荇�����Ƃ�����B�����Ȃ����Ƃ��A�N���ǂ̂悤�ɔ��f����̂��낤���B�������ȉ��Ɏ����B
�ٗʂƔ͈́i���Q�l�j
�@�l���ƍ����@����̑i�ׂɎ���������͐��������݂���B�L���ȂƂ���Ō����������i������������B���̑i�ׂł͐����ی�̎z�Ɋւ�����������ƂȂ��Ă���B��������͐����ۏ���Đ������Ă������A�Z���������ߌZ����̎d����𖽂��������ŕ⏞�������z�����B�Ȃ��A��������͍ō��ق̔������o��O�ɂȂ��Ȃ��Ă��܂������߂ɁA�͂�����Ƃ������_�͏o�Ă��Ȃ��ƍl������B���@��25���ɂ�����u�������v�ł́A�Œ���x�̐����𑗂錠��������Ƃ��Ă��邽�߁A�����ۏ�ɂ��T���ȕ�炵�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl������B�����āA�����ۏ�͐ŋ�����܂��Ȃ��Ă��邽�߁A���z��g�����͍s���̍ٗʂɂ��Ƃ��Ă���B�ٗʂƂ͗��@�{�̔��f�]�n�ł���A�s���s�ׂ̂����̖@���ɋK�肳��Ă��Ȃ����͍̂s�������ٗʍs�����F�߂��Ă���Ƃ��Ă���B�����āA���̍ٗʂ̌��ʁA��������͕������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B
�@�܂��A�߂�����ɖx�ؑi�ׂ�����B���̎����ł͕����̌����ɂ�萶���ł��Ȃ��Ȃ��Ă����x�������ۏ�̑��z��]�ݑi�ׂ��N�������B���̎����ł��s���̍ٗʂƂ��đ��z�͔F�߂��Ȃ������B�������A���̎������痧�@�{���ٗʍs���Ɋւ��郋�[�����ł����B���̃��[���ɂ�薾�����̂���ӂ������f�ɂ͍ٗʂ��y�Ȃ��Ƃ����B���@�ٗʌ��̒�������E������A�i�@�R���̉\����F�߂�Ƃ����ٔ��K�͐���F�߂Ă���Ƃ����_�ŁA���S���v���O�����K����ł͂Ȃ��Ɖ������B
�@�v���O�����K����Ƃ́A���@��Q�T���̐������ɂ��āA���ɉۂ��������I�E�����I�`���Ƃ��ĉ��߂��A�X�̍����ɋ�̓I������ۏႵ�����̂ł͂Ȃ��Ƃ������ł���B�u���@��Q�T���Ɉᔽ���邩�琶���ۏ�̎z���グ�Ă���v�Ƃ����i�����N�������Ƃ͂ł��Ȃ��B��L��̔��������ƍٔ����̔��f�͂��̐����Ƃ��Ă���悤�Ɏv����B���̐��ɔ���������@�I�������ł���B���������Ƃɑ��ĕK�v�ȋ`�����u����悤�v�����錠�����ۏႳ��A���Ƃ�����ɉ�����`��������Ƃ��Ă���B�����܂Ŗ��m���������E�����ٗʂ̏ꍇ�݂̂ł͂��邪�A�����̈ӌ������f�����\����F�߂Ă��鎞�_�ŁA�v���O�����K����ɖ@�I�����������荞��ł���̂ł͂Ȃ����ƍl������B
�i�@�̌��E
�@���m���̘b���ƁA���쎖�������グ����B����Ƃ����y�n�ɂ���A�����J��n�ɂ��Ď��ӏZ���Ȃǂ��i�ׂ��N���������ł���B����́A���{�ƃA�����J�Ƃ̊Ԃ̖��ł���A���̕��j�̖��ł���B���̂悤�ȋɂ߂č��x�ɐ����I�Ȗ��Ɋւ��čٔ����͌����o���Ȃ��Ƃ����Ă���B����������s���Ƃ�сA�i�@�R�����̌��E�̂ЂƂƌ����Ă���B���̎i�@���̌��E�ɂ����m���̌����͂��Ă͂܂�Ƃ���Ă���B���܂�ɂ������\�����Ă���Ǝv����ꍇ�ɂ͂��Ƃ������s�����Ƃ��Ă��i�@�R�������g����Ƃ̂��Ƃł���B���݂̓��{�͓ƍِ���������邽�߂ɎO�������̌`���Ƃ��Ă���A���̒��ł�����͍����̍ō��@�ւƂ���Ă���B�������킯�Ă�����Ŏi�@�������ׂĂɌ��o�����ł���悤�ɂ���͕̂�������Ӗ�������ӂ�ɂȂ��Ă��܂����ߔ[���͍s���B�������A�������ɂ����Ďi�@�̌��������������܂�ɂ����������̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ��͏��Ȃ��炸����悤�Ɏv����B�ٔ����̌����̎コ�ɂ͑����^�O���c��Ƃ���ł���B
�@�ٔ����̗͂̎コ�͌x�@�@�����ł��݂ĂƂ��B���̎��Ăōٔ����̖������Ɋւ���^�O�����Z���킩��悤�ɂȂ����B���̎����ō������������Ƃ��Ă��x�@�@�����߂�ɂ����莩�������F�߂��邽�߂ɍٔ����͎���o���Ȃ��Ƃ����B�������ɍ���͍ō��@�ւł���O�������̊ϓ_���炷��Ƃ���������Ȃ����A�����̑吨��������悤�Ȗ@�������Ƃ��Ă��ٔ������o�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����̂ł���A��E�����s�ׂɂ͍ٔ����������o����Ƃ������[���͂����������݈Ӌ`������̂��Ƃ���v���Ă��܂��B�܂��A�x�@�\�����ጛ�i�ׂł͌��@��9�������ƂȂ������A�t���I�ጛ�R�����ɂ���肪�N���Ă��Ȃ�����͔��f���������Ƃ͍ٔ����ɂ͂ł��Ȃ��Ƃ����B�O���[�]�[���܂ł͍l�����Ɉ�E�̒��ł��^�����Ȃ��̂����͍ٔ����ł����f�ł���Ƃ����B�������A����ł͍����̂قڑS��������ɂ͌����o���Ȃ��Ƃ����Ă���悤�Ȃ��̂ł���ƍl������B
�@�܂��A�ٔ����������o���Ȃ����̗̂�Ƃ��������Љ�_����������B�����Љ�Ƃ́A�c�̓��̋K���E�K���Ɋւ�����ɂ��āA�i�@���ɂ��ጛ�R�������y�Ȃ����Ƃł���B���Ƃ��A�w�Z�̋K���Ɉጛ�R�����͋y�Ȃ��B���̂��Ƃ���悭��������̂͏��a���q�厖���E�x�R��w�i�ׂȂǂł���B�ꌩ���ĉ��\�Ƃ��v����w�Z���̏��u�ɑ��đi�ׂ��N�������Ƃ��Ă��A�w�Z���̍ٗʂ����܂�ɂ���E���Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ͂��̊w�Z�̋K���ɂ��ׂĔC����Ƃ��Ă���B���̂��߁A��L��̗�͂ǂ�����w�Z�������i���Ă���B
�������w�Z���̍ٗʂ��F�߂��Ȃ��������������B�L�����_�ˍ��ꌕ�����Z���ێ����ł���B����́A�L���X�g�n�@���u���݂̂̓��v�̐M�҂ł����G�z�o�̏ؐl�̐��k���A�w�Z�����P�ʂ�F�߂Ȃ��������Ƃɑ��đi�ׂ��N���������̂ł���B�G�z�o�̏ؐl�͖\�͂������Ă���A���Y�w�Z�͌������Z��K�C�Ƃ��Ă����B�������w�Z���̃��[���̂��Ƃł��邽�������Љ�_�͔F�߂���B�������A���̑i�ׂł͊w�Z�����s�i���Ă���B����́A���@��20�����M���̎��R�����邽�߂ł���B�M���̎��R�͎��g�̎v�z�̎��R�ɓ����邽�߁A���@�̒��ł��ی삪��������ނ̂��̂ł���ƍl������B���̌��ōٔ����́A�w�Z���͑�֏��u��p�ӂ��邱�Ƃ��ł������낤�Ƃ��Ċw�Z���̐\�����Ă��p�����Ă���B�܂��A��֏��u�̗p�ӂ͐������������ɂ͈ᔽ���Ȃ��ƌ������Ă���̂������ł���B
�@�G�z�o�̏ؐl�ł�����L���Ȏ����͗A���������Ǝv����B�A���֘A�ł��G�z�o�̏ؐl�͐����肢������肪�N���Ă���B���̒��ł���t���ҊW�̖�肪�������̂͊��҂��A��p���s���ۂɊ��҂͗A�����ۂ���҂͂���������������A��p���ɂ�ނ��A�����s�����B�G�z�o�̏ؐl�ɂƂ��ĊO���猌��A������邱�Ƃ́A����̐��E�̏��ł��Ӗ����Ă���Ƃ����B���{�l�Ō����Ƃ���́A�A���������ƓV���ɍs���Ȃ��Ȃ�Ƃ��������ł���B��t�͎�p�Ɋւ�������������ہA���҂���̗A���̏������Ă��Ȃ��B����́A�ً}���Ԃ̍ۂɊւ�������`����ӂ��������߂Ɋ��҂���̐����ȋ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃ��Ӗ����Ă���B���̂悤�ȊW����`�Ƃ����B���҂ɂ����Ȍ��茠������A�����̈ӎu�d���ׂ��ƍl������B��t�ɂ��p�^�[�i���Y��������A��t�̍ٗʂɊ�Â��A�������ꂩ��ア����ł��銳�҂̗��v�ƂȂ�悤�Ɋ��҂̈ӎv��s���ɉ������̂ł���B�G�z�o�̏ؐl�A�����ێ����ł͐M��������ł��邱�Ƃ����芳�ґ������i���Ă���B�������A��t�͈��C���������킯�ł͂Ȃ��A���g�̑P�ӂɏ]���A�����s���������ł��邱�Ƃ͂������ł���B
���Ƃƍ����̊W��
���Ȍ��茠���p�^�[�i���Y���̑Η��͂Ȃɂ���Ë@�ւ����̖��ł͂Ȃ��ƍl������B���ꂪ�A�l���ƍ��ƂƂ̊W�ł���B���W�ɂ͂��ꂼ�����Ȍ��茠������A���Ƃɂ͖��W���܂Ƃߏグ�邽�߂��p�^�[�i���Y�������݂��Ă���B���܂ł̔�����݂Ă���ƁA���݂̓��{�͂ǂ��ƂȂ����Ƃ̉���ɂ��e�����傫���悤�Ɏv����B�������@�{�������̔�𗁂т�悤�Ȗ@�����肠�����Ƃ��Ă��ٔ����������Ƃ��ł���\���͋ɂ߂ĒႢ�ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł��邽�߂ł���B�ٔ����̌����͍ٔ����@��3���ɋL����Ă���B�ɂ��ƁA�@����̑i�ׂ�����Ȃ��Ĕ��f�ł��邪�i�ׂ��Ȃ���Δ��f�͂ł��Ȃ��B��̓I�Ȗ��ɔ��W���Ă���Δ��f�ł��邪�����łȂ���Δ��f�ł��Ȃ��B���A��ɓ��Ă͂܂��Ă��Ă���X�ł͔��f�����˂�Ƃ��낪����܂��B�܂�A�ٔ����̗͂͐Ǝ�Ȃ��̂�������Ȃ��B���݂̍ٔ��������f���邽�߂ɂ́A�������@����̑i�ׂɔ��W���A���������s���E�����Љ��E�ٗʍs���E�������ɂ�����Ȃ����������Ă�������������A�t���I�R���ł���Ƃ�����������������Ƃ��̂��ʂ��o��Ƃ������Ƃł���B�����͓��t�̊����⍑��̂����Ȃ�ɂȂ邵���Ȃ��댯����s��ł���ƍl���Ă��ԈႦ�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B���������Ĉ�ÊW�̘b�ɖ߂�ƁA�����p�^�[�i���Y���������Ȍ��茠���d��ׂ����ƍl���Ă���B��t���ҊW�ōł��d�v�������C���t�H�[���h�R���Z���g���������Ă�����Ƃ͌l�̊�]�ɉ����ׂ����ƍl���Ă���B��������œ��Ă��Ƃ��A�S�Ă������̈ӎv����ɔC���Ă��܂��ƍ��͂����ɂ��߂ɂȂ�Ƃ������B���������`�����ʂ����A�������킩���������ł̏������ł��Ă���̂ł������͂����B�����ɂ���ɂ��Ƃ���̈ጛ���@�R�����\�ł�������̗͂͂���ɋ����Ȃ�̂ł͂Ȃ����낤���B���́A������n���ɂ���Ă��Ă��ւ��ȍ����������Ă��Č�����킩���Ă���ł��낤���̈̂��l�����ɂ�鍑���̗��v�̂��߂̍s�������f����ɂ����Ȃ�Ƃ������Ƃł���B���Ȍ���͂����܂Ŏ����̎v���s�����ł���Ƃ��������ŁA���ꂪ��ʓI�Ɍ��ĊԈႦ�Ă���悤�ȓ��e���Ƃ��Ă����Ȍ���Ȃ̂��Ƃ����܂���ʂ��Ă��܂��悤�ȏł͂������Ȃ��C������B�D�_�s�f�ɂȂ��Ă��܂����A�����܂Œm���̂��Ƃł��邦�炢�l�����ɂ͂��Ă��炢�A���̌���ɍ������ٔ�����ʂ��ĉ���ł���]�n���ł���悢�̂ł͂Ȃ����ƍl����B�����Љ��ٗʍs�ׂȂǁA���Ƃł͂Ȃ��Ƃ���̈ӌ����Ԃ��荇���ꍇ�ł��A���Ƃ����ޖ��ł��A�O�������E���̎���������Ȃ����x�ɍ����E�i�@�̗͂����߂Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl����B
�ȏ�
�Q�l����
�� �����b�N�X���l���}�i2014�j�u�����b�N�X�@�w���|���@�����\�킩��₷�����@���ᒩ���i�ׁi�������j�̊T�v�Ɣ����̎�|���킩��₷������v
2016�N8��1���A�N�Z�X
������l
�l���ƍٔ����̌���
14J119023 ���� ��l
�l���A�ٔ����̌��������_�ƂȂ�������������������܂����A�L�[���[�h�̒��ɂ������쎖���A�G�z�o�̏ؐl�A�����i���ɂ��Ă��ꂼ�ꏇ�Ɏ��̌��_�ƂȂ������l���������R���q�ׂĂ����܂��B
���쎖���Ƃ������s���_�̐����Ƃ��ꂽ�����ł����A���������s���_�ɂ��ẮA
�K�p�����邩���Ȃ����̊�͌��i�ɂ��A�K�v�Œ���̏ꍇ�ɂ����Ă̂ݍ̗p���ׂ��ł���Ƃ������_�Ɏ���܂����B
�u�����̊T�v�̐����ƋC�ɂȂ����_�v
���쎖���Ƃ́A�����̗���ݓ��ČR��n�̊g���ɔ�����f�����̈ꕔ����n���̗�������֎~���ɐN�������Ƃ������ƂŁA�u���Ĉ��S�ۏ����3���Ɋ�Â��s������ɔ����Y�����ʖ@�ᔽ�v�Ƃ��đi����ꂽ�����ł����A�����n�قł́A�ݓ��ČR�͌��@9���ᔽ�ł���i����ꂽ�f�������͖��߂Ƃ���܂����B�������ō��ق͂��̔�����j�����A�����n�قɍ����߂��ƂȂ�A���̌��ʍݓ��ČR�͌��@9���ᔽ�ł͂Ȃ��Ƃ���A�f�������͖��߂ł͂Ȃ��A�L�߂ƂȂ�܂����B���̍����ƂȂ����̂������s���_�Ƃ���Ă��܂����A�����s���_�ɂ��ƁA���Ĉ��S�ۏ���͍��x�Ȑ�������L������̂ł��邽�߁A�i�@�����̑ΏۂƂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B���������͂��́u���x�Ȑ�������L����Ύi�@�R����Ƃ��v�Ƃ����������C�ɂ�����܂����B���x�Ȑ������Ƃ������̂͂ǂ̂悤�Ȋ�Ŕ��f�����̂��A����������獑�Ƃ���肷���Ă��܂����Ƃ�����̂ł͂Ȃ����A�Ȃǎv���܂����B
�u�����s���_�̌������x�Ȑ������̊�A�����ɑ���^��A���_�Ɏ��������R�v
�����s���_�̗̍p��Ƃ���Ă���u���x�Ȑ�������L������́v�Ƃ͉������ׂĂ݂��Ƃ���A���ڂɍ��Ɠ����̊�{�ƂȂ鍑�Ƃ̍s�ׂ�����ɓ��Ă͂܂�悤�ł����B�������ɁA���Ĉ��S�ۏ���́A���{�̍��h�̂��߂ɕs���ł��邽�߁A���ꂪ�ጛ�Ƃ���Ă��܂��ƁA���{�̍��h���蔖�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�ጛ�Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����߁A�����s�ט_���̗p���āA���Ĉ��S�ۏ���̎i�@�R����Ƃ��Ƃ����������̔����͎d���Ȃ��������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A�l���Ă݂�Ƃ��̔����Ŗ{���������s���_���g���K�v���͂������̂��낤���Ǝ��͎v���܂��B���@9���Ƃ́A���{�ɂ���͂̕ێ��A���͍s�g��F�߂Ȃ��Ƃ������̂ł����A���S�ۏ���ɂ�����ݓ��ČR�Ƃ́A�����܂ŃA�����J���������Ă�����̂ł����āA����A���{�̈��S�ۏ�̂��߂ɂ��邾���ł���Ǝv���邽�߁A���@9���Ɉᔽ�͂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͎v���܂����ǂ���瓖���̍ō��ق������悤�Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ��āA����ɉ�����`�������s���_���o�����悤�ł��B������������o���K�v�͖��������Ǝv���܂��B�G�Ȉӌ����Ǝv���܂����A���q���������ł���̂Ȃ�A(�ݓ��ČR���ǂ����ǂ��Ȃ����͂��Ă���)���Ĉ��S�ۏ���̍ݓ��ČR�����h�̂��߂Ȃ̂����瓯���悤�ɍ����ł���Ƃ��邱�Ƃ������ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
���������s���_��ے�͂��܂��s���ȕ���������܂��B�����s�ט_���̗p����ƁA���炩�Ɉጛ�ł���Ǝv����悤�ȍ��ƍs�ׂł����Ɠ����̂��߂ɕK�v�Ƃ������R�Ō�������Ă��܂��\�������邩������Ȃ��Ƃ����_�ł��B������(���͍����ł���Ə����܂�����)���쎖���̓��Ĉ��S�ۏ���ȂǁA�ǂ����Ă��K�v�ȍ��ƍs�ׂł�ނ����Ȃ��ꍇ�������s���_�������ƕs�ւł���̂ŁA�ŏ��ɏq�ׂ��悤�������s���_�̗̍p�����邩���Ȃ����̊�͌��i�ɂ��A�K�v�Œ���̏ꍇ�ɂ����Ă̂ݍ̗p���ׂ��ł���Ǝ��͎v���܂����B
�G�z�o�̏ؐl�ɂ��Ă̗L���Ȕ���ł���_�ˍ��ꌕ�����Z���ێ����ƗA�����ێ������ꂼ��̎����ɑ��Ă̎��̌��_�Ƃ��̗��R�������Ă����܂��B
�_�ˍ��ꌕ�����Z���ێ����̍ō��ق̔��f�͑Ó��Ȃ��̂ł���Ǝ��͎v���Ă��܂��B�ȉ����R�ł��B
�u�����̊T�v�Ǝ��̍l���v
�_�ˍ��ꌕ�����Z���ێ����Ƃ́A�������Z���@����̗��R�ŋ��ۂ��Ă����G�z�o�̏ؐl�̐M�҂ł��鐶�k�𗯔N�����Ō�ɂ͑ފw�����Ƃ����w�Z�̍s�ׂ́A�ٗʍs���͈̔͂���E���Ĉጛ��@�ł���Ƃ��ꂽ�����ł����A���̔���ł������Љ�_���M���̎��R�����ƂȂ��Ă���ƍl�����܂��B�����Љ�_�Ƃ͒c�̓����̋K���A�܂�w�Z�̍Z���̋����Ȃǂ͎��R�ٗʂł��邽�߈ጛ�R���̑ΏۂƂȂ�Ȃ��Ƃ���闝�_�ł��B���̗��_�ǂ���ł����A�����̎��Ƃ��������邱�Ƃ����ɖ��͂Ȃ��Ƃ����悤�Ɍ����܂��B���ۊw�Z�������O�Ɍ����̎��Z�����邱�Ƃ����\���Ă����Əq�ׂĂ���̂ŁA���͂Ȃ��Ƃ��Ă��܂����B���������́A�����������Љ�_������Ƃ����Ă��A���̐l�̐l���ςɂ��������̂��肪�Ȃ��̂ɂ��ւ�炸�K��������A�e������悤�Ȃ����͍D�܂����Ȃ��ƍl���܂��B�M���̎��R�͌��@�ŕۏႳ��Ă��邽�߁A�����Љ�_������Ƃ����Ă��u��֏��u�v������Ȃǂ�����ł������͂������̂ɂ��ւ�炸�M���̎��R��e������悤�Ȃ��Ƃ������w�Z�͂�肷���ł���Ǝv���A�ٗʍs���͈̔͂��Ă���Ƃ����Ă��d�����Ȃ������Ǝv���܂��B
�A�����ێ����͍ō��قɓ��ӂł����A���S���ӂƂ����킯�ł͂���܂���B���R���q�ׂĂ����܂��B
�u�����̊T�v�A���̍l���v
�A�����ێ����ł́A�A������Ȃɋ���ł����G�z�o�̏ؐl�̐M�҂ł��銳�҂ɗA���������Ƃ������ƂŁA�a�@���i����ꂽ�����ł��B�ō��ق͊��҂����Ȍ��茠�A�܂�l�i���͑��d�����ׂ����̂ł���Ƃ��A����ɂ��킦�a�@�����A�������邩������Ȃ��Ƃ���������ӂ����Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��A���ґ��̑i����F�߂܂����B���̎����ł́A�a�@���A�܂��҂��A�������邩������Ȃ��Ƃ������Ƃ����҂Ɉ�ؓ`���Ȃ������_�����ł���Ǝv���܂��B��҂͎��Ë��ۂ�����Ă��܂����Ƃ����O���ėA���ɂ��ē`���Ȃ������悤�ł����������Ɋ��҂̂��Ƃ��v���Ă��������̂Ȃ�Ύd���Ȃ������͂��邩������܂���B���������̂悤�ȍs�ׂ��p�^�[�i���Y�����Ă�܂��B��������ɂ���҂��ア����̎҂̗��v�ɂȂ邩��Ƃ����ď���Ȕ��f�����邱�Ƃ��p�^�[�i���Y���ƌĂт܂��B����Ɉ�Ö@�Ŋ��҂ɑ��Ĉ�t�͎��Âɂ��Ă̐��������ׂ��ł���Ɛ����`�����K�肳��Ă��邽�߁A���̐��������Ȃ������a�@���ɗ����x���������ƌ��킴��܂���B����ɉ������҂ɂ����Ȍ��茠������܂��B�ō��ق͂��̕����ɐG��Ă��āA�A�������Ȃ��Ƃ�����ȂȈӎv�͑��d�����ׂ��ӎv�ł���Ƃ���Ă��܂��B�����������Ȍ��茠�͑厖�ł��葸�d����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������ɂ͑傢�ɓ��ӂł��܂��B��������҂̗���ɂȂ��čl���Ă݂�ƁA�@���ɂ͊W�Ȃ��ł��������ڂ̑O�̊��҂��A�������Ȃ��Ǝ���ł��܂��Ƃ�����Ԃ̂Ƃ��ɗA��������Ώ�����̂ɂ��ւ�炸�A�A�������ۂ���Ă���̂ŗA�������Ȃ��������ʁA���҂����𗎂Ƃ��Ă��܂����ꍇ�A��t�����ɐӔC�����������҂����������Ƃ����v���������l���ł������ꍇ�A���_�I�Ȗʂł̕��S�͑傫���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����łȂ��Ƃ��A���҂����S�����Ă��܂����ꍇ����͂���ʼn��炩�̖�肪��������\��������Ɨ\���ł��邽�߁A���҂̐�����芳�҂̈ӎv��D�悵�čőP��i�����Ȃ��Ƃ������f������͓̂���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̔���͈�t��������D�悷�邩�A���҂̎��Ȍ��茠��D�悷�邩�Ƃ����������𔗂�ꂽ�����ł���܂��B���̂��ߍō��ق̏q�ׂĂ��邱�Ƃ͓��ӂł��镔���͑����ł����A��t�̗���ɂȂ��čl���Ă݂�Ɗ��S�ɓ��ӂł���킯�ł͂Ȃ��Ƃ������_�Ɏ���܂����B
�Ō�������i���ɂ��Ăł��B���̎����ɂ��ẮA���R�ȊO���ӂł��܂���B
�u�����̊T�v�Ǝ��̍l���v
�����̒�������́A�d�x�̔x���j���҂Œ��N�ɂ킽�荑�����R�×{���ɓ������A�����ی�@�Ɋ�Â���Õ}���ƌ��z600�~�̓��p�i��̐����}�����Ă��܂����B���̌�A��������́A���Z���猎�z1500�~�̎d������邱�ƂɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A���R���̒ÎR�s�Љ�����������́A����1500�~����600�~���A����܂Ő����}���Ƃ��Ďx������Ă������p�i��ɂ��Ă��������}����p�~���A����Ɏc���900�~���A��Ô�̈ꕔ���ȕ��S���Ƃ��Ē�������ɕ��S������A�Ƃ������e�̕ی�ύX������s���܂����B��������́A���̌����s���Ƃ��A���Ȃ��Ƃ��d���肩��1000�~����p�i��Ƃ��Ď茳�Ɏc���ė~�����Ƃ����s���\�����Ă����R���m���ƌ�����b�ɑ��čs���܂����A���ꂼ��p���ٌ̍����Ȃ���܂����B���p�i��z600�~�Ƃ��������̐����ی��́A�����ł�����2�N��1���A�p���c�ł�����1�N��1�������w���ł��Ȃ��قǂ̋��z�������Ƃ����܂��B��������͂�����Č�600�~�̐����ی��͌���������Ƒi�����N�����܂����B
���R�̓����n�ق͒�������̑i����F�ߎ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����̊�Ƃ́A����̍��ɂ��������̎��_�ɂ����ċq�ϓI�Ɍ��肷�ׂ��ł���v�Əq�ׂĂ��܂��B���͂��̑��R�̔��f�͔[���������܂��B���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����������ł�����2�N��1���A�p���c�ł�����1�N��1�������w���ł��Ȃ��قǂ̋��z�ł������킯���Ȃ��Ǝv������ł��B���������R�̓������ق͖{���̌��z600�~�Ƃ����ی��́u�����Ԃ��z�v�ł͂��邯��ǂ���@�Ƃ܂ł͒f��ł��Ȃ��Ƃ��āA���R�����n�ٔ������������܂����B�����̒������͍ō��ق܂ł����Ă������Ƃ����悤�ł����A�ō��ق͒��������S�������Ƃɂ�肱�̑i�ׂ͏I�������Ƃ������f�������܂����B����ɍō��ق͎��̂悤�ɏq�ׂ܂����B�u���{�����@25���́u�������v�́A�X�̍����ɑ��ċ�̓I�Ȍ�����ۏႵ�����̂ł͂Ȃ��A���̎����̂��߂ɍ������^�c���ׂ��ӔC�����ɂ���Ƃ������Ƃ�錾�������̂ɉ߂��Ȃ��B�Ȃɂ��u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����v�ɂ�����̂��́A������b�̍ٗʂɈς˂��Ă���A���̍ٗʌ��̍s�g�ɒ��������p������ꍇ�͕ʂƂ��āA������b�ɂ�鐶���ی��̌��肪�����Ɉ�@�Ƃ���邱�Ƃ͂Ȃ��v���̂悤�ȍl�������v���O�����K����ƌĂ����̂ł��B���̍��قƍō��ق̍l�����ƍ����̂��߂ɓw�͖ڕW�͂��Ă邪�A���Ԃ��ǂ��ł��ꍑ���̐��͕����Ȃ��Ƃ����������Ȃ��̂Ɍ����Ă��܂��B���R�̏q�ׂ��悤�ɓw�͂���Ȃ�q�ϓI�ɔ��f���邱�Ƃ��`���t���A���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����������錠����ۏႷ��ׂ����Ǝv���܂����A�����������̊���͂����肵�Ȃ��Ƃ����������邽�߂ɓ���Ƃ��낪����܂��B
�o�T�A���p��
�R�g�o���N ���쎖��
https://kotobank.jp/word/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6-84491
���{�����@�̊�b�m�� �����s�ט_
http://kenpou-jp.norio-de.com/touchikouiron/
�����b�N�X�@�w�� �������ێ��� �A�����ێ���
�ٌ�m�h�b�g�R�� �����Љ�_
https://www.bengo4.com/saiban/d_7059/
�@�w�ٌ��@������ �����i��
http://www.jicl.jp/now/date/map/33.html
�R�g�o���N �v���O�����K���
https://kotobank.jp/word/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0%E8%A6%8F%E5%AE%9A-127908
�������[
�������̐l���ƍٔ����Ƃ����e�[�}�ɑ��ďo�������_�͍ٔ����������s�����ٗʍs���ɓ��Ă͂܂鎖���������Љ�_�ɓ��Ă͂܂鎖���ł͂Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮA���@�ɂ���l��
���N�Q����Ă���ꍇ�A�l�������������ʂ����Ă���Ƃ������Ƃł���B�ȉ��ɁA���̂悤�ɍl�������R�ɂ��ďq�ׂ�B
�������̂悤�ɍl�������R�͂T����B�܂��P�ڂ̗��R�ł��������s���Ƃ��̔���ł������쎖���ɂ��Ăׂ̂�B�����s���Ƃ͒��ڍ��Ɠ����̊�{�Ɋւ��鍂�x�ɐ������̂��鍑�ƍs�ׂł���A�@����̑i�ׂƂ��čٔ����ɂ��@���I�Ȕ��f���\�ł��邪�����̐�����A�i�@�R���̑Ώۂ��珜�O�����s�ׂ̂��Ƃł���B���̂��Ƃ������ꂽ���Ⴊ���쎖���ł���B���쎖���Ƃ͍��쒬�ɂ������ČR��n�̊g���H���ɔ�����l�X���ČR��n�ɐ����[�g���N�������Ƃ�����Ĉ��S�ۏ���Ɋ�Â��s������ɔ����Y�����ʖ@�Q���ᔽ�ŋN�i���ꂽ�Ƃ��������ł���B���̎����ɑ��čٔ����͌��@�X���͐�͂̕s�ێ��ɂ���Đ�����h�q�͂̕s���ɂ��đ����Ɉ��S�ۏ�����߂邱�Ƃ��ւ��Ă͂��Ȃ��Ƃ������Ƃƍ��Ƃ̑����̊�b�ɋɂ߂ďd��ȊW���������x�Ȑ�������L���邽�߁A�ꌩ�ɂ߂Ė����Ɉጛ�����ƔF�߂��Ȃ�����͍ٔ����̎i�@�R���̊O�ɂ���Ƃ��������s���_��
��̗��R����i����ނ����B���̔���ɑ��Ď��̍l�����q�ׂ�ƁA�����s�ט_�Ŕ��f�ł��Ȃ��Ƃ����Ȃ�����Ƃ��������������A�ꌩ�ɂ߂Ė����Ɉጛ�����ƍl��������̂����Ɉጛ�������o�����ق����������ጛ�����킩��₷���ƍl����B
���ɁA�Q�ڂ̗��R�ł����ٗʍs���Ƃ��̔���ł��������i���ɂ��ďq�ׂ�B�ٗʍs���Ƃ͍s���s�ׂ̂����v���܂��͓��e�ɂ��Ė@������`�I�ɖ��m�ȊT�O�Œ�߂Ă��Ȃ��ꍇ���A�܂�������߂Ă��Ȃ��ꍇ���A�܂��͓��Y�s���s�ׂ��s�����Ƃ��ł���ƒ�߂Ă���ꍇ�ɍs�����̍ٗʂɊ�Â��ĂȂ����s�ׂł���B�܂��s���̍ٗʂɔC����Ă��鎖�����ٔ������������ɐR�����邱�Ƃ́A�s���̍ٗʌ���N�Q���Ă��܂����ƂɂȂ邽�߁A�ٗʌ��̈�E�܂��͗��p���F�߂���ꍇ�⒘�����s�����ł��邱�Ƃ������ł���ꍇ�A�ȊO�͍ٔ����̍ٔ������ٗʍs���ɂ͂����ł��Ȃ��B���̂��Ƃ���������Ƃ��������i��������B�����i���Ƃ͌���X�͍����×{���ɓ������Ă��Ĉ�Õ}������ѐ����}�����Ă��������Z����d���肪�����悤�ɂȂ������߂ɁA�s�̕����������̏�����X�̐����}����p�~����Ô�̈ꕔ�����ȕ��S�Ƃ������߂�X�������ی�@�̋K�肷�錒�N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������邽�߂ɂ͊z�����Ȃ���@�ł���ƍ���i���������ł���B���̎����ɑ��čٔ����͏㍐�̍Œ���X�������ߑi�ׂ̌p���͔F�߂��Ȃ��Ƃ������Ƃ���ƌ��@�Q�T���P���͂��ׂĂ̍��������N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�݂���悤�ɍ����^�c���ׂ����Ƃ����̐Ӗ��Ƃ��Đ錾�������ƂɂƂǂ܂蒼�ڌX�̍����ɋ�̓I�Ȍ�����t�^�����킯�ł͂Ȃ��Ƃ����v���O�����K����̗�����ٔ������Ƃ��Ă�������X�̑i����ނ����B�������͌��@�Q�T���P���̌�����L����Əɏ����Ă��邱�ƂƏ����ۓI�ł��邱�Ƃ���@�I�������̒��ۓI�������̗�����ٔ����͂Ƃ�X�̌������͕ی삷�ׂ��������ƍl����B
���ɁA�R�ڂ̗��R�ł��������Љ�_�Ƃ��̂��Ƃ���������ł���x�R��w�����Ƌ��Y�}�ѓc�����ɂ��ďq�ׂ�B�����Љ�_�Ƃ͌��@��̏d�v�ȋ@�֖��͌��@�セ�̒c�̂̎��������F�߂��Ă���c�̂̓����I�����ɂ��ẮA���Ƃ��@����̑i�ׂɂ�����ꍇ��
���A
���̎��������含�d���ٔ����͂��̔��f�����邱�Ƃ͍T����ׂ��Ƃ��������ł���B
���̂��Ƃ������ꂽ���Ⴊ�x�R��w�����Ƌ��Y�}�ѓc�����ł���B�x�R��w�����Ƃ͕x�R��w�̌o�ϊw���̋���A���w�����̎w���ɔ����Ď��Ƃ𑱂������Ɛ��ѕ]�������{������
�w���������Y���Ƃ̒P�ʔF�蔻�f���s��Ȃ��������߁A�w�����P�ʕs�F��̈�@�m�F�ƒP�ʔF��`���̑��݂̊m�F�����߂������ł���B����ɑ��čٔ����͈�ʎs���Љ�̒��ɂ����Ă���Ƃ͕ʌɎ����I�Ȗ@�K�͂�L�������ȕ����Љ�ɂ�����@����̌W���̂��Ƃ��́A���ꂪ��ʎs���@�����ƒ��ڂ̊W��L���Ȃ������I�Ȗ��ɂƂǂ܂����A���̎���I�A�����I�ȉ������ς˂�̂�K���Ƃ��A�ٔ����̎i�@�R���̑ΏۂɂȂ�Ȃ��Ƃ������Ƒ�w�͍������ł���Ǝ����ł���Ƃ��킸�w���̋���Ɗw�p�̌����Ƃ�ړI�Ƃ��鋳�猤���{�݂ł����āA���̐ݒu�ړI��B�����邽�߂ɕK�v�ȏ������ɂ��ẮA�����I�ŕ�I�Ȍ��\��L���A��ʎs���Љ�Ƃ͈قȂ����ȕ����Љ���`�����Ă��邩
���ʎs���@�����ƒ��ڂ̊W��L���Ȃ������I�Ȗ��͎i�@�R�����珜�����ׂ����Ƃ����邩��ł���B�܂��P�ʔF��s�ׂ́A��ʎs���@�����ƒ��ڂ̊W��L������̂ł��邱�Ƃ��m�F����ɑ������i�̎���Ȃ����菃�R�����w�����̖��Ƃ��đ�w�̎���I�Ŏ����I�Ȕ��f�Ɉς˂���ׂ��ł����čٔ����̎i�@�R���̑ΏۂɂȂ�Ȃ��Ƃ����R�̗��R�Ŋw�����̑i����ނ����B���̔���ɑ��Ă̎��̍l�����q�ׂ�ƁA���̎����̌�ɋN�������w����U�Ȃ̏C���F��Ɋւ��Ă͎i�@�R���̑ΏۂɂȂ��Ă���̂ł��̎������A�w�����̌����Ȃǂ����݂�ׂ��������Ǝv���B���ɁA���Y�}�ѓc�����ɂ��ďq�ׂ�B
���Y�}�ѓc�����Ƃ͓��{���Y�}�̊����ł���ѓc�������A�}�ψ����{�{������Ƃ̑Η��ɂ��}���珜�����������Z���Ă����}���L�̉Ɖ��𖾂��n���悤�ɋ��߂�ꂽ�Ƃ��������ł���B����ɑ��čٔ����̌����Ƃ��ẮA���}�͍����̐����I�ӎv�������ɔ��f���邽�߂̂����Ƃ��L���Ȕ}�̂ł���A�c������`���x���邤���ł���߂ďd�v�ȑ��݂ł��邩��A���x�̎��含�Ǝ�������^���Ď���I�ɑg�D�^�c���Ȃ����鎩�R��ۏႷ��K�v������B���}�̓����I�������ɑ�����s�ׂ́A�@���ɓ��ʂ̒�߂̂Ȃ�����͑��d���ׂ��ŁA�}���ւ̏�������ʎs���@�����ƒ���̊W��L���Ȃ������I�Ȗ��ɂƂǂ܂����A�ٔ����̐R�����͋y�Ȃ����ƂɂȂ��Ă���Ƃ������ƂƁA�{������������
�A�����I�K�͂Ƃ��Ă̓}�K��ɑ����ĂȂ���A�}�K�����Ǒ��ɔ�����ȂǓ��i�̎���̗L���ɂ��咣�����Ȃ��A���̎葱���ɂ͉��̈�@���Ȃ����ߏ��������͗L�����Ƃ���Ă���B���̔���ɑ��Ă̎��̍l�����q�ׂ�ƁA�m���ɐ��}�͍����̐����I�ӎv�������ɔ��f���邽�߂̍ł��L���Ȕ}�̂ł��邪�����܂ŕی삷��K�v�͂Ȃ��ƍl����
�B
���ɂS�ڂ̗��R�ł����M���̎��R�Ƃ��̂��Ƃ�����������ł���_�ˍ��ꌕ�����Z���ێ����ɂ��ďq�ׂ�B�M���̎��R�͓��S�ɂ������M�̎��R�Ə@���I�s�ׂ̎��R�Ə@���I���Ђ̎��R�̂R�ɕ�����Ă���B���S�ɂ������M�̎��R���ۏႷ��̂́A����̐M�����A���邢�͎����Ȃ����R�ƁA�M����������A���邢�͍������Ȃ����R�ł���B
�܂��A���S�ɂ�����M�́A���S�ɂƂǂ܂�����ΓI�ɕۏႳ��Ă���B�@���I�s�ׂ̎��R�͏@����̋V����z����`���s�����R�Ə@���������s��Ȃ����R���ۏႵ�Ă���B
�@���I���Ђ̎��R�͏@���I���Ђ����鎩�R�Ə@���I���Ђ�����Ȃ����R��ۏႵ�Ă���B���̐M���̎��R��ۏႵ�����ƂŗL���Ȕ��Ⴊ�_�ˍ��ꌕ�����Z���ێ����ł���B
�_�ˍ��ꌕ�����Z���ێ����Ƃ͎s���H�ƍ���̐��k�ł�����X�͎���̐M�����G�z�o�̏ؐl�Ƃ����@���̋��`�𗝗R�ɑ̈���Ƃɂ����錕�����Z�ւ̎Q�������ۂ��A���|�[�g��
�o�Ȃǂ̑�֑[�u�����߂����A�Z��Y��͂����F�߂Ȃ������B���ʁAX�͑̈�̐��т��F�肳�ꂸ�Q�N�����Č������u������������A�w���ɏ]���đފw�����Ƃ��ꂽ�BX��Y�ɑ��Č������u�Ƒފw�����̎����������߂������ł���B����ɑ��čٔ����͑̈�Ȗڂɂ�鋳��ړI�̒B���́A��֕��@�ɂ���čs�����Ƃ�������\�ł��������Ƃ�
X�̎�u���ۂ́A���̐M�̊j�S�����Ɩ��ڂɊ֘A����^���Ȃ��̂ł���AX�����s���v���ɂ߂đ傫�Ȃ��̂ł��������ƂƉ��炩�̑�֑[�u���Ƃ邱�Ƃ̐���A���̕��@�A�ԗl���ɂ��ď\���ɍl�����ꂽ�Ƃ͓��ꌾ�����A��֑[�u���Ƃ邱�Ƃ��s�\�ł������Ƃ������Ȃ��B��������������ɏƂ点�AY�̏����͎Љ�ϔO�㒘�����Ó����������AY�̍ٗʌ��͈̔͂��邱�ƂȂǂ������㍐�����p�����B���̔���ɑ��鎄�̍l�����q�ׂ�ƁA���̎����̏d�v�ȕ����͑�֑[�u�̗L�����G�z�o�̏ؐl�̋��`�̊j�S�ɖ\�͂��ӂ���Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ƃ�����������X�����i�ł����̂ł͂Ȃ����ƍl����B
�@���ɁA�T�ڂ̗��R�ł������Ȍ��茠�Ƃ��̔���ł���A�����ێ����ɂ��ďq�ׂ�B
���Ȍ��茠�Ƃ́A�l�����̌l�I�Ȏ����ɂ��āA�����͂��犱����邱�ƂȂ����猈�肷�邱�Ƃ��ł���Ƃ��������������B��̓I�ɂ͎q���������ǂ����ȂljƑ��݂̍�������߂鎩�R�⎩�Ȃ̐����̏I���������Ō��肷�鎩�R�Ȃǂ���������B�������Ȍ��茠��F�߂����Ⴊ�A�����ێ����ł���B�A�����ێ����Ƃ��G�z�o�̏ؐl�̐M�҂ł���X����p�̂܂��Ɉ�tA�ɗA�������ۂ���|��`�����B��tA��X�̗A�����ۂ̈ӎv�d���Ăł������A�����s��Ȃ����A�A���ȊO�ɂ͋~����i���Ȃ����ԂɎ������Ƃ��́A���҂���т��̉Ƒ��̑��ۂɂ�����炸�A��������j���̂��Ă������A���Ë��ۂ����O����X�ɐ��������Ȃ������BA���͗A�����K�v�Ȏ��Ԃ�������\�������邱�Ƃ�F�������̏���������������X�Ɏ�p���{�H���A�������Ȃ�����X���~�����Ƃ��ł��Ȃ��\���������Ɣ��f���ėA�����s�����B���̂��Ƃ�X�����葹�Q�����𐿋������Ƃ��������ł���B
����ɑ��čٔ����͊��҂��A�����邱�Ƃ͎��Ȃ̏@����̐M�O�ɔ�����Ƃ��āA�A�����s����Ís�ׂ����ۂ���Ƃ̖��m�Ȉӎv��L���Ă���ꍇ�A���̂悤�Ȉӎv��������錠���́A�l�i���̂P���e�Ƃ��đ��d�����B�܂�A,�Ȃǂ�X�ɑ��Ė{�����j���������A���̎�p���邩�ۂ���X���g�̈ӎv����Ɉς˂�ׂ��ł������BA����X�Ɏ��Â̐��������Ȃ��������߂ɗA�����\�����������{����p���邩�ۂ��̈ӎv��������錠����D�����_��X�̐l�i����N�Q�����Ƃ�����B
���̎����ɑ��鎄�̍l�����q�ׂ�ƁA���̎����̏d�v�ȕ����͈�t���p�^�[�i���Y����
���҂����Ȍ��茠�ǂ����D�悷�ׂ����Ƃ����Ƃ���ł���B����̎�����X�����i�ł������R��A�������ĂɗA���̉\���������p�����Ȃ������炾�ƍl����
�ȏ�̂��Ƃ���A�ٔ����͓����s�ׂ�ٗʍs�ׂɓ��Ă͂܂鎖���╔���Љ�_�����Ă͂܂鎖���ł͂Ȃ��ꍇ�ɂ����Ă͌��@�ɂ���l�����N�Q����Ă���ꍇ�ɐl������������
�ʂ����Ă���ƍl����B
�Q�l�����@�V����n���h�u�b�N���@�@�R�ԁ@�Q�W�ԁ@�U�T�ԁ@�P�U�T�ԁ@�P�U�U��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�X�O�ԁ@�P�X�P��
���c�m�P
�l���ƍٔ����̌���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@14J118017 ���c�@�m�P
�E���_
�ٔ����̌����ɂ���čٔ��͍s���l���͎���Ă����B�����A���ׂĂ̍ٔ��ɂ����čٔ����̌������K�p�����Ƃ͂����Ȃ��B
�P�E��{�I�l���ƍٔ���
�@�܂��́A��{�I�l���ƍٔ����̌����ɂ��čl���Ă����B
�@��{�I�l���Ƃ́A���������l�Ԃ炵�������Ă������߂ɂ��錠���̂��ƁB��{�I�l���̒��g�͑傫�������ĂT�ɕ�������B�������A���R���A�Љ�A�Q�����A�������̂T���B
�����͎���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł���A�N�Q����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�l��������Ă��Ȃ��A�N�Q���ꂽ�Ƃ��ٔ����͂ǂ̂悤�Ȕ����������̂��B�l���ɂ��Ă̍ٔ��ŗL���ȍٔ�������B����́A�����i�����B�����i���Ƃ́A�P�X�T�V�N�i���a32�N�j�����A�������R�×{���ɓ������Ă���������������b����A���{�����@��Q�T���ɋK�肷��u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�ތ����v�i�������j�Ɛ����ی�@�̓��e�ɂ��đ������s���i�ׂł���B
�@���j���҂ł��錴���́A���{�����{�����J��600�~�̐����ی싋�t���ƈ�Õ}������̂��āA�������R�×{���Ő������Ă������A���X600�~�ł̐����͖����ł���A�ی싋�t���̑��z�����߂��B�P�X�T�U�N�i���a31�N�j�A�ÎR�s�̕����������́A�����̌Z�ɑ���1,500�~�̎d����𖽂����B�s�̕����������͓��N8��������]���̓��p�i��i600�~�j�̎x���������{�l�ɓn���A���镪��900�~����Ô�̈ꕔ���ȕ��S���Ƃ���ی�ύX�����i�d����ɂ���ĕ���������900�~�͈�Ô�Ƃ��ė×{���ɔ[�߂�A�Ƃ������́j���s�����B����ɑ��A���������R���m���ɕs���\�����Ă��s�Ȃ������p������A�����Ō�����b�ɕs���\���Ă��s�Ȃ����A������b��������p���������Ƃ���A�������s���s���R���@�ɂ��i�ׂ��N����ɋy���̂ł���B
�����̎咣�́A�����́u�����ی�@�ɂ��ی�̊�v�ɂ��x������Ⴗ����Ǝ������A���{�����@��25���A�����ی�@�ɋK�肷��u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�ތ����v��ۏႷ�鐅���ɂ͋y�Ȃ����Ƃ���A���{�����@�ᔽ�ɂ�����Ǝ咣�����B
�@���R�̓����n���ٔ����́A���p�i��z��600�~�ɗ}���Ă���͈̂�@�ł���Ƃ��A�ٌ������������i�����̑S�ʏ��i�j
�@���R�̓��������ٔ����́A���p�i�600�~�͂����Ԃ�Ⴂ���A�s���z��70�~�ɉ߂������@��25���ᔽ�̈�ɂ͒B���Ȃ��Ƃ��āA�����̐��������p�����B
�@�㍐�R�̓r���Ō��������S���i1964�N2��14���Ɏ����j�A�{�q�v�Ȃ��i�ׂ𑱂������A�ō��ٔ����́A�ی���錠���͑����ł��Ȃ��Ƃ��A�{�l�̎��S�ɂ��i�ׂ͏I�������Ƃ̔������������B
�@�ō��ٔ����́A�u�Ȃ��A�O�̂��߁v�Ƃ��Đ����}����̓K�ۂɊւ���ӌ����q�ׂĂ���B����ɂ��ƁA�u���@25��1���͂��ׂĂ̍��������N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�ݓ���悤�ɍ������^�c���ׂ����Ƃ����̐Ӗ��Ƃ��Đ錾�����ɂƂǂ܂�A���ڌX�̍����ɋ�̓I�����^�������̂ł͂Ȃ��v�Ƃ��A�����̌����͖@���i�����ی�@�j�ɂ���Ď����Ηǂ��Ƃ����B�u�������N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����ł��邩�̔F�蔻�f�́A������b�̍��ړI�ȍٗʂɈς���āv����A�Ƃ���B
�ٗʍs���Ƃ́A�s���s�ׂ̂����C�v���܂��͓��e�ɂ��Ė@������`�I�ɖ��m�ȊT�O�Œ�߂Ă��Ȃ����C�܂�������߂Ă��Ȃ��ꍇ�C�܂��͓��Y�s���s�ׂ��s�����Ƃ��u�ł���v�ƒ�߂Ă���ꍇ�ɁC�s�����̍ٗʂɊ�Â��ĂȂ����s�ׂ̂��Ƃ��B
�@�����čō��ق͂����ŁA�v���O�����K������N�����B�v���O�����K����Ƃ́A���@�̓���̐l���K��Ɋւ��āA�`���I�ɐl���Ƃ��Ė@���ɂ����Ă͋K�肳��Ă��Ă��A�����I�ɂ͍��̓w�͖ڕW����I���j���K�肵���ɂƂǂ܂�A���ڌX�̍����ɑ��ċ�̓I�����^�������̂ł͂Ȃ��Ƃ���l�������B
�@�͂����Ă����̔����͐l���d���Ă���̂��A�Љ�͕ۏ���Ă���̂��B���͂��̔������������ۏ͂���Ă��Ȃ��Ǝv���B�v���O�����K������ٗʍs����p���č��͐������ɂ��ĞB���Ȍ��������Ă���̂ł͂Ȃ��̂��B���@�̓���̐l���K��Ɋւ��āA�`���I�ɐl���Ƃ��Ė@���ɂ����Ă͋K�肳��Ă��Ă��A�����I�ɂ͍��̓w�͖ڕW����I���j���K�肵���ɂƂǂ܂�A���ڌX�̍����ɑ��ċ�̓I�����^�������̂ł͂Ȃ��Ƃ����B�w�͂������Ă�����̂��B�w�͂��Ă��l�̖����~���Ȃ���ΈӖ����Ȃ��Ǝ��͎v���B
�Q�E�l���Ɋւ���@�����
�@���ɁA������܂��傫�Ȗ��ƂȂ����l����肾�B������G�z�o�̏ؐl�Ƃ������@�����ւ�����l����肾�B���R���̒����M���̎��R������B���������Ȃ�������Ȃ��P�̌������B�ł́A���̖��ƂȂ����G�z�o�̏ؐl�Ɋւ���A�����������Ă������B
�@�G�z�o�̏ؐl�̐M�҂ł���X�́A�@����̐M�O����A�������ۂ���Ƃ����ł��ӎv��L���Ă����B�����̊̑����ǎ�Ƃ̐f�f����X�́A�P�X�X�Q�N�W���A���A����p�̎��т̂��铌����w��Ȋw�����������a�@�ɓ��@���A��tA�ɗA�����ۂ̈ӎv��`�����B��Ȍ��́A�u�G�z�o�̏ؐl�v�̐M�҂̗A�����ۂ̈ӎv�d���A�ł������A�����Ȃ����A�A���ȊO�ɂ͋~����i���Ȃ����ԂɎ������Ƃ��́A���ҋy�т��̉Ƒ��̑��ۂɂ�����炸�A��������j���̂��Ă������AA����X�̎��Ë��ۂ����O���Ė{�����j��X�ɐ������Ȃ������BA���͓��N�X���A�A�����K�v�Ȏ��Ԃ�������\�������邱�Ƃ�F�������̏������������X�Ɏ�p���{�s���A�A�����Ȃ�����X���~�����Ƃ��ł��Ȃ��\���������Ɣ��f���ėA���������B��p��ɗA���̎�����m����X�́A����A���ɑ��đ��Q�����𐿋������B
�@�ٔ����̌����́A�@���҂��A�A�����邱�Ƃ͎��Ȃ̏@����̐M�O�ɔ�����Ƃ��āA�A������Ís�ׂ����ۂ���Ƃ̖��m�Ȉӎv��L���Ă���ꍇ�A���̂悤�Ȉӎv��������錠���́A�l�i���̈���e�Ƃ��đ��d�����B�AX���@����̐M�O����A�����ۂ̌ł��ӎv��L���Ă���A���A����p�����҂��ē��@�������Ƃ�A�����m���Ă����{���ł́AA����X�ɑ��{�����j��������āAA���̎�p���邩�ۂ���X���g�̈ӎv����Ɉς˂�ׂ��������BA���́A�E������ӂ������Ƃɂ��A�����\���̂������{����p���邩�ۂ��ɂ��Ĉӎv��������錠����D�����_�ŁAX�̐l�i����N�Q�����B�Ƃ��������������Ă���B
�@���̍ٔ��̔����ł͌����������i�����B
�@�@�����������G�z�o�̏ؐl�Ƃ͂����������Ȃ̂��B�G�z�o�̏ؐl�́A�@���c�̂̂��Ƃ��B�A�����J�ɖ{���̂���L���X�g���n�̏@���c�̂ŁA�����ɋL����Ă��邱�Ƃ��ʂ�Ɏ��H���邱�Ƃ�����Ă���B���̋����̒��ɂ́A�i���_�̔ے�A�R���ւ̓������ہA�\�͂�i���Z�̔ے�Ƃ��������Ƃ̑��Ɂu�A���̋֎~�v������B�����̒��ɗA����������s�ׂƂ��Ĕᔻ����L�q�����邽�߁A�A�������Ȃ����Ƃ́A�G�z�o�̏ؐl�̐M�҂����˂Ȃ�Ȃ����܂�̈�ɂȂ��Ă���B
�@�G�z�o�̏ؐl�A�������ł́A���Ȍ��茠������̂ɂ�������炸��t�̌����p�^�[�i���Y���i��������ɂ���҂��ア����̎҂̈ӎu�ɔ����āA�ア����̎҂̗��v�ɂȂ�Ƃ������R����A���̍s���ɉ��������A�������肷�邱�Ɓj�ɂ���Ė{�l�̈ӎv�ɔ����čs�����N�������B���̎��_�ŁA���Ȍ��茠�͐N�Q����Ă���Ǝv���B�܂��A�A���ɂ��Ă̐�������t�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ����ł͂Ȃ��̂��Ǝv���B���̍ٔ��ŁA��Ì���ł����Ȍ��茠�����d�����ׂ��Ƃ����l���𐢂̒��ɍL�߂��̂ł͂Ȃ��̂��B
�R�E�i�@���̌��E
�@�ٔ��͂ǂ�Ȗ��ł��ق���Ƃ͌���Ȃ��B�ٔ��ɂ����E�A�i�@���̌��E������B���̒��̂P�������s���Ƃ������̂�����B�����s���Ƃ́A���x�Ȑ������������߁A�i�@���ɂ��R���̑Ώۂ��珜�O���ׂ����̂Ƃ���鍑�ƍs�ׂ̂��Ƃł���B�ł́A�Ȃ��ٔ����͍��x�Ȑ�������тт����ƍs�ׂɂ��Ďi�@���f�����Ȃ��̂��B�ЂƂ́A�����������Ƃ��ٔ����͔��f����ƁA���ʔ@���ł͑傫�ȍ��������������ꂠ��Ƃ��闝�R����ł���B������u�������v�Ƃ����B���Ƃ̊�{�I�Ȏ����́A�����܂Ŗ����`�@�ւ̌X���������������t�̔��f�Ɉς˂�ׂ��A�ٔ����͉�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�u���x�Ȑ�������тт����ƍs�ׁv�ɁA�i�@���͓���܂Ȃ��Ƃ��āA�����͖����`�̌���Ɉς˂�ׂ��Ƃ����̂́A�����I�ȍl�����B
�@�����A�������_��ς��Ă݂�ƍٔ����͓����Ă���̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ����������ł���B����́A�s���Ɏi�@�����k�������Ă��Ȃ����A����Ȃ�Ől���~�ςȂ�đS���ł���̂��Ƃ����������o�Ă���B���������������s���Ŗ��ɂȂ�������������B���쎖�����B
�@���쎖���Ƃ́A�P�X�T�V�N�V���W���ɓ��ʒ��B���������B�ǂ��������ʂ������ۂɁA��n�g���ɔ�����f�����̈ꕔ���A�A�����J�R��n�̗�������֎~�̋��E����A��n���ɐ�m�����������Ƃ��āA�f�����̂���7�������{���ƃA�����J���O���Ƃ̊Ԃ̑����͋y�ш��S�ۏ����Z���Ɋ�Â��{�y�ы����тɓ��{���ɂ����鍇�O���R���̒n�ʂɊւ��鋦��̎��{�ɔ����Y�����ʖ@�ᔽ�ŋN�i���ꂽ�������w���B
�@�ō��ق̔����́A�u���@��9���͓��{���匠���Ƃ��Ď��ŗL�̎��q����ے肵�Ă��炸�A�������֎~�����͂Ƃ͓��{�����w���E�Ǘ��ł����͂̂��Ƃł��邩��A�O���̌R���͐�͂ɂ�����Ȃ��B���������āA�A�����J�R�̒����͌��@�y�ёO���̎�|�ɔ����Ȃ��B�����ŁA���Ĉ��S�ۏ���̂悤�ɍ��x�Ȑ������������ɂ��ẮA�ꌩ���Ă���߂Ė����Ɉጛ�����ƔF�߂��Ȃ�����A���̓��e�ɂ��Ĉጛ���ǂ����̖@�I���f���������Ƃ͂ł��Ȃ��v�i�����s���_�̗p�j�Ƃ��Č�������j�����n�قɍ����߂����B
�@���x�̐����Ɋւ��邱�Ƃ͍ٔ����͍ق��Ȃ��B�܂�A�ٔ����̌����ł͂ǂ��ɂ��ł��Ȃ����Ȃ̂ł���B�O�������Ƃ��ւ��̂���b���B���@�{�ɂ����闧�@�ɂ��@�Đ����ɍٔ����ً͈c�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�܂��A�x�@�\�����ጛ�i�ׂƂ������ٔ��ł������悤�Ȍ������ł���B�ٔ����́A��̓I�ȑi�ׂ���N����Ȃ��̂Ɍ��@�y�т��̑��̖@�����ɔ��f�����������͂Ȃ��Ƃ����B
�@���ɂ��ٔ������ق��Ȃ���肪����B����́A�����Љ�_���B�����Љ�_�Ƃ́A���{�̎i�@�ɂ����āA�c�̓����̋K�����ɂ��Ă͎i�@�R�����y�Ȃ��A�Ƃ���@���̂��Ƃ��B
�x�R��w�����͂����Ⴞ�B�x�R��w�̊w�������C���Ă����Ȗڂ̒P�ʏC����F�߂��Ȃ��������ƂŒP�ʕs�F�蓙�̈�@�m�F�����߂��s���i�ׁB�����́A�㍐���p�B�u��w�́A�������ł���Ǝ����ł���Ƃ��킸�A�w���̋���Ɗw�p�̌����Ƃ�ړI�Ƃ��鋳�猤���{�݂ł����āA��ʎs���Љ�Ƃ͈قȂ����ȕ����Љ���`�����Ă���̂ł��邩��A���̂悤�ȓ���ȕ����Љ�ł����w�ɂ�����@����̌W���̂��ׂĂ����R�ɍٔ����̎i�@�R���̑ΏۂɂȂ���̂ł͂Ȃ��B�v�Ƃ����B�܂肱�̖��A�����Љ�ɂ��Ă͍ٔ����͌��o���ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�S�E�܂Ƃ�
�@�ٔ����́A���@�A�@���A���A�����s�ׁA�����Љ�_�ɂ��Ă͍ق��Ȃ��B�ٔ����̌������y�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ猛�@�A�@���A���͍������t�ŏ��F����Ăł������̂ł���B����Ɍ����o���ƎO�������Ɉᔽ���Ă��܂��B
�@�܂��A�����i���ł́A�ٗʍs���A�v���O�����K������g���B���Ȍ��������ٔ����͔��f�ł��Ȃ��Ƃ����B�͂����Ă���Ől���͑��d��������̂��B�ٔ����ɂ��ǂ����悤���ł��Ȃ���肪����̂��Ɗ������B�G�z�o�̏ؐl�A�������ł��M���̎��R�����Ȍ��茠��������B���Ȍ��茠���p�^�[�i���Y���Ɋւ�����͑����̂ł͂Ȃ����B�Ⴆ�Ύq�{�N�`���̐ڎ�ɂ��Ă��������Ȍ��茠���p�^�[�i���Y���Ƃ̊W�ł͂Ȃ��̂��Ǝ��͎v���B��������̌����Ȃ�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�����̈ӎv�d���Ă��ꂩ���̐l�������ł��������B
�o�T�E�Q�l����
�����s��
http://www.weblio.jp/content/%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E8%A1%8C%E7%82%BA
���쎖��
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://kenpou-jp.norio-de.com/sunagawa-jiken/
�����Љ�_
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%AB%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6
�ٗʍs��
https://kotobank.jp/word/%E8%A3%81%E9%87%8F%E8%A1%8C%E7%82%BA-68309
�G�z�o�̏ؐl
�V�E����n���h�u�b�N�u���@�v
�����i��
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E8%A8%B4%E8%A8%9F
�v���O�����K���
�p�^�[�i���Y��
https://www.kango-roo.com/word/14115
�l���ƍٔ����̌���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@14J118017 ���c�@�m�P
�E���_
�ٔ����̌����ɂ���čٔ��͍s���l���͎���Ă����B�����A���ׂĂ̍ٔ��ɂ����čٔ����̌������K�p�����Ƃ͂����Ȃ��B
�P�E��{�I�l���ƍٔ���
�@�܂��́A��{�I�l���ƍٔ����̌����ɂ��čl���Ă����B
�@��{�I�l���Ƃ́A���������l�Ԃ炵�������Ă������߂ɂ��錠���̂��ƁB��{�I�l���̒��g�͑傫�������ĂT�ɕ�������B�������A���R���A�Љ�A�Q�����A�������̂T���B
�����͎���Ȃ���Ȃ�Ȃ������ł���A�N�Q����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@�l��������Ă��Ȃ��A�N�Q���ꂽ�Ƃ��ٔ����͂ǂ̂悤�Ȕ����������̂��B�l���ɂ��Ă̍ٔ��ŗL���ȍٔ�������B����́A�����i�����B�����i���Ƃ́A�P�X�T�V�N�i���a32�N�j�����A�������R�×{���ɓ������Ă���������������b����A���{�����@��Q�T���ɋK�肷��u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�ތ����v�i�������j�Ɛ����ی�@�̓��e�ɂ��đ������s���i�ׂł���B
�@���j���҂ł��錴���́A���{�����{�����J��600�~�̐����ی싋�t���ƈ�Õ}������̂��āA�������R�×{���Ő������Ă������A���X600�~�ł̐����͖����ł���A�ی싋�t���̑��z�����߂��B�P�X�T�U�N�i���a31�N�j�A�ÎR�s�̕����������́A�����̌Z�ɑ���1,500�~�̎d����𖽂����B�s�̕����������͓��N8��������]���̓��p�i��i600�~�j�̎x���������{�l�ɓn���A���镪��900�~����Ô�̈ꕔ���ȕ��S���Ƃ���ی�ύX�����i�d����ɂ���ĕ���������900�~�͈�Ô�Ƃ��ė×{���ɔ[�߂�A�Ƃ������́j���s�����B����ɑ��A���������R���m���ɕs���\�����Ă��s�Ȃ������p������A�����Ō�����b�ɕs���\���Ă��s�Ȃ����A������b��������p���������Ƃ���A�������s���s���R���@�ɂ��i�ׂ��N����ɋy���̂ł���B
�����̎咣�́A�����́u�����ی�@�ɂ��ی�̊�v�ɂ��x������Ⴗ����Ǝ������A���{�����@��25���A�����ی�@�ɋK�肷��u���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�ތ����v��ۏႷ�鐅���ɂ͋y�Ȃ����Ƃ���A���{�����@�ᔽ�ɂ�����Ǝ咣�����B
�@���R�̓����n���ٔ����́A���p�i��z��600�~�ɗ}���Ă���͈̂�@�ł���Ƃ��A�ٌ������������i�����̑S�ʏ��i�j
�@���R�̓��������ٔ����́A���p�i�600�~�͂����Ԃ�Ⴂ���A�s���z��70�~�ɉ߂������@��25���ᔽ�̈�ɂ͒B���Ȃ��Ƃ��āA�����̐��������p�����B
�@�㍐�R�̓r���Ō��������S���i1964�N2��14���Ɏ����j�A�{�q�v�Ȃ��i�ׂ𑱂������A�ō��ٔ����́A�ی���錠���͑����ł��Ȃ��Ƃ��A�{�l�̎��S�ɂ��i�ׂ͏I�������Ƃ̔������������B
�@�ō��ٔ����́A�u�Ȃ��A�O�̂��߁v�Ƃ��Đ����}����̓K�ۂɊւ���ӌ����q�ׂĂ���B����ɂ��ƁA�u���@25��1���͂��ׂĂ̍��������N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�ݓ���悤�ɍ������^�c���ׂ����Ƃ����̐Ӗ��Ƃ��Đ錾�����ɂƂǂ܂�A���ڌX�̍����ɋ�̓I�����^�������̂ł͂Ȃ��v�Ƃ��A�����̌����͖@���i�����ی�@�j�ɂ���Ď����Ηǂ��Ƃ����B�u�������N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐����ł��邩�̔F�蔻�f�́A������b�̍��ړI�ȍٗʂɈς���āv����A�Ƃ���B
�ٗʍs���Ƃ́A�s���s�ׂ̂����C�v���܂��͓��e�ɂ��Ė@������`�I�ɖ��m�ȊT�O�Œ�߂Ă��Ȃ����C�܂�������߂Ă��Ȃ��ꍇ�C�܂��͓��Y�s���s�ׂ��s�����Ƃ��u�ł���v�ƒ�߂Ă���ꍇ�ɁC�s�����̍ٗʂɊ�Â��ĂȂ����s�ׂ̂��Ƃ��B
�@�����čō��ق͂����ŁA�v���O�����K������N�����B�v���O�����K����Ƃ́A���@�̓���̐l���K��Ɋւ��āA�`���I�ɐl���Ƃ��Ė@���ɂ����Ă͋K�肳��Ă��Ă��A�����I�ɂ͍��̓w�͖ڕW����I���j���K�肵���ɂƂǂ܂�A���ڌX�̍����ɑ��ċ�̓I�����^�������̂ł͂Ȃ��Ƃ���l�������B
�@�͂����Ă����̔����͐l���d���Ă���̂��A�Љ�͕ۏ���Ă���̂��B���͂��̔������������ۏ͂���Ă��Ȃ��Ǝv���B�v���O�����K������ٗʍs����p���č��͐������ɂ��ĞB���Ȍ��������Ă���̂ł͂Ȃ��̂��B���@�̓���̐l���K��Ɋւ��āA�`���I�ɐl���Ƃ��Ė@���ɂ����Ă͋K�肳��Ă��Ă��A�����I�ɂ͍��̓w�͖ڕW����I���j���K�肵���ɂƂǂ܂�A���ڌX�̍����ɑ��ċ�̓I�����^�������̂ł͂Ȃ��Ƃ����B�w�͂������Ă�����̂��B�w�͂��Ă��l�̖����~���Ȃ���ΈӖ����Ȃ��Ǝ��͎v���B
�Q�E�l���Ɋւ���@�����
�@���ɁA������܂��傫�Ȗ��ƂȂ����l����肾�B������G�z�o�̏ؐl�Ƃ������@�����ւ�����l����肾�B���R���̒����M���̎��R������B���������Ȃ�������Ȃ��P�̌������B�ł́A���̖��ƂȂ����G�z�o�̏ؐl�Ɋւ���A�����������Ă������B
�@�G�z�o�̏ؐl�̐M�҂ł���X�́A�@����̐M�O����A�������ۂ���Ƃ����ł��ӎv��L���Ă����B�����̊̑����ǎ�Ƃ̐f�f����X�́A�P�X�X�Q�N�W���A���A����p�̎��т̂��铌����w��Ȋw�����������a�@�ɓ��@���A��tA�ɗA�����ۂ̈ӎv��`�����B��Ȍ��́A�u�G�z�o�̏ؐl�v�̐M�҂̗A�����ۂ̈ӎv�d���A�ł������A�����Ȃ����A�A���ȊO�ɂ͋~����i���Ȃ����ԂɎ������Ƃ��́A���ҋy�т��̉Ƒ��̑��ۂɂ�����炸�A��������j���̂��Ă������AA����X�̎��Ë��ۂ����O���Ė{�����j��X�ɐ������Ȃ������BA���͓��N�X���A�A�����K�v�Ȏ��Ԃ�������\�������邱�Ƃ�F�������̏������������X�Ɏ�p���{�s���A�A�����Ȃ�����X���~�����Ƃ��ł��Ȃ��\���������Ɣ��f���ėA���������B��p��ɗA���̎�����m����X�́A����A���ɑ��đ��Q�����𐿋������B
�@�ٔ����̌����́A�@���҂��A�A�����邱�Ƃ͎��Ȃ̏@����̐M�O�ɔ�����Ƃ��āA�A������Ís�ׂ����ۂ���Ƃ̖��m�Ȉӎv��L���Ă���ꍇ�A���̂悤�Ȉӎv��������錠���́A�l�i���̈���e�Ƃ��đ��d�����B�AX���@����̐M�O����A�����ۂ̌ł��ӎv��L���Ă���A���A����p�����҂��ē��@�������Ƃ�A�����m���Ă����{���ł́AA����X�ɑ��{�����j��������āAA���̎�p���邩�ۂ���X���g�̈ӎv����Ɉς˂�ׂ��������BA���́A�E������ӂ������Ƃɂ��A�����\���̂������{����p���邩�ۂ��ɂ��Ĉӎv��������錠����D�����_�ŁAX�̐l�i����N�Q�����B�Ƃ��������������Ă���B
�@���̍ٔ��̔����ł͌����������i�����B
�@�@�����������G�z�o�̏ؐl�Ƃ͂����������Ȃ̂��B�G�z�o�̏ؐl�́A�@���c�̂̂��Ƃ��B�A�����J�ɖ{���̂���L���X�g���n�̏@���c�̂ŁA�����ɋL����Ă��邱�Ƃ��ʂ�Ɏ��H���邱�Ƃ�����Ă���B���̋����̒��ɂ́A�i���_�̔ے�A�R���ւ̓������ہA�\�͂�i���Z�̔ے�Ƃ��������Ƃ̑��Ɂu�A���̋֎~�v������B�����̒��ɗA����������s�ׂƂ��Ĕᔻ����L�q�����邽�߁A�A�������Ȃ����Ƃ́A�G�z�o�̏ؐl�̐M�҂����˂Ȃ�Ȃ����܂�̈�ɂȂ��Ă���B
�@�G�z�o�̏ؐl�A�������ł́A���Ȍ��茠������̂ɂ�������炸��t�̌����p�^�[�i���Y���i��������ɂ���҂��ア����̎҂̈ӎu�ɔ����āA�ア����̎҂̗��v�ɂȂ�Ƃ������R����A���̍s���ɉ��������A�������肷�邱�Ɓj�ɂ���Ė{�l�̈ӎv�ɔ����čs�����N�������B���̎��_�ŁA���Ȍ��茠�͐N�Q����Ă���Ǝv���B�܂��A�A���ɂ��Ă̐�������t�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ����ł͂Ȃ��̂��Ǝv���B���̍ٔ��ŁA��Ì���ł����Ȍ��茠�����d�����ׂ��Ƃ����l���𐢂̒��ɍL�߂��̂ł͂Ȃ��̂��B
�R�E�i�@���̌��E
�@�ٔ��͂ǂ�Ȗ��ł��ق���Ƃ͌���Ȃ��B�ٔ��ɂ����E�A�i�@���̌��E������B���̒��̂P�������s���Ƃ������̂�����B�����s���Ƃ́A���x�Ȑ������������߁A�i�@���ɂ��R���̑Ώۂ��珜�O���ׂ����̂Ƃ���鍑�ƍs�ׂ̂��Ƃł���B�ł́A�Ȃ��ٔ����͍��x�Ȑ�������тт����ƍs�ׂɂ��Ďi�@���f�����Ȃ��̂��B�ЂƂ́A�����������Ƃ��ٔ����͔��f����ƁA���ʔ@���ł͑傫�ȍ��������������ꂠ��Ƃ��闝�R����ł���B������u�������v�Ƃ����B���Ƃ̊�{�I�Ȏ����́A�����܂Ŗ����`�@�ւ̌X���������������t�̔��f�Ɉς˂�ׂ��A�ٔ����͉�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�u���x�Ȑ�������тт����ƍs�ׁv�ɁA�i�@���͓���܂Ȃ��Ƃ��āA�����͖����`�̌���Ɉς˂�ׂ��Ƃ����̂́A�����I�ȍl�����B
�@�����A�������_��ς��Ă݂�ƍٔ����͓����Ă���̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ����������ł���B����́A�s���Ɏi�@�����k�������Ă��Ȃ����A����Ȃ�Ől���~�ςȂ�đS���ł���̂��Ƃ����������o�Ă���B���������������s���Ŗ��ɂȂ�������������B���쎖�����B
�@���쎖���Ƃ́A�P�X�T�V�N�V���W���ɓ��ʒ��B���������B�ǂ��������ʂ������ۂɁA��n�g���ɔ�����f�����̈ꕔ���A�A�����J�R��n�̗�������֎~�̋��E����A��n���ɐ�m�����������Ƃ��āA�f�����̂���7�������{���ƃA�����J���O���Ƃ̊Ԃ̑����͋y�ш��S�ۏ����Z���Ɋ�Â��{�y�ы����тɓ��{���ɂ����鍇�O���R���̒n�ʂɊւ��鋦��̎��{�ɔ����Y�����ʖ@�ᔽ�ŋN�i���ꂽ�������w���B
�@�ō��ق̔����́A�u���@��9���͓��{���匠���Ƃ��Ď��ŗL�̎��q����ے肵�Ă��炸�A�������֎~�����͂Ƃ͓��{�����w���E�Ǘ��ł����͂̂��Ƃł��邩��A�O���̌R���͐�͂ɂ�����Ȃ��B���������āA�A�����J�R�̒����͌��@�y�ёO���̎�|�ɔ����Ȃ��B�����ŁA���Ĉ��S�ۏ���̂悤�ɍ��x�Ȑ������������ɂ��ẮA�ꌩ���Ă���߂Ė����Ɉጛ�����ƔF�߂��Ȃ�����A���̓��e�ɂ��Ĉጛ���ǂ����̖@�I���f���������Ƃ͂ł��Ȃ��v�i�����s���_�̗p�j�Ƃ��Č�������j�����n�قɍ����߂����B
�@���x�̐����Ɋւ��邱�Ƃ͍ٔ����͍ق��Ȃ��B�܂�A�ٔ����̌����ł͂ǂ��ɂ��ł��Ȃ����Ȃ̂ł���B�O�������Ƃ��ւ��̂���b���B���@�{�ɂ����闧�@�ɂ��@�Đ����ɍٔ����ً͈c�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�܂��A�x�@�\�����ጛ�i�ׂƂ������ٔ��ł������悤�Ȍ������ł���B�ٔ����́A��̓I�ȑi�ׂ���N����Ȃ��̂Ɍ��@�y�т��̑��̖@�����ɔ��f�����������͂Ȃ��Ƃ����B
�@���ɂ��ٔ������ق��Ȃ���肪����B����́A�����Љ�_���B�����Љ�_�Ƃ́A���{�̎i�@�ɂ����āA�c�̓����̋K�����ɂ��Ă͎i�@�R�����y�Ȃ��A�Ƃ���@���̂��Ƃ��B
�x�R��w�����͂����Ⴞ�B�x�R��w�̊w�������C���Ă����Ȗڂ̒P�ʏC����F�߂��Ȃ��������ƂŒP�ʕs�F�蓙�̈�@�m�F�����߂��s���i�ׁB�����́A�㍐���p�B�u��w�́A�������ł���Ǝ����ł���Ƃ��킸�A�w���̋���Ɗw�p�̌����Ƃ�ړI�Ƃ��鋳�猤���{�݂ł����āA��ʎs���Љ�Ƃ͈قȂ����ȕ����Љ���`�����Ă���̂ł��邩��A���̂悤�ȓ���ȕ����Љ�ł����w�ɂ�����@����̌W���̂��ׂĂ����R�ɍٔ����̎i�@�R���̑ΏۂɂȂ���̂ł͂Ȃ��B�v�Ƃ����B�܂肱�̖��A�����Љ�ɂ��Ă͍ٔ����͌��o���ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B
�S�E�܂Ƃ�
�@�ٔ����́A���@�A�@���A���A�����s�ׁA�����Љ�_�ɂ��Ă͍ق��Ȃ��B�ٔ����̌������y�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ猛�@�A�@���A���͍������t�ŏ��F����Ăł������̂ł���B����Ɍ����o���ƎO�������Ɉᔽ���Ă��܂��B
�@�܂��A�����i���ł́A�ٗʍs���A�v���O�����K������g���B���Ȍ��������ٔ����͔��f�ł��Ȃ��Ƃ����B�͂����Ă���Ől���͑��d��������̂��B�ٔ����ɂ��ǂ����悤���ł��Ȃ���肪����̂��Ɗ������B�G�z�o�̏ؐl�A�������ł��M���̎��R�����Ȍ��茠��������B���Ȍ��茠���p�^�[�i���Y���Ɋւ�����͑����̂ł͂Ȃ����B�Ⴆ�Ύq�{�N�`���̐ڎ�ɂ��Ă��������Ȍ��茠���p�^�[�i���Y���Ƃ̊W�ł͂Ȃ��̂��Ǝ��͎v���B��������̌����Ȃ�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A�����̈ӎv�d���Ă��ꂩ���̐l�������ł��������B
�o�T�E�Q�l����
�����s��
http://www.weblio.jp/content/%E7%B5%B1%E6%B2%BB%E8%A1%8C%E7%82%BA
���쎖��
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%82%E5%B7%9D%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://kenpou-jp.norio-de.com/sunagawa-jiken/
�����Љ�_
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%A8%E5%88%86%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%AB%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E4%BA%8B%E4%BB%B6
�ٗʍs��
https://kotobank.jp/word/%E8%A3%81%E9%87%8F%E8%A1%8C%E7%82%BA-68309
�G�z�o�̏ؐl
�V�E����n���h�u�b�N�u���@�v
�����i��
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E8%A8%B4%E8%A8%9F
�v���O�����K���
�p�^�[�i���Y��
https://www.kango-roo.com/word/14115
·
�d�q�o�Ŗڎw���Ȃ�!?�E�҃T���h�{�b�N�X
·
�ŒZ5���ł��Ȃ��̃T�C�g�ɍL���z�M�y�E��AdMax�z
·