���쐳�K
�Z�̃A�h���X���瑗�M�����Ă��������Ă܂��B
���́A���d���Ɏ^���ł��B�܂��A���d�߂͓��{�̌Y�@�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����̂��Ǝ��͍l���܂��B���̗��R�́@�@����܂��B
1���̈�Ƃ��āA�g�D�ƍߏ����@�i�g�D�I�Ȕƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@���j�̈ꕔ����������܂��B
��Z���̓�@���̊e���Ɍf����߂ɓ�����s�ׂŁA�e�����Y���W�c���̑��̑g�D�I�ƍߏW�c�i�c�̂̂����A���̌����W�̊�b�Ƃ��Ă̋����̖ړI���ʕ\��O�Ɍf����߂����s���邱�Ƃɂ�����̂������B�����ɂ����ē����B�j�̒c�̂̊����Ƃ��āA���Y�s�ׂ����s���邽�߂̑g�D�ɂ��s������̂̐��s���l�ȏ�Ōv�悵���҂́A���̌v��������҂̂����ꂩ�ɂ�肻�̌v��Ɋ�Â��������͕��i�̎�z�A�W�ꏊ�̉������̑��̌v��������ƍ߂����s���邽�߂̏����s�ׂ��s��ꂽ�Ƃ��́A���Y�e���ɒ�߂�Y�ɏ�����B�������A���s�ɒ��肷��O�Ɏ����҂́A���̌Y�����y���A���͖Ə�����B
�@�@��@�ʕ\��l�Ɍf����߂̂����A���Y���͖����Ⴕ���͒����\�N���钦���Ⴕ���͋����̌Y����߂��Ă�����́@�ܔN�ȉ��̒��͋���
�@�@��@�ʕ\��l�Ɍf����߂̂����A�����l�N�ȏ�\�N�ȉ��̒��͋����̌Y����߂��Ă�����́@��N�ȉ��̒��͋���
�@�Q�@�O���e���Ɍf����߂ɓ�����s�ׂŁA�e�����Y���W�c���̑��̑g�D�I�ƍߏW�c�ɕs�����v�����A���̓e�����Y���W�c���̑��̑g�D�I�ƍߏW�c�̕s�����v���ێ����A�Ⴕ���͊g�傷��ړI�ōs������̂̐��s���l�ȏ�Ōv�悵���҂��A���̌v��������҂̂����ꂩ�ɂ�肻�̌v��Ɋ�Â��������͕��i�̎�z�A�W�ꏊ�̉������̑��̌v��������ƍ߂����s���邽�߂̏����s�ׂ��s��ꂽ�Ƃ��́A�����Ɠ��l�Ƃ���B
�@�@�掵���̎��Ɏ��̈����������B�i�Q�l�����@�@�O�c�@�z�[���y�[�W�j
���������ƍ߂Ƃ́A�Y�@�ɂ����ẮC
- �\���v���ɊY������
- ��@
- �L��
�@�ȍs�ׂł���Ƃ����B
�@����s�ׂ��ƍ߂Ƃ���邽�߂ɂ́C���̂R�̗v�����[�������K�v������B�ihanzairionshou.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_acfb.html�j
�@���̑g�D�ƍߏ����@�i�g�D�I�Ȕƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@���j�̂U���Q�ł̌v��Ƃ��邪�A���͂��̌v�悪�ǂ̒i�K�Ōv��ƌĂׂ�̂����^��Ɏv���܂����B�ɒ[�Ɍ����A�v��ɂ͈��͘b���������ł�����̐����Ȃ��ꍇ�ł��ߕ߂ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��l������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A��ϓI��@�v�f�̏ꍇ�����邽�߁A�v�悪�ǂ̒i�K�̂��Ƃ��w�������^��Ɏv���܂��B���{�́u�g�D�I�ƍߏW�c�v���Ώۂň�ʂ̐l�͑ΏۊO�Ƃ��Ă��邪�A�ǂ�������`�ň�ʐl�ƌĂׂ�̂����^��Ɏv���܂��B�@���̂悤�ȉ����ɂ��A���܂ł͕߂܂����Ȃ������\���i���s�s�ׂ̒���̑O�i�K�j�̎��_���O�̋��d�̒i�K�őߕߏo����悤�ɂȂ�܂����B���܂ł́A�\���̏����K�肪����̂͂����ꕔ�̋ɂ߂ďd��Ȕƍ߂����ł����B���Ȃ킿�A�����\���߁A�O���\���߁A����\���߁A���Η\���߁A�ʉU�������߁A�E�l�\���߁A�g����ړI���擙�\���߁A�����\���߂�8��ނ�����܂��B�܂��A���͔ƍ߂̍\���v����A���Q�̔������邱�Ƃ�v�����A�@�v���N�Q�����댯�܂��͋��Ђ�������ΐ�������Ƃ����ƍ߁B�i�댯���j
�@�����͂�����������Ȕƍ߂ł���ƂƂ��ɁA�v�������Ă����Ɏ��s�Ƃ������͏����s�ׂ�����ꍇ�������ƍl�����Ă��܂��B������������ƂȂ�Ζ@�v�N�Q���ɂ߂ďd���A�댯�ȍs�ׂȂ̂ŁA���s�̒���Ɏ���Ȃ��\���i�K�ł��Ɨ����ď������ׂ����R������ƍl���Ă���̂ł��B���̂����ꕔ�̋����Ȕƍ߂����ɁA�K������Ă����\���߁i�ƍ߂̎�����ړI�Ƃ��鏀���s�ׂ̂��ƂŁA�d�c�̕��@�ɂ����̂��������T�O�̂��Ɓj����������O�̋��d�̒i�K�őߕ߂ł��邱�Ƃ́A�ƂĂ��ǂ����Ƃ��Ǝv���܂����A���̂����ꕔ�̋����ƍ߈ȊO�̔ƍ߂����d�̎��_�ŕ߂܂����邱�Ƃ��Љ�I�Ɍ��Ă��ǂ����Ƃ��Ǝ��͍l���܂��B�܂��A�댯���Ȃǂ��A��قǂ��G�ꂽ�ʂ�A�@�v���N�Q�����댯�܂��͋��Ђ������邽�߁A���R�ɖh���đߕ߂ł���̂ŗǂ��Ǝv���܂��B
2�܂����Ƃ̏ꍇ�A�����v���Ƃ��āA1���s�ׁE2���̈ӎv�@�m�炸�ɖ𗧂����Ƃ����ꍇ�͐������܂���B
�@��G�R���r�j���i�C�t��̔�������C�w���҂������p���ď��Q�s�ׂ��s����
3�@���Ǝ҂̎��s�s��
�@�菕������Ӑ}�Ŏ菕�����s���Ă��C���Ƃ����s���Ȃ��ꍇ�����Ƃ͐������܂���B
4�@���̈��ʊW
�@�菕�������Ƃ̎��s�ɖ𗧂������e�Ղɂ����ꍇ�łȂ������Ƃ͐������܂���B
�i�݂��ٖ@���������z�[���y�[�W���j
3�̎�����A���܂ŕ߂܂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃ��A���ԂƋ��d�������ƂŁA�ߕ߂��ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
3�������A�������Ƃɂ����Ă͂��܂�ς���Ă��Ȃ��Ǝ��͎v���܂��B�������Ƃ́u���ׂĐ��ƂƂ���v�i�U�O���j�ƒ�߂��Ă���悤�ɁA���Ƃł���ƂƂ��ɐ��Ƃł��B�܂�A�P�ƔƂƂ͈قȂ��Ď���͎��s�s�ׂ̈ꕔ�������S���Ȃ��̂ł����A����ł��ӔC�͍s�ׂ̑S���ɐ�����Ƃ����_�����F�ł��i�ꕔ�s�ׂ̑S���ӔC�j���ƂƂ��Ĉӎv�𑊒ʂ���Ƃ������Ƃ́A�ƍ߂̎��s�Ɍ����Ă���Έ�S���̂ɂȂ����̂ł�����i�����ӎv��̐��j�A����A�E�Q����}���ĂƂ��ɔ��C�����ꍇ�AX�̒e����������Y�̒e���O��Ă��AY�͋������ƂƂ���A�E�Q�̐ӔC���̂ł��B���d���������ł́u�Q�l�ȏ㋤�����Ĕƍ߂����s�v��f���ɓǂ߂A���Ǝ҂��ꂼ�ꂪ���炩�̎��s�s�ׂS���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɖ�����܂��BX�EY������A���ŋ��������AX��A���Č�����A���̊Ԃ�Y��A���F���č��Y��D�����Ȃǂ͓T�^�ł���A����͎��s�s�����Ƃł��B�������Ȃ���A����͌Â�����A���s�͈ꕔ�̎҂ɂ��̂ő����Ƃ��āA���s�ɉ���炸���O�d�c�ɉ�����������̎҂ɂ��Ă����d���������Ƃ��ċ������ƂƂȂ邱�Ƃ�F�߂Ă��܂��B���̈����͎����Ŋm�����Ă���A���d�́A�ʖd��d�c�Ɍ��炸�A�u�ӎv�̘A���v�ő����Ƃ���Ă��܂��B���d�������Ƃ�F�߂闝�_�\���͋����ӎv��̐�������\�����A�܂��Ԑڐ����I�\�����\�ł��B��҂́A���d�ɎQ�������������F�߂���ȏ�A���ڎ��s�s�ׂɊ֗^���Ȃ����̂ł��A���l�̍s�ׂ�����Ύ��Ȃ̎�i�Ƃ��Ĕƍ߂��s�����Ƃ����Ӗ��ɂ����āA���̊Ԃ̌Y�ӂɍ��ق͂Ȃ��Ƃ�����̂ŁA�����ȗ��n���������ō̂��܂����B���d�͈ꓯ����Ă���K�v�͂Ȃ��A�������d�ő����Ɣ��f����Ă��܂��B���d����������F�߂�K�v���̗��R�́A�ォ����Ă���A�Ƃ������t������܂����A�܂��ɂ���قǓT�^��������܂���B�v����ɁA���d����������F�߂Ȃ���Β������s�s����������P�[�X������̂ł��B�������ǂ�قǕs�s�����Ƃ��Ă��A�ߌY�@���`�͗ސ����߂������Ȃ����A���߂ɂ����x������܂����A�@���̉������Ȃ���ΓK�p���F�߂��Ȃ��قǂ̖����ȉ��߂Ƃ������܂���B�Ȃ��K�v���A���������ɒ[�ł����A�\�͒c�R���̃P�[�X�ōl�������ɁA�^�\�͒c�̑g���������R�����̑�����\�͒c�ɉ��荞�݂������đ����̎����҂��o�����Ăɂ����āA���������͎̂��s�s�ׂ��s�����҂����ł����H�ƌ����A�w��ɂ���g����g�D�g�b�v�������ł��Ȃ�����������Ǝv���͂��ł��B�i�x�@���̂��߂̂킩��₷���Y�@�@���X�ؒm�q���j�@���́A���Ȃ��Ƃ����̂悤�Ɏv���܂����B�܂��A���d���������͈ȑO����F�߂��Ă��邽�߁A���d�����{�s���ꂽ����Ƃ����Ă��܂�ς��Ȃ��悤�Ɏv���܂����B
4�Ԑڐ����ɂ����ẮA�Y�@�ɋK�肳��Ă���ƍ߂̗ތ^�͌����Ƃ��āA�P�Ƃ̍s�҂ɂ�������\�肵�����̂ƂȂ��Ă��܂��B������u���ڒP�Ɛ��Ɓv�Ƃ����܂����A���̐l�Ԃ𗘗p���čs�ׂ��s�������̂ł��A�u�P�Ɛ��Ɓv�ƕ]����������̂�����܂��B�܂�A�����������Ă��Ȃ��҂ł��A������A���̎҂��ƍ߂̒��{�l�Ƃ����ꍇ�ł��B���̂悤�ȏꍇ���Ԑڐ����Ƃ����܂����A�Ԑڐ����̒�`�͐F�X�ȍl����������܂��B���l�̍s�ׂ��x�z���鎖�ɂ��A�\���v���������������ꍇ���Ԑڐ����Ƃ���v�Ƃ����s�x�z�����x�z�I�����ƂȂ��Ă��܂��B�i�u�}��҂������I���Ȍ�����s���Ă��Ȃ����ɔw��҂��Ԑڐ����Ƃ���v
�Ƃ����������L�͂ł��B�j�܂�A���ڎ����������Ȃ��Ă������m��Ȃ���O�҂��u����Ƃ��āv���p���A�ƍ߂����������҂��u�Ԑڐ����v�ƌ����܂��B�܂��A����ł́A�\�͂�_�I�����ɂ���Ĕ�Q�҂�}�����A���E�������ꍇ�́A��Q�҂𗘗p�����E�l���Ԑڐ����ƂȂ�܂��B���_�x�؎ҁi�m�I��Q�ҁj�ɑh������\��������ƌ�M�����Ď��E������s�ׂ͔�Q�҂𗘗p�����Ԑڐ����ƂȂ�܂��B�X�֔z�B�l�ɓŖ��z�B������s�ׂ͎E�l���Ԑڐ����ƂȂ�܂��B�i�����b�N�X�@�w���j�����Ŏv�������Ƃ́A���d�߂ŕ߂܂����ꍇ�A�ꏏ�ɊԐڐ��Ƃł��ߕ߂ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̏ꍇ�A�Y�������Əd���Ȃ�̂ł́A�Ȃ�̂����C�ɂȂ�܂����B
5�t�ɂ��܂�ς��Ȃ��Ǝv�������́A�@�@��S���@�������Q�̓���i�Q�O�V���j
�@�@�i�������Q�̓���j
�@�Q�O�V�� �Q�l�ȏ�Ŗ\�s�������Đl�����Q�����ꍇ�ɂ����āC���ꂼ��̖\�s�ɂ�鏝�Q�̌y�d��m�邱�Ƃ��ł����C���͂��̏��Q���������҂�m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����������Ď��s�����҂łȂ��Ă��C���Ƃ̗�ɂ��
�{����
�u�Q�l�ȏ�Ŗ\�s�������Đl�����Q�����ꍇ�v�ɂ�����
�P�u���ꂼ��̖\�s�ɂ�鏝�Q�̌y�d��m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��v
�@�@�܂���
�Q�u���̏��Q���������҂�m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��v�́C
�������Ď��s�����҂łȂ��Ă��C���Ƃ̗�ɂ��i���������ƂƂ��ď��f����j
�Ƃ���������K�肵�����̂ł��B
�Y�@�́A�u�߂�Ƃ��ӎv�v���Ȃ킿�̈ӂɂ��s�ׂ���������̂������Ƃ��Ă���A�߂�Ƃ��ӎv�̂Ȃ��ꍇ�́A�@�����ߎ�����������u���ʂ̋K��v�̂���ꍇ�Ɍ����O�I�ɏ������ꂤ��ɂƂǂ܂�B�i:
http://www.bengo4.com�j�ߎ��Ƃ̊e�\���v�������Ă��A�ߎ��ɂ��A���邢�͒��ӂ�ӂ�A���̌��ʂ��������Ƃ��邾���ŁA��̓I�ɂǂ̂悤�ȕs���ӂ��w���̂��͏����Ă��܂���B�s�ׂƂ��Ă̓T�^���Ȃ��A�ʂɔ��f�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
6���d�߁i�g�D�I�Ȕƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@���j���������������ɂ����āA�u���d�߂͎����ێ��@���v�Ƃ������Έӌ����o�Ă��邪�����ێ��@�Ƃ́A�P�X�Q�T�N�A���{�Ő��肳�ꂽ�u���̌쎝�v�̂��ߎЉ��`�Ȃǔ����Ɛ����^�������̂��߂̖@�B�P�X�Q�W�N�A�ō��Y�Ɏ��Y���������A�R����`�����Ɋ��p���ꂽ�B�P�X�S�T�N�A���{�̔s�k�Ƌ��ɔp�~���ꂽ�B
�吳�f���N���V�[���i�W�������ʁA�P�X�Q�T�i�吳�P�S�j�N�A�����������t�����ʑI���@�i���{�j�������������A����Ɠ����������ێ��@�����肳�ꂽ�B���́i�V�c���j�̕ϊv��A���L���Y���̔ے��ړI�Ƃ������ЂƂ��̉^�����֎~���邱�Ƃ�@���Ƃ��ĉ\�Ƃ����B��̓I�ɂ́A�͂��߂͋��Y�}�i�P�X�Q�Q�N�����j�Ȃǂ̎Љ�v�����߂����^���������܂���̂ł��������A����ɐ��{�̐����ᔻ���鎩�R�Ȕ����������܂�̑ΏۂƂȂ�A�����Ȏ��R��`�҂�J���^���Ȃǂ������܂�̑ΏۂƂȂ��Ă������B�܂��P�X�Q�W�N�̓c���`����t�́A���߂ōō��Y�Ɏ��Y�������A�R���ɑ��锽�Ή^���┽�튈�����������e�������i�Ƃ��ꂽ�B���{�̓V�c���R����`�̐����x���闧�@�ł������̂ŁA�P�X�S�T�N�A���{�̔s�k�ƂƂ��ɓP�p���ꂽ�B�iwww.y-history.net/appendix/wh1503-017.html�j
�ȏ�̂��Ƃ���A���́A�g�D�ƍߏ����@�i���d���j�������ێ��@�Ƃ͑S���Ⴄ���̂��ƍl���Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A���͓V�c���ł͂Ȃ������`���Ƃɂ����Ă��肦�Ȃ��Ǝv������ł��B
�Ō�ɁA���d�����������鎖��2020�N�ɍs����I�����s�b�N�����S�ɊJ�Âł���Ǝ��́A�l���炦�܂��B���d�������邱�Ƃɂ���ăe�����X�g�W�c��g�D�I�ƍߏW�c���v��̒i�K�őߕ߂ł��邱�Ƃ́A�N�����Ȃ��ɉ����ł��邵�A�C�O����ƍ߃O���[�v�̏�ǂ�ǂ�����Ă��邱�Ƃɂ���Ă����ƕ��a�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�i�Q�l�����@�@�x�@���̂��߂̌Y�@�j
���� ��
16�i118001�@�����@��
�L�[���[�h�@���d�߁A�g�D�I�Ȕƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@���A�����ێ��@�A�댯�ƁA�Ԑڐ��ƁA�\���A�A���d�������ƁA�����ƁA�ߎ�
���_�@�������d����s�\���ł���ƍl����B
�P�@�V���P�P���Ɏ{�H���ꂽ�g�D�I�Ȕƍߋy�єƍߎ��v�̋K���Ɋւ���@���̉���������U���̂Q���́A���̊e���Ɍf����߂ɓ�����s�ׂŁA�e�����Y���W�c���̑��̑g�D�I�ƍߏW�c�i�c�̂̂����A���̌����W�̊�b�Ƃ��Ă̋����̖ړI���ʕ\��O�Ɍf����߂����s���邱�Ƃɂ�����̂������B�����ɂ����ē����B�j�̒c�̂̊����Ƃ��āA���Y�s�ׂ����s���邽�߂̑g�D�ɂ��s������̂̐��s���l�ȏ�Ōv�悵���҂́A���̌v��������҂̂����ꂩ�ɂ�肻�̌v��Ɋ�Â��������͕��i�̎�z�A�W�ꏊ�̉������̑��̌v��������ƍ߂����s���邽�߂̏����s�ׂ��s��ꂽ�Ƃ��́A���Y�e���ɒ�߂�Y�ɏ�����Ƃ��Ă���B
���������d���ł́A�ƍ߂̋����s�ׂ��l�̔ƍ߂̎��s�s�ׂ������������ɏW�c�ɑ����Ă����ꍇ���̏W�c�S�����������邱�Ƃ��\�ɂȂ�B��������d���������Ƃ���l��������B�����ł͔ƍ߂̎��s�s�ׂɂ͎����߂Ȃ��Ă����d���Ă���̂őS���𐳔ƂƂ��A�ӔC��S���ɘA�т�����B���Ə]�����̋ɒ[�]�������ł́A�\���v���ɊY������@�ŗL�ӂł��邱�Ƃ̂��ׂĂ�v���̊Y���ɓ���Ă��邽�ߋ��ƂƂ���̂͌������B�ʐ��́A�\���v���ɊY�������@�ȍs�ׂłȂ���Ȃ�Ȃ����A�L�ӂł��鐧���]�������Ƃ��Ă���B���d���������̔���Ƃ��ėL���ȗ��n����������B��l�ȏ�̎҂�����̔ƍ߂��s�����߂ɋ����ӎv�̉��Ɉ�̂ƂȂ��Ă��݂��ɑ��l�̍s�ׂ𗘗p���A�e���̈ӎv�����s�Ɉڂ����Ƃ���e�Ƃ���d�c���Ȃ��A����Ĕƍ߂����s�����������F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���d�ɎQ�������������F�߂���ȏ�A���ڎ��s�s�ׂɊ֗^���Ȃ��҂ł��A���l�̍s�ׂ�����Ύ��Ȃ̎�i�Ƃ��Ĕƍ߂��s�����Ƃ����Ӗ��ɂ����āA���̌Y�ӂ̐����ɍ��ق���ׂ��Ɖ����ׂ����R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B(��1)�Ɣ���͂��Ă���B�����ӎv���ł̋��d�́A���̖d�c�ɎQ�������S�����������邱�Ƃ͐��`�ł���ƁA�l���邪���s�s�ׂ��s���Ă��Ȃ��҂ɂ܂Ő��ƂƂ��邱�Ƃ́A���s�s�ׂ��s���Ă��Ȃ��҂��炵�Ă͂ƂĂ��[���ł��邱�Ƃł͂Ȃ��ƍl����B���l�̍s�ׂ�����Ύ��Ȃ̎�i�̂悤�ɂƔ��f���Ă���̂́A�Ԑڐ����Ǝ��Ă���B�Ԑڐ����͂��̔ƍߍs�ׂ̂��߂Ɏ����̎�͉������ɑ��l��ƍ߂̓���Ƃ��Ĕƍ߂��s���ƁA���̎w�������Ă����҂��Ԑڐ����Ƃ��ď������邱�Ƃ��\�ł���B
�Q�@����E�\���s�ׂɂ���
�@����ɂ��Ă킩��₷������݂��l����B�`���̂��ŐQ�Ă��肻�̖̔��Α��ɂ`�̃J�o�����u���Ă���B�����ցA�a�Ƃb������Ă��Ăb���a�ɂ����̂����ăJ�o�����Ƃ��Ă���悤�ɓ`�����B�b�͂Ƃ��Ă����J�o���������ꂷ�����ł���A�a�͖Y�ꕨ���Ǝv���Ă���B���̂悤�ȏꍇ�A�J�o���͖����`�̐�L�͗���Ă��Ȃ��ƍl����B���̂��߁A�Y�ꕨ�ł���Ǝv���Ă���a�͈⎸�����̍߂̌̈ӂŃJ�o�����Ƃ��Ă��邪�ޓ��̌��ʂ��������Ă���B�����ɁA�a�͌̈ӂƌ��ʂ̍��낪�o�Ă��Ă��܂��Ă���B���ۓI�����̍��납��ޓ��ƈ⎸�����̂̓���\���v���̓o���o���ł���B����͂��̓���d�Ȃ荇�������ł����ق��Ȃ��Ƃ��Ă��邽�߁A�d�Ȃ荇���Ƃ���́u���𓐂ށv�Ƃ������Ƃ�����A�a�̍s�ׂ͈⎸�����̂̌̈ӂ܂ŔF�߈⎸�����̂ŏ�������Ƃ��Ă���B�b�͌��X�ޓ��̌̈ӂ͂��������ߐޓ��̋����Ƃ��ď�������B����̂��������d���ɂ��Ă����d���������s�s�ׂ̒i�K�ō��낪�������ꍇ�ɂǂ̂悤�ɏ������Ă����̂��낤���B�������d���ł̍��낪�������ꍇ�A���d�҂̍���F�����������s��Ȃ���Ιl�߂ɋ߂����Ƃ��N�����Ă��܂���������Ȃ��B
�@�\���s�ׂɂ��Ă�����݂��l����B�v�w�ł���`�a�����a�q���b�ƕs�ς̊W�ɂ������B�a�q�͂b���g���Ă`�̎E�l���v�悵���B�b�͂c�ɓł�p�ӂ���悤�ɓ`���c�͂b�֓ł�n�����B�������A�a�q�Ƃb�͕ʂ̕��@��p���Ă`���E�Q�����B�a���b�C�c�͉��߂ŏ������邱�Ƃ��o���邩�B
�@�a�q�Ƃb�͎E�l�̌̈ӂ͂���A�������Ĕƍ߂��s�����̂ŎE�l�̋������ƂƂȂ�B�����ŁA�c�͂`�ւ̎E�l�ɂ͉��S���Ă��Ȃ����ǂ̂悤�ɏ������邱�Ƃ��\���B���_����o���ƁA�\���̋������Ƃɂ�����B���̂c�ւ̔����ɑ��Ď��͂��܂�[���͂����Ă��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�c�͂a�q�Ƃb�̎E�l�̎��s�s�ׂɂ͉��S���Ă��炸�A�a�C�b�C�c�Ԃ̋��d���Ȃ����c�����ɂ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�������A�\���߂͖ړI�ƂƂ��Ă���B���̂c�̍s�ׂ͓ł���肷��s���̒N���̎E�Q�s�ׂɌ������Ă���ƍl�����邽���\��������B�\���߂͎����ɔƍߍs�ׂɌ������Ă��\���s�ׁA�܂葼�l�ւ��\���͂����Ȃ��Ƃ��Ă���B����ɁA�\���s���͎��s�̒�������Ă��Ȃ���Ԃɂ��邵�A�`�̎E�Q�ւ̈��ʊW���Ȃ��B���ʊW���Ȃ���ΐӔC���A�����Ȃ��Ƃ��Ă���B��ϓI��@�v�f�̒��̖ړI�Ƃ͑��l�\����F�߂Ă��Ȃ����A���������\���Ƃ̋��Ƃ͂��������ƍl����ׂ��ł���B���Ƃ̏�������������A�ӔC���Ǝ�N��������B�ӔC���́A�s���̂������Ƃ��Ă���s�ז����l�I�ł���B�������A���ᓙ�͎�N���܂�A���Ƃ����������̂́A���Ǝ��g����@�ɖ@�v�N�Q���ʂ���N���邩�炾(���Q)�Ƃ��Ă���B�@�v�N�Q�����邩�珈���Ƃ��Ă��邽�߈��ʊW���Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B���̂悤�ɔ��Ⴊ�݂Ƃ߂Ă��܂��Ă���̂�������Ƃ��������ƍl����B���d���ɂ��֘A���邪�A�\���i�K�ł̏����͊w���ł͔F�߂Ă��Ȃ����ٔ��������������߂�̂Ɋ�������܂��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�R�@�댯���E�������Ƃ̊֘A��
�@�g�D�I�Ȕƍߋy�єƍߎ��v�̋K���Ɋւ���@���̕ʕ\�ɂ͊Y������ƍ߂͌f�����Ă���B���̒��̌��Z���������߂�Z���������߂Ȃǂ́A�����̊댯��Ƃ��Ă��܂��̂��댯���Ƃ��ď�������B���͉������ȂǂɔR���ڂ�\��������댯�Ƃ���Ă���B�댯���͒��ۓI�댯�ƂƋ�̓I�댯���̓�ɕ�������B���ۓI�댯���́A�@�v�͐N�Q����Ȃ��Ă����̍s�ׂ��@�v�N�Q�ɂȂ肤��Ƃ������ɐ�������Ƃ��Ă���B��̓I�댯���Ƃ́A��̓I�ȍ����댯�̒��x�K�v�ƂȂ�B��̓I�댯���͂����́u�����̊댯�v109��2�����Ȃ��Ɛ������Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B�ł�����Ǔ��̓��̂�����Z��ł��Ȃ������ɉ����Ă������̊댯�͔F�߂�ꂸ�A�ƍ߂��������Ȃ��̂ł��B���ۓI�댯���ł��錻�Z���������߂́A�l�����ɂ��悤�����܂������̉�����s���̂��댯�Ƃ݂Ȃ��Ă���B�d���߂ł���قǁA���ۓI�댯�Ƃł����Ƃ���Ă���B
���������ɂ���ƁA�v���ʂP�O�O���̓ł��`�Ɉ��܂��邪�a�C�b�͋��d�̈ӎv���ӎv�̘A�����Ȃ��`�ɂT�O�������܂����B�a�C�b�͉��߂ɂ����邾�낤���Ƃ�����ōl����ƁA���݂��̋��d���Ȃ����`�̎��S�͂ǂ����ɍs�ׂŔ������Ă��邩����ɂ͂����ɓ�l�Ƃ��E�l�̋������ƂƂ��ď������Ă���B����͂Q�O�V���ł��������Q�̓���Ƃ��āu��l�ȏ�Ŗ\�s�������Đl�����Q�����ꍇ�ɂ����āA���ꂼ��̖\�s�ɂ�鏝�Q�̌y�d��m�邱�Ƃ��ł����A���͂��̏��Q���������҂�m�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��́A�������Ď��s�����҂łȂ��Ă����Ƃ̗�ɂ��B�v�Ƃ��A�\�s�̌���ɂ���Ύ����̏��Q�ł͂Ȃ��Ƃ��������ł��Ȃ���Ώ��Q�̋������ƂƂ���Ă��܂��B������ߎ����F�߂��Ȃ��B
�������Ƃ́A�ߎ��͘A�тɐӔC�͌ʂɂƂ��Ă��邽�߁A�ߎ��͍\���v���ɊY������@�ŗL�ӂȍs�ׂ̗L�ӂ̕����ɓ��Ă͂܂��ߎ��̋������ƂɂȂ�̂͂��������ƍl����B�����]��������ӔC�̒i�K���ߎ���F�肵�Ȃ���Ήߎ��̂���Ȃ��͌l���킩�邱�Ƃ�����L�ӂ̒i�K�Ō��߂�ׂ����ƍl����B
�S�@�����ێ��@�Ƃ̈Ⴂ
���̂��������d���͂悭��}�Ȃǂ��������ێ��@�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ȃǂ̎w�E������B�����ێ��@�͍��̂⎄�L���Y����ے肷��^���������܂邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Đ��肳�ꂽ�B�Ƃ��ɋ��Y��`�v���^���̌��������O�������̂Ƃ����Ă��邪�A�₪�ď@���c�̂�A�E�������A���R��`���A���{�ᔻ�͂��ׂĒe���E�l���̑ΏۂƂȂ��Ă������B�����ێ��@�͎v�z�������܂��Ă���ƍl���Ă��邽�߁A����̂��������d���͍߂������܂��Ă���̂��Ⴂ�ł͂Ȃ����Ǝv���B�������A�����������ɉ���Ŋ�n���݂ɔ������Ă���l�����������܂邱�Ƃ��\�ł���A���{�⎞��̗���Ȃǂŕ߂܂�Ώۂ��ς��\���̓[���ł͂Ȃ��B�ƍ߂̗v�������d���ƌ��܂炸�A���{�ɔ��̈ӌ������g�D�ɏ���������̂���̔ƍ߂ŏ������邱�Ƃ��\�ɂȂ肤��B����́A�����ێ��@�ƕς��Ȃ��ƍl����B�����܂ł����Ȃ��ɂ���A�����܂��ł������d���ŕ߂܂�l�����Ȃ�������ɂȂ�댯�������Ȃ�ƍl���Ă���B
�T�@������
����̖@���́A�����킽���͎^���̗���Ńe���𖢑R�ɖh���ƂĂ������@���ł���ƍl���Ă����B�������A�ƍ߂̐����v���������܂��ł��邱�Ƃ₽�����̑g�D�ɓ����Ă��邾���Ȃ̂ɏ��������\��������ƒm��A���܂�c�_������Ă��Ȃ��������ɂ悭�Ȃ����ł���A�ƍ߂̐����v���������Ƌ������邱�Ƃ��d�v�ł���ƍl����B���d�ɒi�K�ł̏����ł͂Ȃ����̋N�������ƍ߂Ƃ̌l�̈��ʊW���������肨����������������ق����ǂ��B�����A�ڂ̑O�܂ŗ��Ă���e�����Y���ɑ���@���A�܂��͂��̖@�������邱�Ƃō��ۏ��̒����ł���̂ł���A���O�ɔƍ߂�h�~����p���͂������ɑf���炵�����Ƃł��邪���܂����d���ł͂��܂��N���Ă͂Ȃ�Ȃ��l�߂�l�̎v�z�A�l���Ȃǂ��Ȃ�������ɂ��Ă��܂��s�\���Ȗ@���ł���ƍl���Ă���B�����̂��Ƃ��玄�́A���������d���܂��܂������_�̂���s�\���Ȗ@���ł���ƍl���Ă���B
�o�T�@���P�Y�@�S�I�@���n����
�@�@�@���QWikipedia���Ɓ@��N��
���엽��
��b���{�Ȗځ@���j�T���@�P�UJ�P�P�W�O�O�W�@���엽��
�������d���Ɏ^���ł��B���̗��R�͂Q�O�Q�O�N�ɓ����I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���߂Â��Ă��萢�E���̐l�������W�܂��ė��܂��B�S�N�ɂP�x�Ƒ�ȐߖڂɃe���s�ׂ��N�������Α����̖����D���Ă��܂��܂��B�܂��A���d��������Ώd��Ȏ��������R�ɖh�������ł��܂��B��\�I�Ȏ������n���S�T���������ł��B�P�X�X�T�N�R���Q�O���ߑO�W������A�����s���̒n���S�ۂ̓����A����J���Ŋe�Q�Ґ��A���c���łP�Ґ��A�v�T�Ґ��̒n���S�ԓ��ŁA���w����Ƃ��Ďg�p�����_�o�K�X�T�������U�z���ꂽ�B�i�o�T�@�n���S�T���������@Wikipedia�j���̎����ɂ��P�R�l�̋]���҂Ɩ�U�R�O�O�l�̏d�y���҂��o�܂����B���͂Q�x�Ƃ��̂悤�Ȏ����͋N���Ăق����Ȃ��ł��B�ƍߑg�D���ƍ߂��N�������ƌv�悵�����_�őߕ߂���ׂ��ł��B
�ł́A�g�c���A�Ə������m�����d���̊Y������̂��B�g�D�I�Ȕƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@��
�i�g�D�I�ȎE�l���̗\���j
��Z���@�@�@��@�Y�@��S��\��i�E�l�߁j�̍߁@�ܔN�ȏ�̒���
�@�@�@�@�@�@��@�Y�@���S��\�܁i�c���ړI������y�їU���j�̍߁i�c���ړI�Ɍ���j��N�ȏ�̒���
�@�@�@�@�A�@��@��L�̗\���������҂��A�����Ɠ��l�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@��@���̊e���ɗg����߂ɓ�����s�ׂŁA�e�����Y���W�c���̑��̑g�D�I�ƍߏW�c�̒c�̂̊����Ƃ��āA���Y�s�ׂ����s���邽�߂̑g�D�ɂ��s������̂̐��s���l�ȏ�Ōv�悵���҂͂��̌v��������҂̂����ꂩ�ɂ�肻�̌v��Ɋ�Â��������͕��i�̎�z�W�ꏊ�̉������̑��̌v��������ƍ߂����s���邽�߂̏����s�ׂ��s��ꂽ�Ƃ��́A���Y�e���ɒ�߂�Y�ɏ�����B
�Ə����Ă���B
�Z�����A��̗�Ƃ��āA�w���g�D�ɉ��������̑g�D���Z���̍߂�Ƃ��Ă����B�w�͉�������
����A�g�D�ɂ��ďڂ����킩��Ȃ����������Ă��Ȃ��B�������A�g�D�ɏ������Ă���S
������������B������A���Ɨ��_�ƌ����B���ƂƂ́A�ƍ߂��Q�l�ȏ�̎҂����s�����
�������Ƃƌ����B�i�o�T�@�x�@���̂��߂̂킩��₷���Y�@�@���X�ؒm�q�@���j���Ɨ��_��
�͎O�̏]����������B��ڂ͎��s�A���Ƃ��ƍ߂����s���邩�A���Ȃ����B��ڂ͍ߖ�
�A��l���l���E��������l����������������Ƃ����ꍇ�A��l��l�����ꂼ��
�o���o���ɍߖ����ۂ��ׂ����B�O�ڂ͗v�f�A�ɒ[�A�����A�ŏ��B���̎O�ڂ̗v�f�ɂ�
�Đ[�����ׂ�ƁA�܂��ƍ߂Ƃ́H�������B�ƍ߂ɂ͍\���v���A��@���A�L�ӂ����肱�̎O
������Ȃ���Δƍ߂Ƃ͌��킸�ƍ߂ɂȂ�Ȃ��B�\���v���ɂ͎�ϓI�A�q�ϓI���ʊW��
����B���ʊW�Ƃ́A�������v���Ă��鎖���ƌ��ʎ������v���Ă��������Ƃ͈�����Ƃ���
�s�ׂƌ����Ƃ̊ԂŔ�������W�ł���B�����ł́A�s�ׁi�����j�ƌ��ʂ̊ԂɁA����i
�����j�Ȃ������i���ʁj�Ȃ��A�Ƃ��������W���F�߂���ꍇ�Ɉ��ʊW���F�߂���B���ׂČ��ʔƂɂ����ẮA�����ƂȂ���s�s�ׂƌ��ʂƂ̊Ԃ̈��ʊW���F�߂��Ȃ���A�\���v�������Ȃ��B�i�o�T�@�x�@���̂��߂̂킩��₷���Y�@�@���X�ؒm�q�@���j
�����āA��ϓI�A�q�ϓI���ʊW�́A�O�҂͎������������Ǝv�����������������B�Ƃ������ʊW�����邩�A��҂͈�ʐl�ł�����������Ƃ����������d�v���ƍl���A���ꂪ�������������Ȃ������ł��낤�Ƃ������ƁB�i�o�T�@poweredbyhonda07�j
��@���͌Y�@��O���i�����s�ׁj�@�ߖ��͐����ȋƖ��ɂ��s�ׂ́A�����Ȃ��B
��O�Z���i�����h�q�j�ꍀ�@�}���s���̐N�Q�ɑ��āA���Ȗ��͑��l�̌�����h�q���邽�߁A��ނ��ɂ����s�ׂ́A�����Ȃ��B
�@�h�q�̒��x���z�����s�ׂ́A���ɂ��A���̌Y�����y���A���͖Ə����邱�Ƃ��ł���B
��O�����i�ً}���j�ꍀ�@���Ȗ��͑��l�̐����A�g�́A���R���͍��Y�ɑ��錻�݂̊�������邽�߁A��ނ��ɂ����s�ׂ́A����ɂ���Đ������Q�������悤�Ƃ����Q�̒��x���z���Ȃ������ꍇ�Ɍ���A�����Ȃ��B�������A���̒��x���z�����s�ׂ́A���ɂ��A���̌Y�����y���A���͖Ə����邱�Ƃ��ł���B
�@�O��̋K��́A�Ɩ�����ʂ̋`��������҂ɂ́A�K�p���Ȃ��B
�ƎO�̏��܂܂�Ă���A�ƍ߂Ƃ��ď������ׂ���@���ǂ��l���邩�ɂ��āA�Y�@�Ŏ��ׂ���@�̖{���́A������Љ���Ƃ��������R�Ƃ������̂łȂ��A�Y�@�Ŏ��˂Ȃ�Ȃ��@�I���v�i�@�v�j�ł���A���ꂪ�N�Q���ꂽ���Ƃ���@�ƂȂ�B�@�v�͑傫�������č��ƓI�@�v�A�Љ�I�@�v�A�l�I�@�v�̎O�ɕ��ނ���A���Ōl�I�͂���ɐ����A�g�́A���R�A���_�A���Y�̌܂ɕ��ނł��A�@�v�͂��̏��ŏd���ƍl������B�ƍ߂ł������A�ȏ�̂����̉��炩�̖@�v��N�Q����s�בԗl����߂��Ă���Ƃ������ƁB�@�v�����̂��Y�@�̖�ڂȂ̂ŁA��@�Ƃ͂��Ȃ킿�@�v�N�Q���Ƃ������ƂɂȂ�B
�i�o�T�@�x�@���̂��߂̂킩��₷���Y�@�@���X�ؒm�q�j
�ł́A�Y�@�Ƃ́H�Y���̖ړI�͓����B��͉���_�A������Ƃ����l�����B������͖ړI�_�A������������Ƃ����l�����ł���B
�@���Ȃ���Δƍ߂Ȃ��A�@���Ȃ���ΌY���Ȃ��B����́A�`�F�[�U���E�x�b�J���[�A�Ƃ����Y�@�w�҂��咣����ߌY�@���`�ł���B���̒��ɂ́A�@����`�E�k�y�����̋֎~�E���m���E�f���[�v���Z�X������B
��@���̘b�ɖ߂�ƁA��@���̒��ɂ͍s�ז����l�ƌ��ʖ����l������A���̓���ȒP�Ɍ����\���ƁA�s�ז����l�������i�S�̒��j�Ɩ@�v�A���ʖ����l���@�v�̂݁B�ł́A�����l�Ƃ͂ǂ������Ӗ��Ȃ̂��B�h�C�c��ň�@�ƌ����Ӗ��B�܂�A�s�ז����l�ƌ��ʖ����l�͂��̂悤�ȈӖ��ɂȂ�A
�u���ʁi����N�������Ɓj����@�v���A�u�s�ׁi�����邱�Ɓj����@�v���Ƃ��������B
�i�o�T�@�x�@���̂��߂̂킩��₷���Y�@�@���X�ؒm�q�@���j
�����āA��@���͍s�דI�����l�ɉe������邱�Ƃɂ���āA��ϓI��@�v�f���o�Ă����B��ϓI��@�v�f�Ƃ́A�s�ׂ����ʂ������Ƃ��q�ϓI�ȗv�f�Ȃ̂����A�{���͎�ϓI�ȗv�f������ƌ������Ƃł���B
����o���ƁA����̑�w�̑��Ə؏����U�����ĉƂɏ����Ċy����ł��܂��B�����悤�ɁA���M�����������̂ł����A���������Ȃ������̂ŁA���̍ۂ�����Əؖ���������ɍ���ĉƂɏ����Ē��߂Ċ��ł��܂��B�Ƃɗ����l�����e���Ă����̂ŁA�{���ɖ�����Ɠ����Ă��܂����̂ł����A���͋U���E�s�g�ɂȂ�܂����H
�i�o�T�@�x�@���̂��߂̂킩��₷���Y�@�@���X�ؒm�q�@����j
���_�͉��߂ɂ��Ȃ�܂���B��ϓI��@�v�f�ɂ͌̈ӂ�����Â���̈ӂƂ͕ʂ̂��̂ł���A�ړI�ƁE�X���ƁE�\���ƁE�s�@�̓��̈ӎv�Ƃ���炪�Ȃ��Ɣƍߐ������Ȃ��B
�ł́A�s�ז����l�ƌ��ʖ����l����L�ӂ܂łǂ̂悤�ɍs���̂��A�L�ӂɂ�
�Y�@��O����i�S�_�r���y�ѐS�_�Վ�j�ꍀ�@�S�_�r���҂̍s�ׂ́A�����Ȃ��B
�@�S�_�Վ�҂̍s�ׂ́A���̍s�ׂ����y����B
��l����i�ӔC�N��j�@��l�ɖ����Ȃ��҂̍s�ׂ́A�����Ȃ��B
���̓��������A��ϓI���ߗv�f����ӔC�I�̏�́u�s�ז����l�v�ƕs�@�̓��̈ӎv����̈ӂ́u���ʖ����l�v�̓�����ꂼ��u�m���I�̈Ӂv�Ȃ̂��u���K�̌̈Ӂv�Ȃ̂��u�F�������ߎ��v�Ȃ̂��u�F���Ȃ��ߎ��v�Ȃ̂����f���L�ӂɍs���B
��L�ɏ������Ē������v�f�̋ɒ[�E�����E�ŏ��̎O���\���v���ɏƂ炷�ƁA�ɒ[�͍\���v���E��@���E�L�ӂ������ĂȂ�������Ȃ��B�����͍\���v���E��@���B�ŏ��͍\���v���̂݁B�܂��A�ŏ��ɂ́u�s�������v�Ɓu�ƍߋ������v�̓�̋�����������B�������Ƃ̐�������v���́u�d�c�v����u���s�v�����āu���ʁv�A�����ĊԂɈ��ʐ�������B�������ƂƂ́A�u���Ɓv�E�u���Ɓv�̋��Ƃɓ���A�������ƁE�����ƁE���Ƃ̎O������B�����ƂƂ́A�ƍ߂����錈�ӂ����ĂȂ��w�N���x�N�������̂����A�ƍ߂����s�����鎖�������A
�Y�@��Z����i�����j�ꍀ�@�l���������Ĕƍ߂����s�������҂ɂ́A���Ƃ̌Y���Ȃ���B
�@�����҂����������҂ɂ��Ă��A�O���Ɠ��l�Ƃ���B
�ɂ���Ĕ�������B�������ƂƂ́A�ƍ߂��s���w�N�̎��s���x�N���菕�����鎖�������A�Y�@��Z����i�j�ꍀ�@���Ƃ�����҂́A�]�ƂƂ���B
�@�]�Ƃ����������҂ɂ́A�]�Ƃ̌Y���Ȃ���B
�ɂ���Ĕ�������B�����āA�������ƂƂ́A��l�ȏ�̎҂������̔ƍ߂��ꏏ�ɍs�����������A
�Y�@��Z�Z���i�������Ɓj��l�ȏ㋤�����Ĕƍ߂����s�����҂́A���ׂĐ��ƂƂ���B
�ɂ���Ĕ�������B
���Ƃɂ́u���ڐ��Ɓv�Ɓu�Ԑڐ����v�̓�ɂ킯���A���ڐ��ƂƂ͌��t�̒ʂ�{�l���炪�ƍ߂����s���邱�Ƃł���B�ł́A�Ԑڐ����Ƃ́A�w�N�������m��Ȃ��x�N�������̓���̂悤�ɗ��p���Ĕƍ߂����s���邱�ƁB�����A���p���ꂽ�x�N����l�Ζ����̐ӔC���\�͎҂������ꍇ�́A�x�N�͐��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�x�N�𗘗p�����w�N�͊Ԑڐ��Ƃł͂Ȃ��A�����ƂɂȂ�Ƃ����B
�b���ŏ��̑g�D�ƍߏ����@�ɖ߂��ƁA����́A�Z���̓��@�őg�D�ɉ������Ă��邾���ŏ������鋤�Ɨ��_����������Ē��������A���Ɂu�s�ח��_�v�ɂ��ďڂ������ׂ����Ǝv���܂��B
�s�ח��_�Ƃ͑g�D�̒��ň�l���ƍ߂����s���邽�߂��\���s�ׂ����Ă����ꍇ�A���̈�l����������̂ł͂Ȃ��A�g�D�ɏ������Ă���ґS������������Ƃ������ƁB����́A�ʕ\�O�E�l�Œ�`����Ă���B�܂��A�\���s�ׂƂ͏�L�ɂ���悤�ɁA�ƍ߂����s����ׂ̏��������邱�Ƃł���A�ƍ߂ɂ܂����肵�Ă��Ȃ����s�O�̂��Ƃ������B
�����A�g�D�̒��̒N����l�����s�s�ׂ������ꍇ�A�������l�����łȂ��g�D�ɏ������Ă���S������������B��������d���������ƌ����B
���d���������Ƃ͈�l�ȏ�̑g�D���ƍ߂����邽�ߋ��d���A�g�D�ɏ�������S�����ƍ߂����s����̂ł͂Ȃ����̂����ꕔ�̎҂ł��ƍ߂����s�����ꍇ�A���Ɏ��s���Ȃ������҂ɂ��������Ƃ̍߂��Ƃ������Ƃł���B�������A�ƍ߂̎��s�Ɋւ��Ȃ������҂́A�������Ƃł͂Ȃ������Ƃ܂��͏]�Ƃł͂Ȃ����Ƃ�������������������͏]���̖@�����_��傫���ύX���ċ��d�҂��������ƂƂ��Ĕ������B
���Ƃ��Ƒg�D�ƍߏ����@�́u���d�v�E�u�\���v�E�u�����v�E�u�����v�̎l�̒��Ŗ���������������s�̒���ɂ���ď������Ă������A���d���͑g�D�����d�������_�ŏ������邱�ƂɂȂ�B
�ȏ�̎����玄�͏��c���A�Ə������m�����d���ɊY������Ǝv���܂��B
���́A���R�͍u�`�Řb�����悤�ɏ������m�̂`���u���̒����������Ă���̂͊����ł���v�Ǝv���l�ߊ����Ɋ�������ׂ��鎖���v��B�`�͂��ׂ̈Ƀi�C�t���w�������B���d�߂Ƃ͏ł͓�l�ȏ�̎҂����̔ƍ߂��s�����Ƃ��鍇�ӁB�i�o�T�@�u���^�j�J���ۑ�S�Ȏ��T�j�Ə����Ă���ׁA�`�������Ɋ�������ƌv�悵�����ɂa���a�Ƃ��̑����������`�ƈꏏ�Ɍv������Ă���A���d�߂ɂȂ�܂��B�������A����̐����̏ꍇ�͂`����l�Ōv��������ƍl�����܂��B�Ȃ̂ŁA���̎��_�ł͋��d�߂ɂ͂Ȃ�܂���B
���ɂ`���v������s����ׁA�i�C�t���w�������B�����m���̂a�͉��߂��B���́u�\�������d�������Ɓv�ɓ�����Ǝv���܂��B�`�͊����Ɋ�������Ƃ����ړI�����߂��玝���ăi�C�t���w�����Ă��鎖����g�D�̈�l���\���s�ׂ��s���A�܂�s�ח��_���珼�����m�ɏ������Ă���S�����g�D�ƍߏ����@�ɂ�菈������ƍl���܂��B������̗��R�Ƃ��āA�g�D�ƍߏ����@�̓̏ɏ������m�ɓ��Ă͂܂�L�[���[�h��������邩��ł��B
�ł́A���d�߂��܂��@�Ƃ��Đ������ĂȂ����A�������m���邱�Ƃ͂ł���̂��B���c���A�Ə������m�ɂ��Ē��ׂ�ƁA���c���A�͖��{�ɕs���������ˎ傩���ʂ̕���B���Ă��܂����B���̎��_�ŗ\�������d�������ƂɂȂ�Ǝ��͍l���܂��B�������A���d�����Ȃ��ꍇ�͉��̍߂ɖ���邩�B����́A�댯���ɂ���ď��������ׂ����Ǝv���܂��B�댯���Ƃ́A�@�v���N�Q���ꂽ�Ƃ������ʁi���Q�j���������Ȃ��Ă��A�@�v�N�Q�̊댯����������ΐ�������Ƃ����ƍ߁B�i�o�T�@�f�W�^���厫��j
�����A���c���A�Ə������m�����{�ɑ��ĉ���Ƃ��Ƃ���A���ʂ��������Ȃ��Ă��@�v�N�Q�̊댯����������Δƍ߂ƂȂ�܂��B
�Ō�A�����ێ��@�ɂ��Ăł������̖@���ŏ������m���邱�Ƃ͂ł���Ǝv���܂����A���͂��̖@�ŏ������邱�Ƃ͔��ł��B���R�͐l���Ɋւ����ł���������ł��B���X�̋K���傫���E�����A�x�@���ƌ��@���ɂƂ��Ă͂ƂĂ��s���̂����@�ɕς���Ă����Ă��܂��܂����B���̖@���͂ǂ�ǂ�\�����Ă��������Ɉȏオ�ߕ߂��ꍉ������ꂽ�����ł��B
�ȏ�̎����玄�͋��d�߂Ɏ^���ŁB�����ێ��̂悤�ɞB���Ȗ@���Ō��ʑg�D�������ɔ����鎖�͏o���܂���B���d���ɔ��̐l�̈ӌ��ł̓v���C�x�[�g�̐N�Q�ɓ�����Ƃ����ӌ�������܂����A�e�����N�����Ă���ł͒x���ł��B���d�����Ȃ���e���ɑ��č\����p���݂̂ɂȂ�A�e�����N���ċ]���҂���R�o�Ă��܂��Ă���e�����X�g��ߕ߂ł͒x���ł��B�g�ł͂Ȃ��U�߂邱�Ƃ��K�v���Ǝv���܂��B�n�߂ɏ������Ē������悤�ɂ��ꂩ��I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�Ȃǂ�������{�͖Z�����Ȃ��čs���܂��B����ێ��͐��ނƂ������t������悤�ɂ����~�܂��Ă����Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�ǂ�ǂ��čs���Ȃ��Ă͂����Ȃ��ł����A����͎������������ł��B
�O���A�����b�ɂȂ�܂����B���]�搶�̎��Ƃ͂ƂĂ�����A�悭�����g���܂����A��Ɏ����̂��߂ɂȂ���Ƃ��Ǝv���܂��B����͂����Ɩ@��������Đ搶�ɓ��Ă�ꂽ���ɂ�����������悤���x���A�b�v���Ď��ƂɗՂ݂����Ǝv���܂��B
������ǂ�����낵�����肢���܂��B
�n�c�T��
�鋞��w�@�w��2�N�@16j118009�@�n�c�T��ł�
�ۑ�̃��|�[�g���o�����Ē����܂��B��낵�����肢�v���܂��B
�ƍߗ\�h�Ɛl���@
16j118009 �n�c �T��
����
���͔ƍߗ\�h�Ɛl���̊W����g�D���ɏ������ĂȂ���ʐl�͂ǂ̂悤�ɊW����̂����������B
�P�A
�����ƒ���
���s�̒���Ƃ́A�ƍ߂̐����v���̂ЂƂł���B�ƍ߂̎��s�ւ̒��肪������������𐋂��Ȃ������ꍇ�𖢐��ƂƂ����B���s�̒���́A����ȑO�̗\����A�d�̒i�K�ƁA����Ȍ�̖����̒i�K�Ƃ��镪����̖������ʂ����Ă���B�����Ə����̋K�肪����ꍇ�ł��A���s�̒���Ɏ����Ă��Ȃ���A�\�����̏����K�肪�Ȃ�����ƍߕs�����ƂȂ�B�����Ə����̋K�肪����ꍇ�ɁA���s�̒��肪�F�߂���Ƃ��͖����ƂƂȂ�A����Ɋ����ɒB����Ɗ����ƂƂȂ�B�\���v���Ƃ͌Y���@�K�ɋK�肳�ꂽ�X�̔ƍߗތ^�B���Ƃ��A�Y�@��199���́u�l���E�����ҁv�A���@��235���́u���l�̍�����ގ悵���ҁv�Ȃǂ�����ɂ�����B�����̋K��́A���ꂼ��A�E�l�߂̍\���v���A�ޓ��߂̍\���v���Ƃ����B�ƍ߂��������邽�߂ɂ́A�܂��A����s�ׂ������ꂩ�̍\���v���ɊY�����邱�Ƃ�v����ƂƂ��ɁA���̍\���v���ɊY������s�ׂ��A��@�ŁA���L�ӂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�����ƒ���̐������▢���Ə����Ɨ\���߂����d�߂Ƃǂ��ւ�邩�Ƃ������ƂɂȂ�B
�Q�A
�s�������A�ƍߋ�����
�s�������Ƃ́A�������Ƃ̖{���ɂ��āA�e�����҂͍s�ׂ��������Ċe���̔ƍ߂����s����Ɖ����錩�����Ӗ�����B
�������Ƃ̖{���ɂ��ẮA�ƍߋ������ƍs�������̑���������B�ƍߋ������́A�������Ƃ���������ꍇ�A�e�����҂͓���́u�ƍ߁v���������Ď��s���Ă���Ɖ�����B����ɑ��āA�s�������́A�e�����҂́u�s�ׁv���������Ċe���̔ƍ߂����s���Ă���Ɖ�����B���Ȃ킿�A�ƍߋ������͋������Ƃ��u���l��߁v�Ɖ�����̂ɑ��āA�s�������͋������Ƃ��u���l���߁v�Ɖ�����B
��̌����̎����I�ȑΗ��_�́A�������Ƃɂ�����ߖ��]�����̍m�ہA���Ȃ킿�A����̍ߖ��ɂ��Ă̂������Ƃ̐������m�肷�邩�ۂ��Ƃ����_�ɂ���B
�ƍߋ������́A����̍ߖ��ɂ��Ă̂������Ƃ̐������m�肷��B�����O�ꂵ����������S�ƍߋ������ƌĂԁB�������A���̌����͍ߖ��]���������i�ɉ����邽�߁A�������Ƃ̐����͈͂������Ȃ肷���A�Y�̕s�ύt��������B�����ŁA�e�����҂��قȂ�ߖ��̔ƍ߂����s����ꍇ�ɂ��A�\���v�����d�Ȃ荇�����x�ŋ������Ƃ���������Ƃ����������咣����Ă���i�����I�ƍߋ������j�B
����ɑ��āA�s�������́A�قȂ�ߖ��̔ƍߊԂɂ����Ă��������Ƃ̐������m�肷��B���Ȃ킿�A�������Ƃɂ�����ߖ��]������ے肷��B
����Ŕƍߋ������Ƃ́A�ƍߋ������Ƃ́A�������Ƃɂ����ẮA�����̍s�҂�����̔ƍ߂��������Ď��s����Ɖ����錩���ł���B
���������āA���Ǝ҂̊Ԃɂ͓����ƍ߂ɂ��Ă̋������Ƃ������������A����͂����鐔�l��߂̍l�����ɗ��r����B
���̍l������O�ꂵ�����S�ƍߋ������ɂ����ẮA�܂����������\���v���ɂ��Ă݂̂����������Ƃ̐�����F�߂Ȃ��B
���Ƃ��AA��B�����ꂼ��E�l�Ə��Q�̌̈ӂŁAP�Ɍ����Ă��̔w�ォ�猝�e���ꏏ�ɔ��˂������ʁA����̒e�ۂ݂̂���������P�����S�����ꍇ�A�������Ƃ͐��������A���ꂼ��P�ƔƂ̐ӔC���ɂ����Ȃ��B
���������āA�E�ӂ�L����A�ɂ����P�̎�����N���ꂽ�ꍇ�ɂ́AA�ɂ��ĎE�l�߂��AB�ɂ��Ė\�s�߂���������̂ɑ��āAA�����Q�̌̈ӂ�L���Ă����ɗ��܂�ꍇ�ɂ́AB�ɂ͏��Q�v���̋������Ƃ��������A���̌��_�͑Ó��łȂ��B
�����ŁA���݂͕����I�ƍߋ������Ƃ����������̗p����Ă���B
���̌����́A�̈ӂ��قɂ��鋤���҂����s���悤�Ƃ���قȂ�ƍ߂ɂ��āA���̏d�Ȃ荇�����x�ŋ������Ƃ̐������m�肷��Ƃ������̂ł���B
��L�̗�ł́A�E�l�߂Ə��Q�߂��d�Ȃ荇�����Q�v���̌��x�ŁAA��B�ɋ������Ƃ���������B�������A���̂悤�ɉ����Ă��E�ӂ̂���A�ɂ��ĔF�߂���ߏ蕔���̍ߐӂ����ƂȂ�B����́AA�̒P�ƔƁi��L�ł͎E�l�߁j�Ƃ��ď�������邱�ƂɂȂ邪�AP�̎��̌��ʂ��d�]�����邱�Ƃ�����邽�߁AA�ɂ��Ă͎E�l�߂̐����݂̂��m�肳���B���������āAA�ɂ��ĎE�l�߂̒P�Ɛ��ƁAB�ɂ��ď��Q�v���߂̋������Ƃ���������B
�R�A
�ƍߗ\�h
�܂��A���d�����g�D�I�Ȕƍߋy�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@���̈Ⴂ
���ۂ����߂�Ƃ��Ȃ��Ă��A�v��̒i�K�Ŕƍ߂ɂȂ�B�܂�����A�����A�\���̑O�����d�ƂȂ�߂ɂ܂�B�g�D�I�ƍߏW�c���ΏۂŁA��ʐl�͑ΏۊO�������s�̒��肪�ς�苤�Ƃ̏]�����ɂ�������邾�낤�B�\�͒c�E�e���g�D�Ȃǂ̔��Љ�I�c�̂�A��ЁE�����c�́E�@���c�̂Ȃǂɋ[�������c�̂ɂ��g�D�I�Ȕƍ߂ɑ���Y���̉��d�ƁA�ƍߎ��v�̃}�l�[�E���[���_�����O�s�ׂ̏����A�ƍߎ��v�̖v���E�ǒ��Ȃǂ��߂�̂��g�D�I�Ȕƍߋy�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@���ƒ�߂��Ă���A���d���Ƃ��Ȃ莗�ʂ����_������B�����ň�C�ɂȂ����_������A��Ђɑ��Ă��g�D�I�Ȕƍ߂Ƃ��ēK�p����邪�u���b�N��ƂȂǂ̒����ԘJ�����]�ƈ��ɂ����Ă����Ђ́A�g�D�I�Ȕƍ߂ɂȂ�Ȃ��̂��낤���A��Ђ́A���v��������œ��Ă͂܂�̂łȂ����ƍl�����B
1925�N�ɑ吳14�N4��22���@����46�����肳��c���⎄�L���Y����ے肷��^���������܂邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Đ��肳�ꂽ���{�̖@���ŏ@���c�̂�A�E�������A���R��`���A���{�ᔻ�͂��ׂĒe���E�l���̑ΏۂƂȂ����̂������ێ��@�����d���Ƃ͑g�D�I�Ȕƍ߂Ƃ����_�ł͓����ł��邪�����ێ��@�͈�ʐl���������܂��������d���ł͈�ʐl�͑Ώۂł͂Ȃ��̂Ŋ댯���͂��܂�Ȃ��ƍl����B
���l��̂悤�ɗ��p���Ď���̔ƍ߂����s���邱�ƁB���ʂ̎���̂��Ƃł́A���̂悤�Ȕƍ߂̎������\�ƂȂ�B���Ƃ��A��t���A���҂�ŎE����ړI�ŁA�����m��Ȃ��Ō�t�ɑ��āA�Ŗ�������������ˉt�����҂ɒ��˂�����ꍇ������ɂ�����B���ڐ��Ƃ��Ԑڐ����͑ΊT�O�ł���B�Ԑڐ��������l�̍s�ׂ𗘗p���Ĕƍ߂����s����̂ɑ��A���ڐ��Ƃ͍s�Ҏ��g�����ړI�ɔƍ߂����s����ꍇ�ł���B�܂��A�Ԑڐ���������̔ƍ߂����s����_�ɂ����āA���l���ƍ߂����s����ɂ������Ă���ɉ��S���鋷�`�̋��ƁA���Ȃ킿���������Ƌ�ʂ����i�Ȃ��A�Ԑڐ��Ƃ�ے肵�A���ƂƉ����錩��������j�B�����ŁA�Ԑڐ����Ƃ͉����A�Ƃ��ɒ��ڐ��Ƃ⋤�ƂƂǂ̂悤�ɋ�ʂ��邩�́A���ƂƂ͉����A�܂��A���ƂƋ��Ƃ������ɋ�ʂ��邩�Ƃ������_�I�Ȗ��̌������܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��A�ƍ߂ɂ���ẮA�U�؍߁i�Y�@169���j�̂悤�ɁA���ƎҎ��g�ɂ�钼�ڂ̍s�ׂ�v������̂�����A���������ƂƂ����B����Ƃɂ͈�ʓI���Ԑڐ�����F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B2�l�ȏ�̎҂�����̔ƍ߂��������Ď��s���鋤���ƍs�̌`�Ԃ������B���̏ꍇ�e�l�́C�������Ĕ������������ʂ̑S���ɂ����ׂĎ��Ȃ������������̂Ɠ������ӔC��Ȃ���Ȃ�Ȃ� (�ꕔ���s�̑S���ӔC�̌���) �B����́C�e�������s�S����ꍇ�͂������C���d�̂������d�҂̂���҂������ӎv�Ɋ�Â��Ď��s�����Ƃ��́C���s�S���Ȃ����̎҂��܂��������Ƃł���Ƃ���B�w���ł́C���s���Ȃ����d�҂����������Ƃ��邱�Ƃ�ے肷�錩�����Ȃ��L�͂ł���B��l�ȏ�̎҂��������Ĕƍ߂����s���邱�ƁB�֗^�����S�������ƂƂ��Ĕ�������B
4.
���Ə]����
���Ƃ������̑ΏۂƂ��Đ������邽�߂ɂ́A���ƂɈ��̗v�����[������邱�Ƃ�K�v�Ƃ���Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B���Ə]�����́A���s�A�v�f�A�ߖ��Ƃ����R�̖��ɋ�ʂ���Ă���B���s�Ƃ́A���Ƃ̖����Ƃ��������邽�߂ɂ͐��Ƃ����s�ɒ��肵�����Ƃ�v���邩�Ƃ������ł���B�����Ƃ́A�ƍ߂̌��ʔ����̊댯�����������Ƃ��������錋�ʔƂł��邩��A�����ƂƛƂɂ����ẮA���Ƃ����s�ɒ��肵�Ȃ�����̂悤�Ȋ댯�͔������Ȃ��B
���́A�����́A�\���v���ɊY�����Ȃ��ƍl����̂ŋ��Ə]�����ɂȂ�Ǝv���B
5.
�g�D�I�ƍ�
�ƍ߂̍\���v����A���Q�̔������邱�Ƃ�v�����A�@�v���N�Q�����댯�܂��͋��Ђ�������ΐ�������Ƃ����ƍ߁B���Ȃǂ��댯���Ƃ��������d�߂Ȃǂ̑g�D�I�Ȕƍ߂ɂǂ����т��̂��낤���A�Ⴆ�ΎE�l�߂Ȃǂ̂悤�ɁC���̋K��ɂ���ĕی삵�悤�Ƃ��闘�v�������ɐN�Q����邱�Ƃɂ���Đ�������ƍ߂�N�Q�ƂƌĂԂ��C����ɑ��C�Ⴆ�Ε��߁C�����댯�߂̂悤�ɁC�@�v�N�Q�̊댯�̔����݂̂ɂ���Đ�������ƍ߂��댯���Ƃ����B���́A�@�v�N�Q�ȂǑg�D�I�Ȕƍ߂ɂ��\���l������Ƃ��������B
��l�ȏ�̎҂��A�ӎv�̘A���Ȃ��ɁA���܂��ܓ����ɓ����Q�҂ɑ�����Q�s�ׂ����邱�ƁB�ƍ߂̐��ۂɊւ��Ă͊e�l�ʂɕ]������邪�A���Q�̓����Ƃɂ��Ă͋������ƂƂ��Ď�舵����̂���������������́A���d���ɂ�����̂��낤���A�ӎv�̘A���Ȃ����Ǝ������d�ɂ�Ȃ�Ȃ��ƍl����
���ƊW�ɂȂ���l�ȏ�̎҂��A����̎��ԁE�ꏊ�Ŕƍs���Ȃ����ƁB�Ɨ��ɔƍ߂���������B����́A���O�̑ł����킹�܂蒅�肪��l�ł����̂���l�ł����̂��Ɠǂݎ���B
��ʂɁA���ʔ����̉\��������ꍇ�A�s�҂����ӂ�����A���̌��ʂ̔�����\���������̂ɂ�������炸�A�s���ӂɂ���ĔF�����Ȃ����Ɓi���Ȃ킿�A���ӂ��ׂ��ł���̂ɒ��ӂ��Ȃ��������Ɓj���Ӗ�����B�s���ӂƂ́A���Ӌ`���Ɉᔽ���邱�Ƃ������B���ʂ̔�����F�������ꍇ�́u�̈Ӂv�Ƌ�ʂ����B�@���p��Ƃ��ẮA�ߎ��͌̈ӂƕ��ԐӔC�̌`���E�v�f�ł���A�̈ӂ��Ȃ����Ƃ��O��ƂȂ�B������A����̃e�[�}�g�D�I�Ȕƍ߂Ɛl���ƃ}�b�`���Ă��āA�������̔ƍ߂��s�����Ƌ�̓I�E�����I�ɍ��ӂ��邱�Ƃɂ���Đ�������ƍ߁B���ۂɔƍ߂��s��Ȃ��Ă��A���炩�̔ƍ߂����d�����i�K�Ō����E�������邱�Ƃ��ł���B
6.
�e�[�}���w��ł݂Ă̊��z
���d�߂Ȃǂ����̂悤�ɂ�����ƒ��ׂ�܂ł́A��ʐl�ɂ͊W�Ȃ��A���Љ�I�g�D�ɉ�������C�������̂Ŏ����ɂ͊W�Ȃ��Ǝv���Ă������A���{�̂��Ă������@���A�����ێ��@�ȂLj�ʐl���Y�����Ă�����A����Ǝ��s�ȂǑg�D�ɏ������Ă��Ȃ���ʐl���[���ւ���Ă��Đl���Ƃ͎����Ŏ�镨�Ǝv�����B
�Q�ƁF�L��t�|�P�b�g�U�@�A�E�B�L�y�f�B�A�A�R�g�o���N
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�
Windows 10 �ł����[�����瑗�M
��t����
�ƍߗ\�h�Ɛl��
�܂��A���_����q�ׂ����Ǝv���B
�������d���̖@�Ď��̂ɂ͎^�������A���݂̐��x�����d���ɂ͔��ł���B
�@
�@�i���d�߂Ƃ́j
1.
��������̔ƍ߂̋��d���ꎩ�̂��\���v���i����s�ׂ�ƍ߂ƕ]�����邽�߂̏����j�Ƃ���ƍ߂̑��́B�Ė@�̃R���X�s���V�[(conspiracy)�����̗�ł���B
2.
���{�̑g�D�I�Ȕƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@���i�ʏ́F�g�D�ƍߏ����@�A�g�D�I�ƍߏ����@�j�́u���́@�g�D�I�Ȕƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̖v�����v�ɐV�݂��邱�Ƃ���������Ă���u�g�D�I�Ȕƍ߂̋��d�v�̍߂̗��́B�����V�݂���@�ẮA��x2005�N8���̏O�c�@���U�ɂ��p�āB���N�̓��ʍ���ɍĒ�o����A�R�c���肵�����A2009�N7��21���O�@���U�ɂ��ӂ����єp�ĂƂȂ����B2017�N�̑�193��ł́A�u���d�߁v�̍\���v�������߂āu�e���������߁v��V�݂���u�g�D�I�Ȕƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@�����̈ꕔ����������@���āv�����t����o���ꐬ���E�{�s����Ă���iWikipedia�j
�Ȃ��Ȃ�A���������Ĕƍ߂��������邩���B���ł��邩��ł���B
�ƍ߂͍ߌY�@���`�́u�@���Ȃ���ΌY���Ȃ��v�̊ϓ_����P�ƔƂ̏ꍇ�A�\���v���A��@���A�L�ӂ̎O�̃K�C�h���C������A�����̌^�ɓ��Ă͂߂Ĕƍ߂���������̂ł���B���Ƃ̏ꍇ�ɂ��A���̎O�̃K�C�h���C���̒��ɂ�����ɎO�̗v�f������A���s�A�ߖ��A�v�f�i�ɒ[���A�������A�ŏ����j�Ƃ������Ə]����������B���̋��d�߂̋��Ƃ̏��������͂Ȃ�Ȃ̂��낤���B�������ƂȂ̂��B�����Ȃ̂��B���Ȃ̂��B�����̕��������ɞB���ł��邳��ɋ��d�����Ɣ��f������͈̂�̂Ȃ�Ȃ̂��낤���B�ߎ��̋������Ƃ̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ�̂��B
�g�D�ƍ߂̏����Ɋւ���@���U���̇A���̏ɂ͂��������Ă���B
���̊e���Ɍf����߂ɓ�����s�ׂŃe�����Y���W�c���̑��̑g�D�I�ƍߏW�c�̒c�̂̊����Ƃ��āA���Y�s�ׂ����s���邽�߂̑g�D�ɂ��s������̂̐��s���l�ȏ�Ōv�悵���҂͂��̌v��Ɋ�Â��������͕��i�̎�z�A�W�ꏊ�̉����A���̑��̌v��������ƍ߂����s���邽�߂̏����s�ׂ��s��ꂽ���͓��Y�e���ɒ�߂�Y�ɏ�����B
����
�Ⴆ�A�f�����������Ă���c�̂̂�����l���u�������̍��ɁA���̐������ᖢ���͂Ȃ����疾������j���悤�B�v�Ƌ��d���āA�����ɂȂ��āA�l�������߁A�u�߂܂肽���Ȃ��������ς��߂悤�B�v�Ƃ��u�|���������ς��߂悤�v�ƋC�������ω����A���d�����ł��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B
�������A���u�ƍߌv��v���o���オ���Ă����͎̂����ł���A�Љ�I�Ȕ�Q���o�ĂȂ������d�߂���������̂őߕ߂����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
���̗�Ȃ炨���炭���d������������������Ǝv����B
�����Ȃ�����d���������̊g����߂��ǂ�ǂ�i��ł��܂��̂ł͂Ȃ����낤���B
���d���������Ƃ́A��l�ȏ�̕����l�̐l�������ƍ߂����d������ŁA���̋��d�Ɋ�Â��Ĕƍ߂����s�����ꍇ�ɁA���s�s�ׂS���Ă��Ȃ����d�҂��������Ƃɂ�����Ƃ������_�ł���B����܂ł̊�ƂȂ��Ă����ō��ٔ���ł́u�d�c�i���d�̑��k�����邱�Ɓj�����݂��A�ƍ߂̎��s�����������Ƃ����i�ɏؖ�����邱�Ɓv�i���ܔ��N�܌��ō��ٗ��n���������j�����d���������̐����̂��߂ɕK�v�Ƃ��Ă����B
�܂����d���������́u���d�v�����d���́u���d�v�͓���̒�`�ɂȂ��Ă��܂�������s�̒���Ƃ�������K�v�Ȃ��Ȃ�A��قǏq�ׂ��悤�����d���������̊g����߂��i��ł��܂����Ƃ����O�����B
�g����߂��i��ł��܂��������ێ��@�Ɠ����������ɐi��ł��܂��댯�������Ȃ��炸����Ǝ��͎v���B
�����ێ��@�Ƃ́A���́i�c���j�⎄�L���Y����ے肷��^���������܂邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Đ��肳�ꂽ���{�̖@���B�iWikipedia�����p�j
���̖@���͓������Y��`�v���^���̌��������O�������̂ƌ����Ă������A�₪�ĉ��߂��g�債�Ă����A�@���c�́A�E�������A���R��`���A���{�ᔻ�͑S�Ēe���E�l���̑ΏۂƂȂ��Ă������ƌ����Ă���B�iWikipedia�Q�Ɓj
�ꌩ�A���d���̏Ƃ����ԈႤ�悤�Ɋ����邪�A�����ێ��@�����d���̉����Ⴂ�d�Ȃ邩���J�ɐ������Ă������Ǝv���B
�@�m�������d���������ێ��@�͍��{�I�ɍl�����Ƃ��č߂�Ƃ����Ƃ����҂ւ̏����Ɠ���̎v�z�����������̏�������Ƃ����傫�ȈႢ������B�܂�A�ȒP�ɂ��������d�����߂ɑ���l�����A�����ێ��@���v�z�ɑ���l�����ł���B�̂����d���������ێ��@�͌����ē����ł͂Ȃ��A�S���̕ʕ��ł���B
�@�ł́A�Ȃ������ێ��@�����d�����d�Ȃ�̂��Ƃ����ƁA��قǏq�ׂ��g����߂ł���B�����ێ��@�ŏ��͋��Y��`�v���^�����������O�������̂������B���������ߊg��͂ǂ�ǂ�i��ł����A�����{�͒e���̑ΏۂɂȂ��Ă��������j������B���݂����d�������̗��ꂪ����\��������B
�@�Ⴆ�A�ČR��n�̔��f�������ŒN�����߂܂����Ƃ���B��������Ƃł��c�̂͊Ď��̑ΏۂɂȂ�B�i���ۂɒN�����߂܂������Ƃɂ���ĔƍߎҏW�c�̉\�������シ�邩��j���������f�������Ȃ�u�������̓����ǂ��ł�낤�v���Ƃ��u�ČR��n�j�������v�Ȃǂ�����������Ȃ��B�����Ȃ����猋�ʓI�Ɉ�ʐl���ΏۂɂȂ��Ă��܂��B�\���̎��R�̒e���ɂȂ���B���Ԃ��ǂ��܂ŗ������Ă���̂��͒m��Ȃ����i��}�̐����s���j���Ɋ댯�ł���A���ꂪ���Δh�̈ӌ��Ȃ̂ł���B
�@�ł́A�Ȃ����d�߂����K�v������̂��B
���d�߂��K�v�ȗ��R�i�@����HP�����p�j
�ߔN�ɂ�����ƍ߂̍��ۉ��y�ёg�D���̏Ɋӂ݁A���тɍۓI�ȑg�D�ƍ߂̖h�~�Ɋւ��鍑�ۘA�����̒����ɔ����A�e�����Y���W�c���̑��̑g�D�I�ƍߏW�c�ɂ����s�����s�ׂ��d��ƍߐ��s�̌v�擙
�̍s�ׂɂ��Ă̏����K��A�ƍߎ��v�K���Ɋւ���K�肻�̑����v�̋K�������K�v������B���ꂪ�A���̖@���Ă��o���闝�R�ł���B
�@�܂�A���{�̐����ł͍��ۑg�D�ƍߖh�~���iTOC���j��������邽�߁i���炭���ꂪ�^���h�̍l����ő�̃����b�g���ƍl������j�@�����K�v�ƌ����Ă���̂����ʂ����Ė{���ɕK�v�Ȃ̂��낤���B
���A�͍��ۓI�ȑg�D�ƍ߂ւ̌��ʓI�ȑ��ړI�Ƃ��Ē�߂Ă���B�g�D�ƍߖh�~���Ȃ̂ŒP�Ƃ̔Ɛl�ɂ�閳���ʎE�������⎩���e�������͑傫�Ȕ�Q���o�Ă��A�ΏۂɂȂ�Ȃ��B���̎��_�Ńe����ɔ��������ł��ĂȂ����낤���B����ɑg�D�ƍ߂ɑR����@���Ȃ�A�Y�@77������������e���\���߂����邽�ߑΉ����邱�Ƃ��ł���Ǝv����B�����̖@���ɂ����̍��������邽�߂܂��܂����d�߂̕K�v���ɋ^�����o�Ă���B
�����ł�����Ə]�����ɂ��Đ����������B
���Ə]�����Ƃ́A���Ƃ������̑ΏۂƂ��Đ������邽�߂ɂ́A���ƂɈ��̗v�����[������邱�Ƃ�K�v�Ƃ���Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B���Ə]�����́A���s�]�����A�v�f�]�����A�ߖ��]�����Ƃ����R�̖��ɋ�ʂ���Ă���B
���s�]�����Ƃ́A���Ƃ̖����Ƃ��������邽�߂ɂ͐��Ƃ����s�ɒ��肵�����Ƃ�v���邩�Ƃ������ł���B
�����Ƃ́A�ƍ߂̌��ʔ����̊댯�����������Ƃ��������錋�ʔƂł��邩��A�����ƂƛƂɂ����ẮA���Ƃ����s�ɒ��肵�Ȃ�����̂悤�Ȋ댯�͔��������A���������āA������̖����́A���Ƃ̎��s�̒���ɏ]�����邱�ƂɂȂ�B
�v�f�]�����Ƃ́A���Ƃ��������邽�߂ɂ́A���Ƃ̍s�ׂ��ǂ̂悤�Ȕƍߗv�f��������邱�Ƃ��K�v���Ƃ������ŁA���݂̒ʐ��͍\���v���ɊY�������@�ȍs�ׂłȂ���Ȃ�Ȃ����A�L�ӂł���K�v�͂Ȃ��Ƃ��鐧���]�������ł���B
�ߖ��]�����Ƃ́A���Ƃɐ�������ߖ��͐��ƂƓ����ł���ׂ����Ƃ������ŁA����̔ƍ߂ɂ��Ă̂��Ƃ̐�����F�߂�ƍߋ������A�\���v�����d�Ȃ荇�����x�ŋ��Ƃ̐�����F�߂镔���I�ƍߋ������A�s�ׂ̋�����������Ƃ̐�����F�߂�s���������咣����Ă���B�i�ٌ�m�h�b�g�R���j
���Ə]�������Ԑڐ����̐������������Ǝv���B
��A��҂����҂��E�����Ǝv���A���˂ɓł����B�Ō�t�͂����m�炸���҂ɒ��˂�ł��Ă��܂����B���̏ꍇ�A���Ȃ��҂͎E�l�߁A�Ō�t���ߎ��v���߂ɖ����B�ŋ߂͍s�������Ɣƍߋ��������������Ĉ�@�_�Ƃ��������o���オ���Ă���A�ߖ��̓o���o���ł��s�ׂ̓��������ŏ����闬�ꂪ���邩�炾�B
���̋��Ƃ̏]���������ɊW���Ă��邩�Ƃ�����
�댯���A�������̍\���v�������d���̍\���v���Ɩ������o�Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B
�ƍ߂ɂ͎�ɋ��d�A�\���A�����A�����̒i�K�����邪�A���܂ł͊m���ȏ؋����Ȃ�����\���i�K�ł̑ߕ߂͂Ȃ������B�������A�������d�����K�p����邾�낤�B
�@�܂��A�Ď��͂ǂ�����̂��낤���A���炭�A�Ď�������@�ɓ����Ƃ�����i������Ǝv�����A�ʐM�T��@�͊����̒i�K�ɓ����ĂȂ��ƌ��@�̐l���̊ϓ_����g�����Ƃ��o���Ȃ��B�����Ȃ��Ă���Ɩ��炩�ɍ���A���d�߂ɉ������K�v�ɂȂ��Ă���B�Ƃ������Ƃ����d���͂�͂���������b�������ׂ����Ǝv���̂��B���̖@���ō��܂ł̊�ƂȂ��Ă�������⌻�s�@�̈ʒu�����K�v�Ȃ��Ȃ�A���Ȃ�@�̃o�������X������Ă��܂��B�@���͉�X�����̂��߂ɂ�����̂Ő��{�̂��߂ɂ�����̂ł͂Ȃ��̂ł���B���X���d���̓A�����J�̖@���̗A�����ł����������{�̖@���Ƃ̑����������͖̂ڂɌ����Ă���̂��BIS�Ȃǂ̍��ۓI�ȑg�D�ƍ߂������Ă���B�̂ɁA�m���Ƀe���Ȃǂ��܂߂��g�D�I�ȋ����ƍ߂𖢑R�ɖh�����Ƃ͑厖�����������d���ł̓e���̒P�ƔƂ͖��R�ɖh���Ȃ����A�Ď�������@�A���d�����Ƃ��锻�f��A���Ə]�����̏��������A�ȂǂقƂ�ǂ��B���ł���A���̖@�����\��Ă��܂�Ȃ����A���̂܂ܘb���i�ނ��ƂɎ��͔��Ɋ댯�������Ă���B���x����������ɂ܂��܂��b�������͕K�v�ł���B�����Ɠ��e���l�߂�ׂ��ł���B����277�̔ƍ߂��Ώۂ����g�D�I�ȔƍߏW�c�Ȃǂ̒��ۓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����ƌ���I�ɋ�̓I�ɁA�ƍ߂̑Ώۂ������ƌ��炷�Ȃǂ����Ă���Ȃ���P���K�v���낤�B���̂܂܂ł͋��炭�A�l�߂ݏo���Ă��܂����낤�B
�e�@��
16J118012�@�e�@��
�u�ƍߗ\�h�Ɛl���ɂ��āv
�������d���i�e���������߁j�ɂ��Č������ׂ����Ǝv���Ă���B
�u���d���̌������ׂ��_�v
�܂����d�����{���ɕK�v�Ȃ̂��A���d���̏��������͂ǂ��Ȃ̂��H�����Ăǂ��܂ł������K�p����̂��Ǝv���Ă���B
�܂����d�����{���ɕK�v�Ȃ̂������A���d�Ƃ͂S�ɕ�����ƂP�Ԏ�O�Ɉʒu������̂��Ǝv���B
|
���d |
�\�� |
���� |
���� |
�@�@�@�������炪�ƍ߂ɒ��肵�����@��
��ɍ��͂����ŋ��d����Ƃ������Ƃ͍��ӂ̈ӎv������Ƃ��ď����Ă����B
���d�Ƃ͓���̔ƍ߂�����ɂ������ĂQ�l�ȏ�̐l���Ōv�����݁i���d�j���ӁA���͂��݂��̈ӎv�m�F��������̂��Ǝv���B
�����Ď��s����Ƃ������ꂾ��
���܂Łi���d�����{�s�����O�j�͋��d�i�K�ŏ�������邱�Ƃ͂Ȃ������B
�߂܂�Ƃ������͔ƍ߂ɒ��肵�Ă��炾�B�����łȂ���Ή\���͂����Ă��߂܂��邱�Ƃ͕s�\�������B���d�����Ĕƍ߂ɒ��肷��Ƃ��̎҂��������d���������Ƃ����g�g�݂ŕ߂܂�A
�ԈႦ�₷���̂������d���������ŕ߂܂�ꍇ�͕K��2�l�ȏ�ŋ��d�i�ӎv�m�F�j�����A���s�̒�������Ă���B
���d���������ŏd�v�Ȃ��Ƃ͋N���Ă��܂����ƍ߂Ƃ̈��ʊW�A�����ď]�������̂Q���̂��Ǝv���Ă���B
�����Ŕ�����o�����Ǝv���Ă��邪���̔���͏]������S���������Ă���B
�w����P�x

���̔���̂R�Ԃ����Ȃ͕s�ϊW�ɂ������j�ɕv�̎E�Q�v������������j�̏]�Z��ɓ��e��b���m�F������Ă���ł�p�ӂ��Ă�������B���v���E���ۂɗp�ӂ����ł͎g�킸�Ɏ��������������Ă�����������g���������Ƃ�����i�E�����B
�u���̍l���A���_�v�@
�Ȃƕs�ϊW�ɂ������j�͊ԈႢ�Ȃ��������Ƃ̎E�l�߂��B�ł�p�ӂ����]�Z�킾���ł�p�ӂ��邱�Ƃ͈�@�s�ׂł��邪�A�ł͎g��ꂸ�v�̎��ƈ��ʊW�͂Ȃ����߁A�����K�p�O���Ǝv���B
����������͍Ȃƕs�ϊW�ɂ������j�͋������Ƃ̎E�l�߂����A�ł�p�ӂ����]�Z����������Ƃ��\���߂Ƃ��ĕ߂܂����̂��B
��قǂ��o������
|
���d |
�\�� |
���� |
���� |
�@�@�@�������炪�ƍ߂ɒ��肵�����@��
�����悪�ƍ߂ɒ��肵�����ǂ����ŋ��d�A�\���͔ƍ߂̒��肪������ʊW���Ȃ��Ɛ������Ȃ��B�i���d���{�H�O�j��������������̔ƍ߂��ł��g���Ă����Ƃ�����]�Z��͋������Ƃ����߂Ƃ��ĕ߂܂��Ă����B����Ȃ�킩�邪����̔���͂��ǂ���������������B
���������̔���ł͓ł͎g��ꂸ�v�̎����Ƃ̈��ʊW���Ȃ��ɂ�������炸�]�Z��̒j�����\���߂ŕ߂܂��Ă���B���ʊW���S����������Ă���B�����90���N�̔��Ⴞ�����̎��_�ŏ������d���Ɏ��Ă���Ǝv���B
�����ł����P������Љ�����B
�w����Q�x
���͖��ɋs�҂��Ă���܂�12�ŋs�҂���Ă������Ƃɂ��ӎv�\�͂��킪��Ă����B���̍ۂɕ��������ΑK�����ɍs���������ΑK�𓐂��Ă��܂����B���̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ�̂��B
|
�\���v���iT.B�j �q�ϓI�{��ϓI�A���ʊW ��������ʁi���ʊW�j |
|
��@���R�T�A�R�U�A�R�V �s�ז����l�A���ʖ����l �������ƍs�� |
|
�L���R�X�A�S�P �̈ӂ�����Ȃ��� �̈ӁA�ߎ� |
�u���̍l���A���_�v
�����ΑK�𓐂�Ε��͐ޓ��߂̋����ł��邪�A���͖����N�Ȃ��ߔƍ߂ɂ͂Ȃ炢�B�����̏ꍇ�͔ƍ߂̒��肪����F�߂��Ȃ���ق��Ȃ��̂ŁA���̏ꍇ�͕����Ԑڐ������F�߂�ꖺ�͖��߂ƂȂ�B
���͖����N���s�҂ɂ��ӎv�\�͂��Ȃ��Ȃ��Ă���\���v���ƗL�ӂɓ��Ă͂܂�Ȃ��̂Ŕƍ߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
���̔���͖����N�̔ƍs������Ԑڐ��ƂɂȂ����킯�ł͂Ȃ��B
�����P�����悤�Ȕ�����Љ�����Ǝv���B
�w����R�x
�ꂪ�����̑��q�i�����N�j�ɂ��X�̂��̂𓐂ނ悤�ɂƌ����A���q�͏�肭����ł��܂����B
����́w����Q�x�Ǝ��Ă��邪�������e���قȂ�B
�u���̍l���A���_�v
����̔���Ɋւ��Ă͎q���ɋs�҂Ȃǂ̍s�ׂ��Ȃ��ӎv�\�͂��͂����肢�Ă���A�����N�ƌ����ǂ������Ŕ��f���ł��邱�Ƃ��狤�����Ƃ̋����ŕ�͕߂܂��Ă���B
�����������Q�o���B
�w����S�x
�@A��B������B����2�l��C���E�����Ƌ��d����2�l�Ƃ��v���ʂP�O�O%�̓ł����܂��E�����B����͎E�l�߂��������d�����ŕ߂܂�B
�AA��B������B2�l��C���E�����Ǝv���Ă��邪�A���d���Ȃ��S���̋��R�ł��܂��ܓł�v���ʂT�O%���ꂻ�̌�C�͎��B����͋������ƂɎv���邩������Ȃ����A���̔�����������Ƃ���������2�l�ɎE�l�����߂ɂȂ����B
���̂��Ƃ����ƁA�Q�l�͓ł��ɓ��ꂽ���Ƃɂ��ǂ���̓łŎ��̂����ʊW���͂����肵�Ă��炸�ǂ����̓łŎ��̂��킩��Ȃ����߂��������Ȕ����ɂȂ����B
�@��2�l�ŎE�����Ƃ͌��܂��Ă���2�l�ŋ��͂����̂ŋ������Ƃŕ߂܂����B�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�������Ƃ��ߎ�
�w����T�x
����H���X�AY�AZ���łɉ������ꂽ�r�����C�ɗ��������ƂŁA�ł����ɒ~�ς����̋���H�ׂ��l�������a�C�ɂȂ��Ă��܂����B
�����X�AY�AZ���s���ӂɂ�藬���Ă��܂������Ƃɂ�肱���Ȃ��Ă��܂����B�N�̂����Ƃ����킯�łȂ�3�l�������Ƃ�������1�l�����Ƃ������ʊW�͂Ȃ�����3�l�Ƃ����Q�v���߂ɂȂ����B
�������g�D�I�Ȕƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@���͍��ۑg�D��g�D�I�ȔƍߏW�c�͕ʕ\�R�ɋL�ڂ���Ă���ƍߍs�ׂ̎��s�̏����s�ׂ��s�Ȃ������ɔ�����@���B
�댯���������炩�̖@�v�N�Q��^������̂��w���B
�悭���锻�Ⴞ��A�͂܂��l���Z��ł�ƒm���Ă���̂Ɍ�����R�₷�悤��B�Ɍ����R�₳�����BA�͂P�O�W����B�P�O�X���ōق����B
�ƂĂ��G�ɂȂ��Ă��܂����������ێ��@�Ƃ͍]�ˎ���ɂ������@���ł��荡�ł͂����Ȃ����������d���͂��̂��������ێ��@�̂悤�Ȃ��̂ɂȂ�Ǝv���B
���d�̒i�K�ŕ߂܂�Ƃ������Ƃ͂�����m�F����Ƃ�����Ƃ����݂���B����͂��̂����v���C�x�[�g�ȂƂ���܂ł��Ď������̐l����N�Q���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
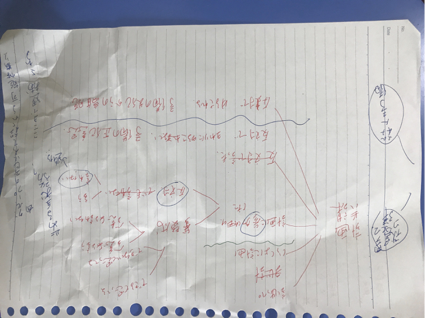
��������d���ɂ�錜�O���ׂ��_���������B�ȏ�ŏI���B
�����@�x�@���̂��߂̕�����₷���Y�@
�@�@�@�|�P�b�g�Z�@
�@�@�@����{�g�삳��{���Ȃ�����{�P�W�g
���V��
��b���{���K���|�[�g
16J118019�@���V��
�e�[�}�u�ƍߗ\�h�Ɛl���v
���_
�ƍߗ\�h�Ɛl���͂����Ɛ[���l����ׂ����Ǝv���B
1.���@�Ɛl��
�@���{�����@�ɂ͍����̐l�������@������߂��Ă���B���Ȃ킿�A���@���l���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B���@��11���ɁA�u�����́A���ׂĂ̊�{�I�l���̋��L��W�����Ȃ��B���̌��@�������ɕۏႷ���{�I�l���́A�N�����Ƃ̂ł��Ȃ��i�v�̌����Ƃ��āA���y�я����̍����ɗ^�ւ���B�v�Ǝ�����Ă���B�l�������@��V�c���牶�b�Ƃ��ė^����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�l�Ԃł��邱�Ƃɂ�蓖�R�ɗL����Ƃ���錠���ł��邱�ƁA�l���������Ƃ��Č����͂ɂ���ĐN����Ȃ��Ƃ������ƁA�l���́A�l��A���A�g���Ȃǂ̋�ʂɊW�Ȃ��A�l�Ԃł���Ƃ����������ꂾ���œ��R�ɂ��ׂċ��L�ł��錠���ł���Ƃ������ƁA�Ƃ����R�̏d�v�ȊϔO���݂邱�Ƃ��ł���B���͂������݂�Ƃǂ��������O�̍l�����̂悤�Ɏv���Ă��܂��B���������̂悤�ȍl������1789�N�̃t�����X�l���錾�̍l�������L�܂������ʂł���A���{�ɂ����Ă͑���E����ɂȂ��Ă悤�₭���y�����l���ł������B
�@
�ȏ�̂悤�ɍl����ƁA���{�����@���ۏႷ���{�I�l���Ƃ́A�i�l�Ԃ��Љ���\�����鎩���I�Ȍl�Ƃ��Ď��R�Ɛ������m�ۂ��A���������ێ����邽�߁A����ɕK�v�Ȍ��������R�ɔF�߂��邱�Ƃ�O��Ƃ��āj���@�ȑO�ɐ������Ă���ƍl�����錠�������@�������I�Ȗ@�I�����Ƃ��Ċm�F�������́A�Ƃ������Ƃ��ł���B�܂��ɑ��d�ɒl���錠���Ƃ����邾�낤�B
2.�Y�@�Ɛl��
�@�Y�@�ɂ��l�����[���ւ���Ă���B�O�ɂ��łĂ����t�����X�l���錾�́A���E�̖����`���W�j��A�L�O��I�Ȓn�ʂ��߂Ă���B��{�I�l���A�l���匠�A�v�z���_�̎��R�A���L���̕s�N�ȂǁA���̎������ɂƂ��Ă͓�����O�̂��Ƃ�搂��Ă���B�������A���̂���͒N�ɂł��^������l���̊ϔO�ł͂Ȃ��A�M���A�m���A�����̐g���ɂ�������炸�A���l�̒j���ɂ͕����ɗ^������Ƃ������̂������B����͗��j�ɂ����Ĕ��ɉ���I�Ȃ��Ƃł���Ǝv���B
�t�����X�l���錾�́A�ƍ߂ƌY���Ɋւ��āA�ߌY�@���`�i�V���j�A����@�̋֎~�i�W���j�A���߂̐���i�X���j�荞��ł���B�g�����̑��݂�������A�ꐧ�N���̎傽���ɂƂ��āA�ǂ��Ƃł����R�����Đl�����S�����A����������Ă��̎|���������A����͏��Y���邱�Ƃ͊ȒP�Ȃ��Ƃł������B�������[���b�p�̖����ٔ��͂��̓T�^�ł���B
3.�ߌY�@���`
�@�Y���̖ړI�Ƃ��ĉ����Y�_�i�߂ɂ����ĐӔC��Njy���A�߂����킹��j�ƖړI�Y�_�i�ڂ������Ɍ����āC�ƍߐl�̍ĔƖh�~�̂��߂ɉȂ�����ׂ��j������B�u�@���Ȃ���Δƍ߂Ȃ��A�@���Ȃ���ΌY���Ȃ��v�Ƃ������t������A����̓h�C�c�̌Y�@�w�҃t�H�C�G���o�b�n�̌��t�ł����āA�߁i�ƍ߁j�Y�i�Y���j�@���`��\���Ă���B���ꂪ�\���v���ɂȂ���B
�ߌY�@���`�͐�����
�E���m���̌���
�E����@�̋֎~
�E�ސ����߂̋֎~
�E�@����`
�E�f���[�v���Z�X
���o���B�킪���ł́A����@�I�ɂ́A�Y���@�K�����m���Ɍ�������A�����I����������L���Ȃ��ꍇ�ɂ́A���@��31���̋K�肷��K���葱�����ᔽ�ƂȂ�A�ጛ�Ɣ��f����邱�ƂɂȂ�B
4.�ƍ߂Ǝ��R��
�@���{�����@�ɂ�莩�R�Ɛl���͕ۏႳ���B�������A�ƍ߂�Ƃ����ꍇ�́A���R�͈�U�S�ۂ���A�S������������B�@�����ƂƂ��ē��R�̍s�ׂł���e�Ղɂ��̐��x�͗����ł��邪�A��胉�C�������ꍇ�A���̎҂̐l���͓V�����܂��Ƃ����邱�ƂȂ����D����鎖�ƂȂ�B���Ȃ킿���Y�ł���B�����Ɏ��R������������Ă���ƍl����B���@�ɂ́A���_�I���R���A�o�ϓI���R���A�g�̓I���R������߂��Ă���B�ƍ߂�Ƃ����ꍇ�Ɋւ���Ă���̂͐g�̓I���R���ł���B����ɂ́A�z��I�S����������̎��R�i18���j�A�@��葱�̕ۏ�i31���j�A�Z���̕s�N�i35���j�@��^�ҁE�퍐�l�̌����ۏ�i33���A36�`39���j������B������߂Ă���ɂ�������炸�A�ƍ߂�Ƃ����炱�̌����͐N�Q����Ă��邱�ƂɂȂ�B�����ɔƍ߂Ɛl���ɖ�����������ƍl����B
�����܂ł����_�ł���B�������A�����𗝉��ł��Ă��Ȃ��ƍ���̃e�[�}�̓��e�𗝉����邱�Ƃ�������������߁A���K�ƂƂ��ɏq�ׂ����Ă�������B�������炪�{��ł���B
5.���ƂƋ�������
�@���Ƃɂ�3�̎�ނ�����B
�E�������Ɓi�U�O���j
�E�����Ɓi�U�P���j
�E���Ɓi�U�Q���j
�����͂��ׂĐ��Ƃɋ��Ƃ��֗^����Ƃ����\���ł���B
�ƍ߂̎��s�s�ׂɊւ�������s�������Ƃ����łȂ����d���������̎҂��A�������������ƂƂ��Ĉ�����B�i���d���������j�B���`�̋��Ƃ́A���Ƃł͂Ȃ������Ƌy�����Ƃł���B
���Ƃ̐����Ƃ��ċ��Ə]�����Ƃ������̂�����B����́A���Ƃ����s���Ȃ�������A�����E���͏�������Ȃ��Ƃ������̂ł���B���̏]�����ɂ��āA���Ƃ��ƍ߂����s�����Ƃ���ɂ͐��Ƃ͂ǂ̒��x�ƍߐ����v�������悢���Ƃ������ɂȂ�B����E�ʐ��́A�\���v���ɊY�����Ĉ�@�ł���悭�A�ӔC�����邱�Ƃ܂ł�K�v�Ƃ��Ȃ��Ƃ��闧����Ƃ��Ă���B
�Ⴆ�AX��A���E�Q����悤Y�������̂������P�[�X�ɂ�����
�@Y��A���E�Q������s�s�ׂɒ��肵�Ȃ�������X�̎E�l�����߂͐������Ȃ��B�i���Ə]�����j
�A���肵���x���P�S�Ζ����ł���ꍇ�A�x���g�ɎE�l�߂͐������Ȃ����A�w�̎E�l�����߂͐�������B�i�����]���`���j
�����ɂ����ċ����߂̓K�p�͂߂����ɂȂ��A�قƂ�ǂ����d���������Ƃ��ď�������Ă���̂�����ł��邽�߁A�w�Ƃx�����d���������Ƃ��ď�������ƍl������B�������A�x�������Ə������q����������ӔC���\�͎҂ł���A�w���Ԑڐ����ɂȂ�B
�@���Ƃ͋�̓I�Ȕƍߍs�ׂ��������čs�����̂ł���i�ƍߋ������j�B�����A�ߎ��Ƃɂ��Ă͑��݂ɗ����������Ĕƍ߂�Ƃ����Ƃ͂��肦�Ȃ��ƍl����̂ŁA�ƍ߂���������̂ł͂Ȃ��s�ׂ���������ƍl���Ȃ�����ߎ��Ƃ̋������Ƃ͔F�߂��Ȃ��͂��ł���B�������A�ߎ��Ƃ̋������Ƃ��m�肷�鎖�Ⴊ�����Ȃ��Ă���̂͊m���ł���B����E��ɂ����Ď��Ȃ̍s�ׂ�������Ȃ��A���̒��Ԃ̍s�ׂɂ��Ă��݂��ɔz�����ׂ����Ӌ`��������ꍇ���ߎ��̋������ƂƂȂ�Ƃ���Ă���B
�Ⴆ�A�H�ꂪ�łɉ������ꂽ�r�����C�ɗ��������ƂŁA�ł����ɒ~�ς��āA�����H�ׂ������̐l���a�C�ɂȂ����Ƃ���B����́A�H����̒N���̕s���ӂł���Ƃ������Ƃ��ł����A�ǂ̐l�����ʊW���ے肳��ĒN���Ɩ����ߎ��v���߂ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A���ʂ��������͍̂H����̒N���ł��邱�Ƃ͂����炩�ł��邽�߁A�ߎ��̋������Ƃ�F�߂邱�ƂŁA�W�҂��ߎ��ɖ₤�A����Ό����I�ȏ��������Ă���̂ł���B
�@�����łЂƂ��Ƃł�������e�ɂӂ�Ă������Ǝv���B
���Ɠ��̖��ŁA�`�͂a�ɍ��݂������Ă����B�����ŁA�`�͂a�̈��ݕ��̒��ɖ��50�O�������ꂽ�B�`�͂��̖�̒v���ʂ�50�O�������Ǝv���Ă���B�����Ƃ��A�b���a�ɍ��݂������Ă����B�����ŁA�b���������ݕ��ɖ��50�O�������ꂽ�B�������b���v���ʂ�50�O�������Ǝv���Ă���B�������A���̖�̒v���ʂ�100�O�����ł���A�a�͎���ł��܂����B���̏ꍇ�̂`�͉��߂ɂȂ�̂��B�Ƃ������̂��o�肳�ꂽ�B���̖��̃|�C���g�Ƃ��Ă͋������ƂɂȂ�̂��A�E�l�߂Ȃ̂��A���Q�߂Ȃ̂��ł���B�`�Ƃb�͓�������ɍ��݂������Ă������A�`�Ƃb�͈ꏏ�Ɍv��������̂ł͂Ȃ��A���܂��ܓ����ɉ��Q�s�ׂ������̂ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ��������Ƃ����B�܂��`�͎E�����Ǝv��50�O�����̖����ꂽ���A�v���ʂ�100�O�����ł��邽�߁A�`�����̔ƍs��������a�͎���ł��Ȃ��������낤�B���̏ꍇ�A���Q�߂ɂȂ�ł��낤�B�������A�b���ƍs���s�������ߒv����100�O�����ɂȂ�a�������߁A�`�͎E�l�����̋������ƂƂȂ�B
6.���Ƃ̏����
�@���Ǝ҂̔F���Ɛ��Ǝ҂����s�����ƍߎ����Ƃ����Ⴕ�Ă����ꍇ�̍���ɂ��Ăǂ��Ȃ�̂����ɂȂ�B����E�ʐ��ł́A���낪����̍\���v���͈͓̔��ɂ��邩����A�q�̂̍���i�e�̂͂P�j�ł�����@�̍���i�q�͕̂����j�ł���A�̈ӂ͑j�p����Ȃ��Ƃ��闧��ł���Ƃ��Ă���B�i�@��I�������j
�Ⴆ�A�w�͂x�ɑ��A�m�荇���̂`�̉Ƃ͂�������������A�N�����Č�����D���悤�ɋ������x�����̋C�ɂ������B�x���`��ɍs���Ă݂��Ƃ���x�������d�œ��ꂻ�����Ȃ��̂ŁA�f�O�������̂́A��������������ׂ̂a��ɐN�����A�M�����𓐂B���̏ꍇ�A�x�͏Z���N���߁E�ޓ��߂ɂȂ�͓̂��R�����A�w�͏Z���N���E�ޓ��e�����߂ɖ����̂����ɂȂ�B�w�ɂ��Ă݂�`�����肵�ċ��������̂����A�����ƌ������̂ł����āA�ׂ̂a��Ŏ��s����A���������̂͋M�����Ƃ����̂ł́A�ʂ̔ƍ߂ł͂Ȃ����ƍl�����B�������A���̍���͓���̍\���v���Ԃ̍���̏ꍇ�ɊY������B�w�̋����ɂ���Ăx���Z���N���E�ޓ��̔ƈӂ��A���̔ƍ߂����s�����ȏ�A���R�w�̌̈ӂ͑j�p����Ȃ��ƍl����B
�܂��ʂ̗��������ƁA�w�͂x��Ƌ��d���A����̂`��ɐޓ����邱�ƂƂ��A�x�炪�N�����A�w�͊O�Ō������Ă����Ƃ���A���͂`��͗���ł͂Ȃ��������߂x��͂`�������ċ��������ꍇ�A�w�͉��߂ɖ����̂��B����́A���s���������Ƃw�̔F���Ƃ̊Ԃ̍���ł���ƍl����B���̏ꍇ�A�w�͍\���v���̏d�Ȃ�y���ق��̐ޓ��ŐӔC������ł��낤�B���ɁA���������d���A�w�͊O�Ō�����x�炪�`��ɐN�������Ƃ���A���܂��ܗ���ł���ޓ��œ��̂ł���w�͐ޓ��̋������Ƃɂ����Ȃ肦�Ȃ��ƍl����B
�@�\���߂ɂ��Ă͑����ɋK�肪�Ȃ��A�e���̕��A�E�l�A�����Ȃǎ�̏d�߂Ȕƍ߂ɂ��āA�����\������������K�肪�u����Ă��邾���ł���B�������A�������\���߂ɂ��Ă̑����̋��Ɨ�͓K�p�����̂����ƂȂ��Ă��܂��B
�@���������Ȃ�A�E�l�̎�i�Ƃ��ė��p�����̂�m��Ȃ���_�\�[�_��n�������A����͌��ǎ��s�ɒ��肵�Ȃ��������Ăɂ����āA�E�l�\���߂̋������Ƃ��F�߂�ꂽ�P�[�X������B�����A�\���߂ɂ��ċ��Ɨ�̓K�p���Ȃ��Ƃ���A���̊֗^�͕s��ɂ����B���̃P�[�X�̎��Ăɂ����āA���Ƃ����̂܂E�l�̎��s�ɒ��肵�Ă���A�퍐�l�͎E�l�����Ȃ�����̋��d�������ƂȂ��������Ƃɖ����B�����ł͋��d�������ƂɂȂ肪�������A�d�c�̎����A�֗^�̒��x�Ȃǂɂ���Ă����Ƃŏ������邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B
7.���d���̕K�v���Ɗ댯��
�@�@����܂ŁA�E�l�߂⋭���߁A���e�W�̔ƍ߂ȂǁA��������ꂽ�d��ƍ߂Ɍ��肳��āA�\���߂Ƃ������̂��K�p����Ă����B����A����܂ł����d���߂ɖ₤�Ă���ꍇ���������B���ꂪ���d�������Ƃł���B���d�������Ƃł́A�����̂��߂ɂ͏��Ȃ��Ƃ��ƍ߂̎��s�����肳��Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���B�ƍ߂������̂��̂ƂȂ��Ă���Ƃ��ɁA���̐ӔC��₦�鋤�Ǝ҂͈̔͂����ƂȂ��āA���d�ɉגS���������̎҂��ӔC��₦��Ƃ����̂����d�������Ɨ��_�Ȃ̂ł���B�������A���d���̑傫�ȈႢ�́A�������܂߂����s�s�ׂ����肳��Ă��Ȃ��Ă��A���̍��ӂ����ō߂���������Ƃ����_�ł���B2�l�ȏ�̎҂��ƍ߂��s�����Ƃ��ӎv��v���邱�Ƃł���A����ȏ�́A�Ⴆ�ΒN���ɓd�b��������A������Ƃ������ƍ߂̏����s�ׂɎ�肩���邱�Ƃ���������̗v���ƂȂ��Ă��Ȃ��B�܂��\���߂����O�̒i�K�A�����Ď��s��Ȃ����d���߂ɖ₨���Ƃ������̂Ȃ̂ł���B
���d����1999�N�ɐ��肳�ꂽ�g�D�I�ƍ߂̏����y�єƍߎ��v�̋K�����Ɋւ���@���̋K��P�������̂ł���B�g�D�I�ƍߏ����@�ɑ����d���Ƃ����V�����ތ^�����悤�Ƃ��Ă��āA�������d���̓K�p���A������ɍL���邨���ꂪ����B���́A�����̐l���𐧌����A�s���Ȏ����܂��^�p���s����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�g�D�I�ƍߏ����@�̓K�p�Ώۂ́A����Ő������ꂽ���d���̓e���������߂Ɛ������Ă���B�I�E���^������ŋ��A�I���I�����\�A�\�͒c�Ȃǂɂ��K�p����Ă��đg�D�I�Ȕƍ߂ɑΉ�����ړI�ł��K�p�����\��������B�����߂ł��邪�A�I�E���^�����̃g�b�v�͌���ŃT�������܂������s���Ƃł͂Ȃ����A��d�҂Ƃ��Ă��댯���ł��邽�߁A�E�l�߂̋��d�������Ƃɖ���A���Y���m�肵�Ă���B
���d��������ɒ�o�����w�i�̂ЂƂɁA�R�N��ɓ����I�����s�b�N���T���Ă��鎖�����B�e���݂̂������܂�ړI�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�e�����X�g���܂߂�������g�D�ƍ߂������܂�Ώۂł���A���������̏���߂Ă���̂��e�������łȂ��̂ł���B����ɂ��̖@��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ő�̗��R�Ƃ��āA���ۏ����y���邽�߂ɁA�����@������Ƃ������ƂȂ̂ł���B���̏��͂Ȃ�Ȃ̂��Ƃ����ƁA��Q���Ƒ�T��������ɏ�����Ă���B���{�͂��v�����������肵�Ă��鍇�Ӎ߂̕���I��ł��āA���ꂪ��������d���ł���B�@�Ď��̂͂ǂ��������̂ŁA����������߂ɂȂ�̂��Ƃ����ƁA����͍���̖@�Ă̂Q���Ɖ����ĂU���̂Q������ɏ�����Ă���B�@�@
�����đ�Z���̓�@���̊e���Ɍf����߂ɓ�����s�ׂŁA�e�����Y���W�c���̑��̑g�D�I�ƍߏW�c�̒c�̂̊����Ƃ��āA���Y�s�ׂ����s���邽�߂̑g�D�ɂ��s������̂̐��s���l�ȏ�Ōv�悵���҂́A���̌v��������҂̂����ꂩ�ɂ�肻�̌v��Ɋ�Â��������͕��i�̎�z�A�W�ꏊ�̉������̑��̌v��������ƍ߂����s���邽�߂̏����s�ׂ��s��ꂽ�Ƃ��́A���Y�e���ɒ�߂�Y�ɏ�����B�������A���s�ɒ��肷��O�Ɏ����҂́A���̌Y�����y���A���͖Ə�����B
�ƍ߂���ړI�̑g�D�ŁA�X�ɂ��̑g�D�ɂ͂�����Ǝw�����ߌn���Ɩ����̕��S�������āA���x���������Ċ��ɔƍ߂�����Ă���g�D�ł̊����Ƃ��āA�l�ł͂Ȃ��g�D�Ƃ��Ĕƍ߂���邱�Ƃ��v�悵���ꍇ�ɁA���̌v�悵���l�̂����̈�l�ł�������p�ӂ�����A����p�ӂ�����A����̉�����������Ƃ�����������������A���̌v�悵���l�����͔�����B�v������s�Ɉڂ��O�Ɏ�����߂͌y���Ȃ�B�ǂ̔ƍ߂��ΏۂɂȂ邩�͌��̕\�ŕ��ׂ�B�Ƃ������̂Ȃ̂ł���B
�@�����悤�Ȏ��������ƌY�����y���Ȃ�Ƃ������@�����ȑO�ɂ��������B���ꂪ�����ێ��@�ł���B�����ێ��@���ł́A�X�p�C�s�ׂ�����ɍs�Ȃ��Ă����B�X�p�C�ƂȂ����҂����������A�ړ��ĂƂ���l������ߕ߂�����A�X�p�C���g�͎�������ď�����Ƃ��A�Ƃ����d�g�݂ł���B���d���������ێ��@�̍l���Ɠ����ł���B���d���́A�g�D�ƍߑ�̂��߂ɐ݂�������̂��Ƃ��āA�ƍߑg�D������邽�߂ɂ́A����ƍ߂��s�Ȃ��Ƃ��������ӎv���������l�X�̏W�c���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ӎv���������l�X�ł��邩�ǂ����ׂ邽�߂ɂ́A�X�p�C�������L���ł���B���d���ł��A�����ێ��@�Ɠ������A���s�ɒ��肷��O�Ɏ����҂́A���̌Y�����y���A�܂��͖Ə�����Ƃ̋K�肪�݂����Ă���B�W�c��e�����邽�߂ɃX�p�C�𑗂荞�݁A�����ێ��@�Ɠ��l�ɋ��d���f�b�`�����邱�Ƃ��A������ł��ł��Ă��܂��ł��낤�B���d���́A�g�D�e���@�Ƃ��ċ@�\����̂ł���B���ꂾ���ł��ƂĂ��댯�Ɏv���Ďd�����Ȃ��B
8.���d���Ǝ������̎��R
�@�܂��A���d���͎������ɂ��K�p�����\��������B��ʍ����ł��A���炩�̑g�D��c�̂ɓ����Ă��āA�����ʼn��炩�̔ƍ߂̑��k���s��ꂽ��A���������ژb�Ɋւ���Ă��Ȃ��Ă��A���d�����K�p����ď����ΏۂɂȂ��Ă��܂������ꂪ����B
�܂��A�\���̎��R������Ă��܂��\���ł���B�\���̎��R�́A�l�b�g��̔����Ȃǂɂ��傫���ւ�镔���ł���A����̎������͂r�m�r�Ȃǂ̃l�b�g�𗘗p���邱�Ƃ������Ȃ��Ă���B���܂Ńl�b�g��Ŕ������Ă��߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��������Ƃ��A������T�܂Ȃ������d���Ƃ��Ĉ����Ă��܂��Ƃ����\��������B�l�b�g��ł́A���܂��܂Ȏv�z���������l�����R�ɔ��������Ă��邪�A�c�̂̃z�[���y�[�W��c�̂̍\���������������Ă���̂������ł���B�����ŁA�l�b�g��ŁA�s�K�ȓ��e�̔��������Ă���c�̂���������A�}�[�N����\���������Ȃ�A�����āA�}�[�N���ꂽ�c�̂̍\�������A�����ƍ߂��\������悤�ȓ��e�̔��������Ă��܂��ƁA���̎��_�����d�����K�p����Ă��܂������ꂪ����Ƃ������Ƃł���B�l�b�g�ʼn��C�Ȃ����������Ƃ���A�����Ȃ�x�@������Ă��ĉƑ�{�����ꂽ��C�ӓ��s�����߂�ꂽ�肷��\��������̂��B
�Ⴆ�A����c�̂���k�Łu����ȕ��A�����Ă����炢������Ȃ��́v�ȂǂƔ���������A���̎��_�Őޓ��߂̋��d�ƌ����Ă��܂������ꂪ����̂ł���B���������̏ꍇ�A���������l�����ł͂Ȃ��A���̒c�̂ɎQ�����Ă���l���ׂĂ������̑ΏۂɂȂ邨���ꂪ����̂ł���B�����Ȃ��Ă��܂��A�\���̎��R���N�Q����A�l�b�g��̏W�c���댯�Ȓc�̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ��A���ꂪ��ʐl�̖��Q�ȏW�܂�ł������Ƃ��Ă��A���d�����K�p����Ă��܂��\��������̂ł���B
���Ƀv���C�o�V�[�����N�Q����鋰��ł���B�Ȃ��Ȃ�A���d����E�����邽�߂ɂ́A����1�l1�l�̌l�̒ʐM���e���Ď�������Ȃ�����ł���B���̎���ɋ��d���s����ꍇ�A�ʐM��i���g�p����ł��낤�B�����ŁA�{���@�ւ͒ʐM���e���`�F�b�N���邱�ƂɂȂ�B�܂��A�������ƍl������l���̉ߋ���o�����肷��̂ŁA�l�����\����Ă��܂��B���Ԑl�ɂ͌l���ی�@������A���l�̌l����ʐM���e�ׂ悤�Ƃ��Ă����e�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�{���@�ւ͍����̃��[�����e��ʐM�L�^�A�ߋ��̔ƍߓ��e��o�g�n�A�o�g�w�Z��Ζ����ȂǁA���ׂ邱�Ƃ͔�r�I�e�ՂȂ��ƂȂ̂ł���B���d�����������Ă��܂��ƁA������{���@�ւ��Ƃ����Čl�������炢�����̂̓v���C�o�V�[���N�Q����A�l��댯�ɂ��炳��Ă��܂����ꂪ����A���S�ł��Ȃ��B
�I�_
�ȏ�̂��Ƃ���A�ƍߗ\�h�Ɛl���͂����Ɛ[���l����ׂ����Ǝv���B���d���̖��͎��������Ԑl�ł͎�ɕ�������̂ł͂Ȃ��ł��낤�B�����I�����s�b�N�Ő��E������l���W�܂���C�x���g���J�����Ƃ��Ă���̂�����A���R�e����ɗ͂�����K�v������Ƃ����̂͊Ԉ�������Ƃł͂Ȃ��ł��傤�B���������̔��ʁA������������̂���������A���@�ɒ�߂Ă��錠�������Ɏ��R�����N�Q����Ă��܂����ƁA���܂Ŕƍ߂ɂȂ肦�Ȃ��������Ƃ��ƍ߂ɂȂ�߂܂��Ă��܂����ƁA�ی삳��Ă������̂����̋@�ւɂ���Ă����ɂȂ��Ă��܂����ƂȂǁA�l�X�Ȋ댯�����߂Ă���Ǝv���Ă���B�����������͂��ꂩ��̓��{��C���Ă������Ƃ��������l�ɓ��[���āA���̑�\�҂����߂Ă���B����ɂ��ւ�炸�A�������������댯�ɂ��炷�@��������͍̂l���������镔���ł���B
�ȏ�
�Q�l����
��b���{���K���ƃm�[�g
�x�@���̂��߂̂킩��₷���Y�@�@���X�ؒm�q
�͂��߂Ă̌��@�w�@��R�Ł@�����r�j���ҏ�
�l���Ɣƍ��@http://otasuke.goo-net.com/qa2368698.html
���d���\�T�̎����\�@http://www.jlaf.jp/iken/2004/iken_20040115_02.html
���d�� Q&A�@ http://www.anti-tochoho.org/kyz1/qaex.html
�댯���@https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%8A%AF
�Y���̖ړI�i����Y�_�E�ړI�Y�_�j�@http://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9236/
���R���ƎЉ�@http://www1.tcue.ac.jp/home1/takamatsu/101103/chapter3.html
�g�D�I�ƍߏ����@�u���d�߁v�́A�l�b�g��́u�\���̎��R�v��D�����H
https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-13560.html
���Ə]�����Ƃ��@https://www.bengo4.com/c_1009/d_4602/
�e���������߂���₷������@http://blogos.com/article/217041/?p=2
Windows 10 �ł����[�����瑗�M